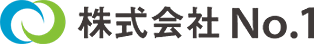カテゴリー: ファクタリング
定義を知ればファクタリングが分かる!融資との違い、メリット・デメリットを定義の観点から徹底分析
皆さんは、ファクタリングの定義をご存じでしょうか。
改めて「定義は?」と考えてみると、戸惑う人も多いことと思います。
始めてファクタリングを利用する人、あまり理解せずにファクタリングを利用してきた人は、ファクタリングの定義を理解しましょう。
そこからファクタリングの種類やメリット・デメリットへ広げることで、ファクタリングの全体像がよく見えるようになります。
この記事では、ファクタリングの定義や種類、融資との違い・使い分け、メリット・デメリットなどの基礎知識を、分りやすく解説します。
ファクタリングの定義
近年、特に中小企業の間で普及している資金調達方法に「ファクタリング」があります。
ファクタリングとは、会社の所有している売掛金をファクタリング会社に売却する方法です。
本来、売掛金は支払期日を待って初めて回収できるものです。
このため、売掛金の増加は資金繰りの負担につながります。
ファクタリングを利用すれば、支払期日を待たずに売掛金を回収できるため、資金繰り改善に効果的です。
もちろん、早期資金化がそのまま資金調達になりますから、銀行融資など従来の資金調達方法に比べて、資金繰り的なメリットの多い方法といえます。
政府は、資金調達の多様化を促すために、特に売掛金の活用促進に力を入れています。
その一環としてファクタリングの利用を奨励しており、ファクタリング周辺の法的整備も徐々に進んできました。
金融庁の定義
ファクタリングを簡単に説明すると「売掛金を売却すること」です。
しかし、これだけではファクタリングを十分に理解したとはいえません。
そこで、ファクタリングの定義を知っておくことで、理解が深まります。
金融庁では、ファクタリングを以下のように定義しています。
「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。
ファクタリングの法的根拠
金融庁の定義によれば、ファクタリングは債権譲渡取引です。
この定義が、ファクタリングの仕組みを理解する助けになります。
そもそも、ファクタリングで売却する売掛金は売掛債権の一種です。
売掛債権とは、支払期日に代金を受け取る権利であり、この権利を譲渡(売買)することを債権譲渡取引といいます。
ファクタリングの仕組みを表面的にみると、「売掛金を売却する」といったイメージがありますが、正確には「売掛金という『債権』を『譲渡』することで、対価(売掛金の買取代金)を受け取る『取引』」なのです。
金融庁の定義によって、ファクタリングが債権譲渡取引であることが分かれば、ファクタリングの合法性もおのずから明らかになります。
債権譲渡取引は法的に認められた取引であり、民法にも以下のように明記されています。
第四百六十六条
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2.当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
出典:出典:e-GOV法令検索「第四節 債権の譲渡」
ここ数年の間に、ファクタリングを装ったヤミ金業者が複数件摘発されました。
個人の給与を買い取る「給与ファクタリング」がその代表例です。
しかし、No.1をはじめとする正規のファクタリング会社が取り扱っているのは「事業者向けファクタリング」であり、債権譲渡取引のため全くの合法です。
金融庁の定義をみれば、ファクタリングの合法性には疑いがありません。
その他の定義
ただし金融庁の定義は、あくまでも金融庁の見解に過ぎません。
ファクタリングの現場では、もう少し広く捉えることが多いです。
例えば、銀行系ファクタリング会社の三菱UFJファクターは、ファクタリングを以下のように定義しています。
企業の売上債権(売掛金・受取手形)の総合管理をお引き受けするサービスです。
出典:出典:三菱UFJファクター「ファクタリングとは」
これは、金融庁の定義よりも広い見方です。
金融庁は、ファクタリングを「売掛金の債権譲渡取引による早期資金化サービス」と定義していますが、三菱UFJファクターは「売上債権の総合管理」としています。
総合管理とは、売掛金の回収代行、売上保証、与信管理などのトータルサポートです。
売掛金の早期資金化も、総合管理の中に含まれます。
日本でファクタリングが普及してきたのはごく最近のことで、現時点では明確な定義がありません。
金融庁は、日本の金融業界を監督する組織ですから、基本的には金融庁の定義が軸となります。
しかし、三菱UFJファクターのように定義をやや広く考えることも多いため、利用者としては、
「ファクタリングとは、売掛金の早期資金化を中心に、総合管理を行うサービスである」
といった捉え方が妥当でしょう。
ファクタリングの買取型・保証型
三菱UFJファクターの定義から、ファクタリングが必ずしも売掛金の早期資金化だけではないことがわかります。
ファクタリングには「買取型」と「保証型」があります。
自社のニーズに合わせて使い分けるためにも、このふたつの違いを理解しておくことが大切です。
買取ファクタリングの定義
ファクタリングに関する記載のほとんどは「買取型」や「保証型」といった前置きをせず、単に「ファクタリング」と表現しています。
これは、保証型に比べて買取型の方が圧倒的に普及しているためです。
ファクタリングを利用する会社の大多数は買取型の利用を前提としており、ファクタリング会社としても買取型の提供が中心となるため、「ファクタリング=買取型」と考えます。
金融庁が、ファクタリングを「売掛金の早期資金化」と定義するのも、このような実態を考慮しているのでしょう。
「買取型」であることを特に強調する場合、「買取ファクタリング」という表現が一般的です。
買取ファクタリングでは、支払期日前の確定債権(請求内容が確定した売掛金)を対象に、買取手数料を徴収して買い取ります。
売掛金の価値(売掛先の信用力)に応じて手数料率を設定し、額面金額から買取手数料を差し引いたものが買取代金となります。
保証ファクタリングの定義
保証型は、「保証ファクタリング」の表現が一般的です。
保証ファクタリングは、三菱UFJファクターの定義にある「総合管理」の一種であり、回収不能になった売掛金の支払いを保証するサービスです。
買取ファクタリングのように、売掛金を早期資金化するサービスではありません。
保証ファクタリングも、支払期日前の確定債権が対象ですが、手数料は保証料として請求されます。
基本的に、回収不能リスクの低い売掛金の保証を請け負うため、保証料は低く、買取ファクタリングに比べてローコストです。
ファクタリングの方式
なお、ファクタリングの方式には「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類があります。
2社間ファクタリングの定義
2社間ファクタリングは、ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式です。
金融庁の定義に沿って解釈すれば、「事業者が保有している売掛債権等を、売掛先が一切関与しない形で、期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」と定義できるでしょう。
2社間ファクタリングは、買取ファクタリング・保証ファクタリングのどちらにも利用される方式であり、保証ファクタリングは原則的に2社間ファクタリングで取引します。
売掛先が一切関与しないため、売掛先にファクタリングの利用を知られずにファクタリングできます。
ファクタリングの利用を知られると、売掛先によっては「銀行融資を受けられないのか?」などと経営悪化を疑うことが少なくありません。
このような疑いはできるだけ避けたいところ。
実際、ファクタリングを利用する中小企業のほとんどは2社間ファクタリングを選びます。
売掛先が関与しないため、手続きをスムーズに進めることができ、最短即日でのファクタリングが基本です。
売掛先に知られず、スピーディに資金調達できることが2社間ファクタリングのメリットですが、その反面、手数料が高い(額面金額の10~30%が相場)のが難点です。
3社間ファクタリングの定義
3社間ファクタリングは、利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引します。
金融庁のように定義すれば、「事業者が保有している売掛債権等を、売掛先が関与したうえで、期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス」と定義できるでしょう。
買取ファクタリングは、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングのどちらにも対応しています。
3社間ファクタリングの最大の特徴は、売掛先が関与することです。
売掛先に内諾を受けてから申し込むほか、売掛先に対して債権譲渡通知を行うため、ファクタリングの利用を必ず知られます。
また、利用会社とファクタリング会社だけではなく、売掛先とファクタリング会社の間でも手続きする必要があり、少なくとも1週間程度を要する点にも注意が必要です。
ただし、2社間ファクタリングよりも手数料が安く、額面金額の1~10%程度で利用できます。
ファクタリングと融資の違いは?定義から徹底比較
会社が資金を調達する際、真っ先に候補になるのが融資です。
銀行融資だけではなく、日本政策金融公庫や自治体による公的融資、ノンバンクのビジネスローンなど、融資には色々なものがあります。
融資が伝統的な資金調達方法であるのに対し、ファクタリングは新しい資金調達方法であり、使い分けに悩む人も少なくありません。
ファクタリングを正しく理解し、融資とファクタリングを適切に使い分けるには、「ファクタリングの定義」と「融資の定義」を比較し、違いを明らかにすることが大切です。
ここでは、ファクタリングと融資の定義の違いと、定義の違いによって生じる特徴・差異を解説します。
それぞれの定義
まずは、融資とファクタリングの定義をそれぞれみてみましょう。
融資の定義
融資の定義について、三井住友銀行の公式HPでは以下のように述べています。
融資とは、企業や個人が金融機関からお金を借りることを表す言葉で、主に事業資金が必要なときに使います。
出典:出典:三井住友銀行「融資とは?出資やローンとの違い、メリットや注意点を分かりやすく解説」
ここでは「金融機関からお金を借りること」を定義としていますが、金融機関に限らず、貸金業者などからお金を借りることも融資に属します。
つまり、融資の定義は「民間金融機関・公的金融機関・ノンバンクなど、事業として貸付けを行う相手からお金を借りて資金調達すること」です。
ファクタリングの定義
ファクタリングの定義は、ここまでもみてきた通りです。
金融庁の定義にある通り、「売掛金を売却し、早期資金化によって資金調達すること」がファクタリングの定義といえます。
定義による取引の違い
融資の定義は「借入れによる資金調達」、ファクタリングの定義は「売掛金の売却による資金調達」であり、定義の違いは明らかです。
この定義の違いにより、取引するものにも違いが生じます。
融資の定義と取引
融資の定義は「借入れによる資金調達」です。
したがって、取引するものは「現金」にほかなりません。
この「現金」は、銀行や貸金業者からみた場合には「貸付金」であり、融資を受ける会社からみた場合には「借入金」となります。
ファクタリングの定義と取引
ファクタリングの定義は「売掛金の早期資金化」です。
この場合、取引先するものは「売掛金」となります。
ファクタリングも資金調達である以上、現金を取引しているようにみえるかもしれません。しかし、ファクタリングは法的に債権譲渡ですから、建前としては「売掛金の取引」であり、現金(売掛金の買取代金)は債権譲渡に付随するものです。
定義による契約の違い
融資とファクタリングは定義が違うからこそ、取引するものが「現金」と「売掛金」で大きく異なります。
取引するものが異なれば、取引の内容や法的根拠も変わるため、それぞれ別の契約を結ばなければなりません。
融資の定義と契約
融資の定義は借入れであり、法的には金銭の消費貸借にあたります。
消費貸借について、民法には以下のように記載されています。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
出典:出典:e-Gov法令検索「第五節 消費貸借」
融資の定義に照らし合わせると、金銭消費貸借は「融資を受ける会社は返済することを約して、銀行や貸金業者から金銭を受け取ること」といえます。
この取引について、返済の条件や期日、担保・保証の設定、利息などを取り決めるのが金銭消費貸借契約です。
「融資の定義は借入れ→借入れは法的には金銭の消費貸借→融資の際には金銭消費貸借契約を結ぶ」
と考えるとわかりやすいでしょう。
ファクタリングの定義と契約
ファクタリングの定義は売掛金の早期資金化、法的には債権譲渡であることは、金融庁の説明にもある通りです。
債権譲渡については、民法第466条に定められていることも既に解説しました。
ファクタリングは債権譲渡ですから、契約の際には債権譲渡契約を結びます。
債権譲渡契約では、譲渡する売掛金の特定、売掛金の管理・回収、手数料、債権譲渡通知の有無、担保・保証の有無、償還請求権の有無などを取り決めます。
これも、「ファクタリングの定義は早期資金化→早期資金化は法的には債権譲渡→ファクタリングの際には債権譲渡契約を結ぶ」と考えるとわかりやすいです。
もっとも、ファクタリングの際には債権譲渡契約以外に、いくつかの契約を結ぶことがあります。
例えば2社間ファクタリングでは、債権譲渡登記代行契約(債権譲渡登記の代行手続きに関する契約)や売掛金回収委託契約(ァクタリング後の回収・決済に関する契約)を結ぶのが一般的です。
とはいえ、これらは債権譲渡契約に付随する契約です。
ファクタリングは定義として債権譲渡であるからこそ、債権譲渡の事実を明らかにする(第三者対抗要件を具備する)ために債権譲渡登記が必要となります。
また、債権譲渡によって債権者が「利用会社→ファクタリング会社」に変化するからこそ、回収の流れを契約によって明確化する必要があるのです。
定義から考えると、それぞれの契約の関係・位置づけがよくわかります。
定義による安全性の違い
定義と契約の違いに続き、安全性の違いもみていきましょう。
融資の定義と安全性
融資は、比較的安全性の高い取引です。
融資は定義的に金銭の消費貸借であり、融資する側は業として貸付けを行います。
このため、銀行ならば銀行法の規制対象となり、その他の貸金業者は貸金三法、つまり貸金業法・利息制限法・出資法の規制対象です。
貸金業者の活動は、貸金三法によって強く制限されます。
貸金業法では、業として貸付けを行う場合には金融庁への登録を義務付けています。
もちろん、健全性に問題がある業者は登録できません。
登録義務に違反した業者は、無登録営業として摘発されます。
金融庁に登録している業者も、融資の定義に基づき貸し付ける限り、上限金利による規制は避けられません。
上限金利を超えた場合、出資法5条2項によって5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
以上のように、様々な規制があることによって、融資の安全性は高いといえます。
もちろん、規制を守らない違法な貸金業者が存在することも事実です。
単純に「借入れであること」を定義とするなら、違法業者からの調達も融資といえます。
しかし、融資の定義である「借入れ」は法的に「金銭消費貸借」であり、金銭消費貸借に伴い様々な規制を受けます。
この意味において、「法規制を遵守した金銭消費貸借取引」こそ融資の定義に適うものであり、違法業者は融資の定義に当てはまりません。
ファクタリングの定義と安全性
現在、ファクタリングの安全性には問題があります。
ファクタリングは、ここ数年で急速に普及した資金調達方法であり、法整備が追い付いていません。
もちろん、ファクタリングの定義は「売掛金の早期資金化」、法的に「債権譲渡」であるため、債権譲渡に関する法規制を受けます。
しかし、貸金三法のような強力な規制がなく、新規開業の際に登録や免許は一切不要、なおかつ手数料の上限規制もありません。
そのため、現在のファクタリング市場は悪質業者が紛れ込みやすい環境となっています。
「ファクタリング業を装い、違法な貸し付けを行う業者」に対し、金融庁は「ヤミ金」と断定しています。
ヤミ金とは「闇営業(=無登録営業)の貸金業者」のことです。
融資の定義に基づき、業として貸付けを行えば貸金業法違反により摘発されます。
それを避けるには、ファクタリングの定義(債権の譲渡であり、金銭の貸付けではない)を隠れ蓑にするのが好都合というわけです。
実態は紛れもなくヤミ金ですから、このような業者を利用すれば経営悪化は避けられません。
ファクタリングの法整備は年々進んでおり、この問題はやがて解消されるでしょう。
しかしながら、現時点では、ファクタリングは融資よりも安全性が低いと考えてください。
定義による調達先の違い
定義の違いによって取引の内容や契約も異なるため、調達先も異なります。
調達先の違いは、資金調達の難易度を左右する要素です。
融資の定義と調達先
融資の定義は借入れですから、調達先は必ず「業として貸付けを行っている事業者」となります。
資金調達の軸となるのは、銀行や信用金庫・信用組合などの民間金融機関です。
また、日本政策金融公庫などの公的金融機関も調達先となります。
自治体・民間金融機関・信用保証協会が連携して融資する制度融資は、民間と公的の両方の側面を持っています。
このほか、ビジネスローンも借入れですから、ノンバンクなどの貸金業者も調達先のひとつです。
融資の調達先である民間金融機関・公的金融機関・ノンバンクは三者三様です。
民間金融機関は営利を目的に融資するため、審査が厳しく、資金を調達できないこともあります。
公的金融機関は営利目的ではないため、民間金融機関で資金調達できない会社でも資金調達可能です。
最も審査が緩いのはノンバンクのビジネスローン。
ビジネスローンならば、民間金融機関や公的金融機関の審査に落ちた会社でも、資金を調達できる可能性があります。
ファクタリングの定義と調達先
ファクタリングの定義は売掛金の早期資金化であり、資金の調達先は「売掛金の期日前の買い取りに対応している事業者」です。
このような事業者を、一般的には「ファクタリング会社(業者)」といいます。
なお、債権回収業者(サービサー)も売掛金の買い取りを行っていますが、これはあくまでも「不良債権の買い取り」です。
ファクタリングの定義は「早期資金化」であり、支払期日を過ぎて不良債権化した売掛金は買い取りません。
したがって、ファクタリングの調達先に債権回収業者は含まれません。
近年、ファクタリング市場の拡大によって、ファクタリング会社の数が増え続けています。
ファクタリング会社によって、事業規模やサービスの内容・方針は様々です。
また、ファクタリング会社はいくつかの系列に分類できます。
基本的な分類と定義は以下の通りです。
- 銀行系ファクタリング…銀行が提供するファクタリングサービス、または銀行のグループ企業が提供するファクタリングサービス
- ノンバンク系ファクタリング…銀行以外の金融事業者(信販会社や消費者金融業者など)が提供するファクタリングサービス
- 独立系ファクタリング…銀行・ノンバンクのいずれにも属さない、独立した事業者が提供するファクタリングサービス
この系列によって、ファクタリングの難易度やサービス内容が異なります。
資金調達難易度の目安は「銀行系>ノンバンク系>独立系」です。
ただし、融資における「民間金融機関>公的金融機関>ノンバンク」ほどの違いはありません。
定義による審査基準の違い
定義の違いは、審査基準の違いに色濃く表れます。
ここが、融資とファクタリングの使い分けの要ともいえる部分です。
融資の定義と審査基準
融資の定義は借入れであり、法的には金銭の消費貸借です。
この定義により、調達先は民間金融機関・公的金融機関・ノンバンクなどに分かれ、調達の難易度も異なります。
とはいえ、これらの調達先は全て、融資の定義に基づき貸付けを行っている点では同じです。
貸付けである以上、貸付金は確実に回収する必要があります。
基本的には、金融機関でもノンバンクでも、本業から得られる利益を返済原資とみなします。
事業がうまくいっているか、返済原資である利益が確保できるかどうかによって判断します。
つまり、審査基準は必ず「融資先」です。
返済力に問題がある会社は、そもそも融資の定義にそぐわない会社ですから、融資による資金調達は不可能です。
例えば「連続赤字に陥っており、黒字転換の見通しが立たない会社(=返済力に致命的な問題がある会社)」は、どの調達先からも融資を断られます。
ファクタリングの定義と審査基準
ファクタリングの定義は売掛金の早期資金化であり、法的には債権譲渡です。
これは、銀行系・ノンバンク系・独立系の全てに共通する定義であり、必ず債権譲渡のくくりで取引します。
債権譲渡取引で重要となるのは、取引する売掛金の価値です。
売掛金の価値相応に買い取ることができれば、業者側が過大なリスクを負うことはありません。
では、売掛金の価値を左右するのは何かといえば、「売掛金の内容」と「売掛先の支払能力」です。
売掛金の内容とは、売掛金の額面金額や支払期日です。
これにより、ファクタリング会社は収益性を測ることができます。
さらに重要なのが売掛先の支払能力。
後述の通り、債権譲渡を定義とするファクタリングでは、無担保・無保証、償還請求権なしが原則です。
これは、買い取った売掛金を無事に回収できれば収益を確保でき、買い取った売掛金を回収できなければ損失が発生することを意味します。
だからこそ、ファクタリングは「売掛先の支払能力」が審査基準となります。
後述の通り、ファクタリングは銀行融資よりも資金調達しやすいことがメリットですが、これも定義によって審査基準が異なるためです。
定義による保全策の違い
保全策とは、取引に伴い安全を確保することであり、簡単にいえば担保や保証によって損失に備えることです。
融資とファクタリングは、定義の違いにより保全策も異なります。
融資の定義と保全策
融資は、あらゆる資金調達方法の中でも保全を重視します。
これは、融資は定義的に金銭の消費貸借であり、貸付金の回収を前提とするためです。
上記の通り、返済原資は「本業からの利益」ですが、これが全てではありません。
企業の業績は常に変化し、利益から回収できなくなることもあり得ます。
そのリスクに備えるためにも、融資の時点で保全を図るのです。
融資における保全策のうち、主となるのは不動産担保と信用保証協会の保証です。
民間金融機関から融資を受ける場合、無担保・無保証で融資を受けられる会社は全体の1割未満です。
公的金融機関は、無担保・無保証での融資にも対応していますが、担保・保証があれば金利が安くなります。
また、ノンバンクでは無担保・無保証を基本としますが、不動産担保ローンでは銀行以上の担保評価を出すことも多いです。
つまり、公的金融機関やノンバンクも、担保・保証を軽視しているわけではありません。
融資の定義に基づく以上、担保・保証による保全は重視されるのです。
ファクタリングの定義と保全策
ファクタリングには、保全という概念がありません。
そもそも、担保・保証による保全は、貸倒れリスクの回避・軽減が目的です。
貸付金を回収できなくなった場合、担保資産の売却や信用保証協会の弁済によって貸倒損失を避けることができます。
もし、ファクタリングが定義的に「金銭の消費貸借」であれば、ファクタリング会社が保全を図ることもあるでしょう。
しかし、ファクタリングは定義的に債権譲渡取引であり、返済義務がありません。
返済義務がなければ、「返済できなくなったら場合に備えて…」という考え方が成り立たないのです。
このため、ファクタリングは原則的に無担保・無保証で利用できます。
逆にいえば、ファクタリングの定義が「売掛金の早期資金化」「債権譲渡取引」である以上、担保・保証付きの契約は不可能です。
担保・保証付きを条件とする場合、保全を目的としていることは明白です。
したがって、ファクタリング業ではなく実質的には貸金業とみなされます。
当然、貸金業に対する厳しい規制を受けることとなり、ファクタリング業としての自由を失うのです。
正規の業者は、必ずファクタリングの定義(債権譲渡)に則って「無担保・無保証」で契約します。
健全なファクタリング会社か、ファクタリングを装う違法業者かを判断するためにも、担保・保証の有無は重要です。
定義による償還請求権の違い
融資とファクタリングの定義の違いは、償還請求権の有無にも表れます。
償還請求権とは、譲渡した債権が回収できなくなった場合、譲受人が譲渡人に買い戻しを求める権利です。
償還請求権があれば買戻し請求が可能、償還請求権がなければ買戻し請求は不可能となります。
融資の定義と償還請求権
融資の定義は金銭の消費貸借ですから、債権譲渡を行うものではなく、償還請求権の有無も関係ありません。
ただし、融資には色々なタイプがあり、場合によっては償還請求権を伴います。
例えば、銀行に受取手形を買い取ってもらう手形割引は、債権譲渡としての側面を持っています。
しかしながら、実質的には手形を担保とする融資でもあり、法的解釈も複雑です。
手形割引で資金調達する際、「償還請求権あり」の契約となります。
したがって、銀行に譲渡した手形が不渡りになった場合、利用会社は手形を買い戻さなければなりません。
融資は定義的に償還請求権とは無関係、しかし一部の手形割引などの融資形態では償還請求権ありと考えてください。
ファクタリングの定義と償還請求権
ファクタリングの定義は債権譲渡ですから、償還請求権の有無が大きなポイントとなります。
一般的に、債権譲渡と償還請求権はセットで考えることが多いです。
「償還請求権あり」の場合、譲渡した売掛金が回収不能になれば買戻しを求められます。
しかしながら、ファクタリングは「償還請求権なし」が原則です。
「償還請求権あり」の場合、譲受人はほとんどリスクを負わない形で債権譲渡が成立します。
回収不能時、債権譲渡に伴う金銭の返還を求めることができるため、実質的には「債権を担保とした貸付け」とみることもできます。
金融庁の解釈でも、「償還請求権ありのファクタリングは、実質的には貸付け」です。
したがって、貸金業者としての規制を受けるため、金融庁への登録や上限金利の順守を求められます。
つまり、「償還請求権あり」でファクタリングするならば、その業者は貸金業登録をしており、手数料率も年利換算で20%以下でなければなりません。
実際、手形割引を行っているのは銀行、もしくは貸金業登録を行っている手形割引業者だけであり、なおかつ年利20%以下を守っています。
だからこそ、手形割引は「償還請求権あり」の契約が認められるのです。
多くのファクタリング会社は貸金業登録をしておらず、年利換算で20%を超える手数料を請求しています。
この場合、貸金業法違反や出資法違反を避けるには、「償還請求権なし」での契約が必須です。
「ファクタリングの定義は債権譲渡(貸付ではない)→債権譲渡であれば償還請求権なし」と考えてください。
定義による調達コストの違い
資金調達を選ぶ際には、調達コストを比較すべきです。
この時、定義を考えることによって、調達コストの根拠がみえてきます。
融資の定義と調達コスト
融資の定義は金銭の消費貸借であり、調達コストを左右するのは金利です。
金利を規制する法律には、利息制限法と出資法があります。
利息制限法の「上限を超えた金利が無効となること」、出資法は「刑事罰の対象となる上限金利」について定める法律です。
上限金利は、融資額が10万円未満の場合には年20%、10万円~100万円未満の場合には年18%、100万円以上の場合には年20%となります。
融資の定義に基づき貸付けを行う事業者は、融資額に応じてこの上限金利を守らなければなりません。
ビジネスローンは金利が高いといわれますが、いかなる場合にも年利20%以下です。
銀行融資も規制を受けますが、実際には上限金利を大きく下回る設定(年2%程度)が一般的です。
金利は需給バランスや市場金利によって決まります。
企業が数百万円、数千万円の資金調達をする場合、ビジネスローン並みの金利を設定すれば、貸倒れリスクが非常に高くなります。
そのような金利では借り手がおらず、いたとしても貸倒れリスクが高いため融資は困難でしょう。
銀行は貸したい、しかし貸付先がないという「需要≪供給」の状態ですから、金利を安くせざるを得ません。
また、経済全体への影響も大きくなるため、日銀の金融政策により市場金利が調整され、結果的にビジネスローンよりも大幅に安くなるのです。
融資の定義は借入れですが、借入先によって金利の根拠が異なり、調達コストにも大きな差が生じることがわかります。
ファクタリングの定義と調達コスト
融資の金利は調達先によって変わりますが、変動するのはあくまでも年20%以下の範囲にとどまります。
これは、融資の定義が金銭の消費貸借であり、定義に基づく限り上限金利の規制を受けるためです。
これに対し、ファクタリングの調達コスト(手数料)は変動の幅が非常に広いです。
上記でも述べた通り、ファクタリングは法整備が不十分な状況であり、手数料に関する規制がありません。
定義的には債権譲渡であるものの、純粋な債権譲渡であるか、貸付けの要素を帯びているかによって、規制が大きく変わってきます。
後者の場合は上限金利の規制対象となりますが、定義に基づく純粋な債権譲渡である場合、上限金利の規制対象外です。
そもそも、利息制限法や出資法は貸付けに伴う金利を制限するものであり、債権譲渡に伴う手数料を制限するものではないからです。
したがって、現時点ではファクタリングの手数料の上限を明確に定める法律がなく、ファクタリング会社の裁量で決めることができます。
実際に、2社間ファクタリングの手数料の目安は「額面金額に対して10~30%」ですが、これは年利換算すると120~360%です(1ヶ月後に回収予定の売掛金の場合)。
もちろん、規制がないため120%以下あるいは360%以上の手数料を設定することもできます。
融資が「年利20%以下の範囲で変動」であることに比べると、ファクタリングの調達コストの変動幅は非常に大きいといえます。
だからこそ、ファクタリング会社を選ぶ際には、手数料をシビアに考える必要があるのです。
定義による資金調達スピードの違い
融資とファクタリングの定義の違いから、資金調達スピードについて考えてみましょう。
融資の定義と資金調達スピード
基本的に、融資は資金調達スピードが遅いです。
これは、融資は定義的に「返済義務を伴う取引」であり、返済力の見極めが重要となるためです。
融資先の返済力を判断するには、現状の経営と将来的な見通しを把握するために、決算書や経営計画書などを詳しく分析します。
融資担当者や支店長との面談も欠かせません。
融資担当者が分析結果と融資判断を稟議書にまとめた後、複数人の上司を経て支店長の判断に至り、案件によっては本部決済を仰ぎます。
この一連の流れにおいて、すべて「融資可」でなければ融資を受けることはできません。
このため、融資実行までには数週間~1ヶ月以上を要します。
ノンバンクのビジネスローンでは「即日融資可」とする業者もありますが、実際に即日で調達できるケースは少なく、数営業日~1週間以上c を要するのが一般的です。
融資の資金調達スピードが遅いのは、時間をかけて審査するためであり、それも全て「融資とは借入れである」という定義によるものです。
当然、「新規融資である」「調達額が大きい」「経営に問題がある」「担保・保証が不足している」など、審査に時間がかかる場合、資金調達スピードはさらに遅くなります。
ファクタリングの定義と資金調達スピード
ファクタリングは、資金調達方法の中でも特に資金調達スピードに優れています。
ファクタリングは定義的に債権譲渡であり、債権譲渡には返済義務がありません。
したがって、融資のように厳しい分析・判断を求められます。
2社間ファクタリングの場合、「申し込み→審査→契約締結(債権譲渡完了)」の流れを申し込みの当日中に完了し、即日で資金調達することも可能です。
審査では、入金確認書類や請求書の情報によって、売掛金の収益性や売掛先の支払能力を把握し、回収不能リスクを測定します。
審査の対象となる情報が極めて少なく、結果的に簡易審査になるケースが一般的です。
だからこそ、審査にあまり時間がかからず、最短即日で買い取ることができます。
最近では、2社間ファクタリングの手続きを全てオンラインで行う「オンラインファクタリング」も徐々に普及しています。
これも、定義的にはやはり債権譲渡であり、なおかつAI審査やクラウド契約の活用により、最短数時間での調達も可能です。
3社間ファクタリングは、2社間ファクタリングよりも時間がかかります。
ただし、手続きのうち時間を要するのは、主に債権譲渡通知・承諾手続きです。
3社間ファクタリングも定義に基づく債権譲渡取引ですから、返済力の見極めが不要であり、審査が簡単な点では変わりません。
だからこそ、1週間程度で資金を調達できるのです。
定義による調達可能額の違い
資金調達の目的は必要資金を調達し、確実に資金繰りを回すことです。
資金を調達できたとしても、必要資金を満たさなければ資金繰りはショートします。
あるいは、設備や新規事業への投資が不十分となり、期待した結果が得られません。
だからこそ、資金調達方法を選ぶ際には「調達可能額」も重要な基準となります。
調達可能額は、資金調達方法ごとの定義によって大きく変わります。
融資の定義と調達可能額
融資の定義は金銭の消費貸借であり、判断基準は「元金と利息を確実に回収できるかどうか」です。
銀行や貸金業者は、融資によって得られる利息が収益の柱ですから、返済力がある会社には積極的に貸付けます。
貸倒れリスクに問題がないかぎり、できるだけ多く貸し付けたいというのが本音です。
特に銀行は、借入れの動機が健全であり、返済力や将来的な見通し、あるいは担保・保証による保全が充足していれば、いくらでも融資します。
もちろん現実的には、銀行の貸付原資と融資先の返済原資は有限ですから、無限に借りられるわけではありません。
しかし、数億円~数十億円、大企業であれば数百億円単位での調達も可能です。
実際、トヨタ自動車は約30兆円の有利子負債を抱えています。
したがって、会社が資金繰りに必要とする資金は、おおむね融資によって調達可能といえるでしょう。
ただし、ビジネスローンは多額の借入れに不向きです。
ビジネスローンも融資ですから、定義的には貸付けであり、判断基準は「融資先の返済力」にほかなりません。
ただし、リスク許容度が異なります。
ビジネスローンは、主に「経営に問題があり、銀行融資を受けられない会社」と対象とするため、貸倒れリスクが高いことが前提です。
「貸付である」という定義に基づきながら、貸倒れリスクをある程度許容するのがビジネスローンといえます。
リスクを分散するには、特定少数に多額の融資を行うよりも、不特定多数に少額ずつ融資すべきです。
だからこそ、ビジネスローンの多くは融資上限額を数百万円~1000万円程度に設定しています。
ファクタリングの定義と調達可能額
ファクタリングには、明確な調達可能額がありません。
ただし、経営状況次第でいくらでも調達できるものではなく、融資に比べると少額になると考えてください。
これは、ファクタリングの定義が「売掛金の早期資金化」であり、手元の売掛金に依存するためです。
この定義は法的にいえば債権譲渡ですから、譲渡できる債権が手元になければ資金を調達できません。
つまり、ファクタリングの調達可能額は、手元の売掛金の総額とイコールです。
厳密にいえば、ファクタリングには手数料がかかるため、「調達可能額=手元の売掛金総額-手数料」となります。
また、ファクタリングでは支払期日前かつ請求済みの売掛金(確定債権)だけを対象とします。
未請求の売掛金は、特殊な場合を除いてファクタリングの対象外です。
もし、この会社が将来的に確定見込みの売掛金(将来債権)を所有していても、ファクタリングすることはできません。
例えば、月商1000万円、このうち信用取引の比率が100%、平均回収サイトを1ヶ月とすれば、手元には常に1000万円の売掛金があります。
したがって、この会社がファクタリングによって調達できる上限額は、「1000万円-手数料」です。
このように、「ファクタリングは債権譲渡」という定義によって、会社ごとに調達可能額は大きく変わります。
信用取引の比率が低い会社、回収サイトが短い会社、そもそも月商が少ない会社などでは、手元の売掛金も少なく、ファクタリングで調達できる金額も小さくなります。
逆に、月商が大きい会社、信用取引の比率が高い会社、回収サイトが長い会社などは、多額の資金調達も可能です。
このうち、特に影響が大きいのは回収サイトです。
月商1000万円において、回収サイト1ヶ月の場合の調達可能額(=手元の売掛金)は1000万円ですが、回収サイト2ヶ月の場合には調達可能額(=手元の売掛金)が2000万円となります。
回収サイトの長期化は資金繰りに悪影響を与えますが、ファクタリングを活用することで影響を緩和できます。
ファクタリングの定義によるメリット
融資とファクタリングの定義の違いを様々な角度で比較しました。
この比較によっても分かる通り、ファクタリングには様々なメリットがあります。
ここまでの内容を踏まえて、ファクタリングのメリットをさらに詳しくみていきましょう。
ファクタリングの代表的なメリットは以下11個です。
1.売掛金を早期資金化できる
金融庁の定義にもある通り、ファクタリングは売掛金を早期資金化するサービスです。
売掛金を早期資金化することによって、以下の2つのメリットが得られます。
- 売掛金によって資金調達できる
- 回収サイトを短縮できる
売掛金で資金調達できる
ファクタリングは、売掛金さえあれば資金を調達できます。
もちろん、「支払期日前である」「売掛先の支払い能力に大きな問題がない」といった条件はあるものの、不良債権でない限り高確率でファクタリング可能です。
ほとんどの会社は信用取引をしており、手元には常に売掛金があります。
手元の売掛金をファクタリングすれば、自社が必要な時にいつでも資金を調達できるのです。
中小企業は銀行融資への依存度が高い傾向がありますが、ファクタリングを取り入れることによって資金調達の多様化につながり、資金繰りの安定に大きな効果が期待できます。
回収サイトを短縮できる
また、支払期日を待たずに回収することで、回収サイトの短縮も可能です。
例えば、回収サイト1ヶ月(支払期日は30日後)の売掛金をファクタリングで即日現金化すれば、実質的な回収サイトは0日となります。
回収サイトが短ければ短いほど資金繰りがラクになるのが、資金繰りの原則です。
このように、ファクタリングには資金繰り改善効果もあります。
2.財務への影響が小さい
売掛金は、貸借対照表では資産の部の流動資産に分類されます。
これを売却することによって資金を調達するファクタリングは、「資産売却による資金調達」にほかなりません。
自社が所有している在庫(棚卸資産)や、不動産の売却による資金調達と同じです。
したがって、ファクタリングによる財務の変化は、「ファクタリングに利用した売掛金の減少」と「売掛金の買取金額分の現金の増加」だけです。
借入れではないため、負債は増加しません。
もちろん、自己資本比率や債務償還年数などの財務指標も悪化しないため、財務への影響は非常に小さいといえます。
このほか、借入れではないため返済義務もなく、資金繰りへの影響も軽微です。
3.銀行融資よりも資金調達しやすい
ほとんどの会社は、銀行融資によって資金を調達します。
銀行融資への依存度が高すぎると、銀行から融資を断られた場合に経営難に陥る可能性が高いです。
銀行は、あくまでも返済能力に応じて融資します。
返済能力に問題ありと判断した会社に融資することはありません。
一方、ファクタリングは利用会社の経営に問題があっても、利用できる可能性が高いです。
なぜならば、ファクタリングの審査対象は利用会社ではなく売掛先だからです。
ファクタリング会社にとって重要なのは、「買い取った売掛金が、支払期日にきちんと支払われるかどうか」に尽きます。
売掛先の支払い能力に問題がなければ、利用会社の経営がどうであろうと買取可能なのです。
このように、銀行融資とファクタリングでは審査対象がまるで違います。
普段からファクタリングを活用しておけば、急に銀行融資が利用できなくなった場合でも冷静に対処できるでしょう。
さらに、銀行融資は資金調達に数週間~1ヶ月を要しますが、ファクタリングは最短即日で資金調達できます。
この意味でも、ファクタリングは銀行融資に比べて利便性が高いです。
4.申し込みが簡単
ファクタリングは、簡単に申し込むことができます。
これも、ファクタリングの利便性が高いといわれる理由のひとつです。
ファクタリングに申し込む方法は、電話・FAX・メール・公式HPのフォームなど色々あります。
ポイントは、申し込みの際にファクタリング会社の店頭を訪問する必要がないということです。
銀行融資ならば、店頭を訪問せずに申し込むことは基本的になく、融資担当者と面会し、直接融資を依頼します。
融資の定義は借入れであり、信用を重んじるため、顔を合わせずに融資交渉はできないのです。
しかし、ファクタリングの定義は売掛金の早期資金化であり、債権譲渡で重視するのは売掛先の信用ですから、申し込み時の面談を重視しません。
また、ファクタリングは融資よりも少ない書類で利用できます。
特に優良ファクタリング会社では、手元の書類だけで申し込めるケースが大半です。
No.1のファクタリングサービスは、以下の4点にてお申込みいただけます。
- 直近3ヶ月の取引入金が確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表)
- 決算書直近2期分(勘定科目明細付で税務申告済みの捺印のあるもの)
- 成因資料(請求書・発注書・納品書など)
- 取引先企業との基本契約書
これらは全て、債権譲渡に必要な最低限の書類であり、ファクタリング会社はこれによって売掛先の信用を測ります。
少ない書類で申し込めるのも、ファクタリングが定義的に債権譲渡であるためです。
5.オンラインでさらに便利に
近年、ファクタリング業界でも徐々にオンライン化が進んでいます。
2社間ファクタリングの手続きをオンライン完結する「オンラインファクタリング」という仕組みです。
オンラインファクタリングも売掛金の早期資金化であり、定義は他の買取ファクタリングと変わりません。
オンラインファクタリングの登場によって、ファクタリングの利便性はさらに高まっています。
従来の2社間ファクタリングは、対面または郵送による契約が基本でした。
ファクタリングは定義的に債権譲渡であり、債権譲渡契約を必ず結びます。
この時、オンライン契約の仕組みがなければ、対面取引や契約書類の郵送取引によって契約するほかありません。
対面契約の場合、利用会社とファクタリング会社が遠方であれば、移動に時間がかかるためスピーディな資金調達が困難です。
郵送契約に至っては、書類のやりとりに数日を要するため、場合によっては3社間ファクタリングなみ(1週間程度)を要することもあります。
つまり、従来の契約方法では、ファクタリングの利便性を損なうことが多々あったのです。
オンラインファクタリングには、このような契約の問題がありません。
クラウド契約を用いることにより、対面・郵送による契約が必要なくなり、契約時の負担を大幅に軽減できます。
6.無担保・無保証で資金調達できる
上記でも比較した通り、融資とファクタリングは定義が違うため、保全策も大きく異なります。
融資は定義的に金銭の消費貸借であるため、担保・保証による保全が重要です。
特に銀行融資の場合、担保・保証が不足している会社は借入れが困難となります。
コロナ禍の影響も無視できません。
コロナ禍において、政府は様々な特別措置を行いました。
そのひとつに、「ゼロゼロ融資」があります。
ゼロゼロ融資の特徴は、実質無利子・無担保で融資する点です。
利子を自治体が負担し、信用保証協会が特別枠で保証することによって担保不足を補います。
通常、信用保証協会の保証枠は無担保8000万円、有担保2億8000万円が上限となりますが、この保証枠を使い切っている会社でも、ゼロゼロ融資で調達できる仕組みです。
今年に入ってから、ゼロゼロ融資の返済が本格化しました。
しかし、コロナ後の立て直しがうまくいかず、経営が正常化していない会社も少なくありません。
経営正常化には、それなりの資金が必要です。
コロナ禍でゼロゼロ融資を利用した会社は、信用保証協会の特別枠を返済しないうちは通常の保証枠が回復せず、新規に保証付融資を受けることができません。
このため、必要資金を調達できず、ゼロゼロ融資の返済負担によって倒産する会社が続出しています。
融資の定義によって考えるならば、特別措置といえども返済義務を負うのは当然であり、返済できなければ倒産は避けられません。
経済の先行きが不安定な今、無担保・無保証で資金調達する重要性が高まっています。
その点、ファクタリングの定義は売掛金の早期資金化であり、債権譲渡です。
融資の定義である「借入れ」とは根本的に異なり、返済義務を負いません。
だからこそ、無担保・無保証で資金を調達できます。
担保・保証の不足によって融資を受けられない会社は、ファクタリングで資金調達しましょう。
もちろん、担保・保証を温存したい会社にもファクタリングが役立ちます。
7.スピーディに資金調達できる
ファクタリングは資金調達スピードに優れています。
ここでは、融資以外の資金調達方法も含め、資金調達スピードの目安を比較してみましょう。
- 民間金融機関のプロパー融資:最短2週間程度。ただしプロパー融資を受けられるのは全企業の1割未満。
- 民間金融機関の保証付融資:1ヶ月程度。銀行の融資審査と信用保証協会の保証審査を受ける必要があり、通常の融資より時間がかかる。
- 日本政策金融公庫の融資:数週間~1ヶ月以上。将来性によって融資するため経営計画書や創業計画書の審査に時間をかける。また、支店数が少ないため対応に時間がかかることも。
- 自治体の制度融資:1ヶ月以上。自治体への申し込み、銀行の融資審査、信用保証協会の保証審査が必要となる。自治体や信用保証協会の対応に時間がかかり、数ヶ月を要することも。
- ノンバンクのビジネスローン:最短即日~1週間程度。ただし即日融資は稀。
- 手形割引:最短数日~1週間程度。券面の郵送に時間を要するため、即日資金調達は不可。
- 出資:出資者の募集状況によって異なり、明確な目安はない。スピーディな資金調達は不可。
- 少人数私募債:引受人の募集状況によって異なる。明確な目安はなく、スピーディな資金調達は不可。
- 2社間ファクタリング:最短即日。多くのファクタリング会社が即日入金を基本としている。
- 3社間ファクタリング: 最短1週間程度。債権譲渡通知書・債権譲渡承諾書の郵送に数日を要するため、即日対応は不可。
- オンラインファクタリング:最短数時間。オンライン完結によりスピーディに調達できる。
融資には色々な形がありますが、定義的に金銭の消費貸借ですから、審査に時間を要します。
ビジネスローンや手形割引はそれなりにスピーディですが、ファクタリングほどのスピードは期待できません。
出資の定義について、出資法では「株式などの取得によって財産を提供する取引のうち、元本の返済義務がないもの」としています。
定義的に元本の返済義務がある融資にくらべて、出資はリスキーな取引です。
だからこそ、融資以上に時間がかかります。
少人数私募債の定義は「少人数私募により発行する社債」です。
縁故者などの少人数を対象に、公募ではなく私募により社債を発行します。
私募債とはいえ、社債発行には一定の手続きが必要となるため、スピーディな資金調達には不向きです。
以上のように比較すると、ファクタリングがいかにスピーディかがよくわかるでしょう。
ファクタリングは、定義的に純粋な債権譲渡であるからこそ、最短数時間~即日といった対応が可能なのです。
8.回収不能リスクを回避できる
買取ファクタリングは、原則的にノンリコースです。
ノンリコースとは、償還請求権がないことを意味します。
このため、ファクタリングした売掛金が回収不能になった場合にも、利用会社に買戻しを請求することはできません。
回収不能による損失は全てファクタリング会社が負うこととなります。
つまり、ファクタリングで売掛金を手放しておくことによって、回収不能リスクを回避できるのです。
もちろん、保証ファクタリングにも同じ効果があります。
保証ファクタリングは、回収不能に陥った売掛金の代金を保証するサービスです。
買取型・保証型のどちらも、リスクマネジメントに役立ちます。
9.財務と融資環境の維持に役立つ
ファクタリングは、財務と融資環境の維持も効果的です。
このメリットについても、定義から考えてみましょう。
融資の定義と自己資本比率
基本的に、融資は財務に悪影響をもたらします。
これは、融資の定義が「借入れ」であり、借入金は返済義務を伴う「他人資本」となるためです。
これに対し、資本金や利益剰余金などの返済義務がない資金を「自己資本」といいます。
さらに、他人資本と自己資本の合計を「総資本」、総資本に占める自己資本の割合を「自己資本比率」といいます。
融資で資金を調達する場合、他人資本が増加する一方で自己資本は変わらないため、自己資本比率の低下は避けられません。
自己資本比率は重要な財務指標のひとつであり、銀行融資でも重視します。
つまり、融資は財務の悪化、延いては融資環境の悪化につながるのです。
ファクタリングの定義と自己資本比率
これに対し、ファクタリングは定義的に債権譲渡であり、借入れではありません。
したがって、ファクタリングで資金を調達しても他人資本が増えることはなく、結果的に自己資本比率の低下を防げます。
つまり、ファクタリングは財務と融資環境の維持に役立つのです。
ビジネスローンも定義的に借入れだが…
特に、ビジネスローンとファクタリングの違いは顕著です。
ビジネスローンは、定義的には借入れであっても、銀行の評価は大きく悪化します。
高金利であり返済負担が大きいこと、また「何らかの理由によって銀行融資を受けられず、ビジネスローンで調達した」という事実を、銀行は重く捉えます。
実際に、ビジネスローンから借り入れたことによって、銀行融資を受けられなくなるケースは珍しくありません。
定義は同じでも、ビジネスローンは他の融資に比べて、融資環境への悪影響が深刻なのです。
この点、ファクタリングは銀行自身も取り扱っており、「売掛金の早期資金化」「債権譲渡」という定義も銀行の評価に影響しません。
銀行融資を受けられない場合、ビジネスローンとファクタリングで迷う人も多いでしょう。
しかし、両者の定義と影響を比較すれば、ファクタリングを優先すべきことは間違いありません。
10.個人事業主にも利用しやすい
ファクタリングは、個人事業主にも利用しやすい方法です。
少なくとも、融資に比べて資金調達のハードルはかなり低いといえます。
これも、やはりファクタリングと融資の定義の違いによるものです。
融資は定義的に元本の返済義務を負うため、融資先となる個人事業主の信用と返済力によって判断します。
個人事業主は法人に比べて事業規模が小さく、業績・財務は脆弱です。
また、事業の資金繰りと個人的な資金繰り(家計)が一体になっていることが多く、資金繰りの安定性・健全性を見極めにくいことも問題です。
例えば、事業用の資金として融資したものを、個人の生活費や借金返済に流用されるかもしれません。
融資審査では資金使途を重視するため、この点が不透明な個人事業主は審査に通りにくいのです。
その点、ファクタリングの定義は売掛金の早期資金化であり、この定義は融資対象によって変わるものではありません。
個人事業主も、信用取引を行っていれば売掛金を所有しており、それをファクタリングすることで簡単に資金を調達できます。
手続きも法人のファクタリングと変わらず、定義に基づき「申し込み→審査→債権譲渡(契約)→入金⇒早期資金化の完了」という流れです。
近年、個人事業主専業のファクタリングが増えており、好条件で利用できるサービスも多いです。
個人事業主の資金調達にもファクタリングを活用しましょう。
11.資金調達方法の多様化に効果的
資金調達方法によって定義が異なるからこそ、状況に応じて最適な資金調達方法を選択し、資金繰りの効率を高めることも可能です。
「売掛金の早期資金化」「債権譲渡」を定義とするファクタリングは、会社の状況や規模、業種、業歴、事業者区分を問わず、簡単に取り入れることができます。
つまり、資金調達方法の多様化に効果的ということです。
ファクタリングと他の資金調達方法の定義と違いを知り、うまく組み合わせることによって資金繰り・資金調達の最適化を図りましょう。
ここでは、最も理想的な「銀行融資+ファクタリング」の組み合わせを紹介します。
融資の定義と活用
融資とファクタリングの定義を比較すれば、両者はまさに水と油。
組み合わせるイメージがつかないかもしれませんが、定義的に真逆であるからこそ、この組み合わせが効果的なのです。
融資の定義は「借入れ」「金銭消費貸借」であり、融資先の信用・返済力を基準に審査するほか、担保・保証も重視します。
これにより、資金調達のハードルは高くなります。
しかし、定義的に金銭消費貸借であるからこそ、信用・返済力に問題がなければ多額の資金を低コストで調達でき、担保・保証の活用度も高いのです。
これは融資のメリットですから、多額の資金調達が必要な場合や、担保・保証に十分な余裕がある場合には、銀行融資を積極的に活用すべきでしょう。
「銀行融資+ファクタリング」の意義
逆に、多額の資金調達を必要としていない場合や、担保・保証の余力を温存したい場合には、ファクタリングが役立ちます。
ファクタリングの定義は債権譲渡であり、調達可能額と手元の売掛金総額はイコールです。
短期的な資金繰りであれば、ファクタリングだけでも十分に回すことができます。
調達金額に関係なく銀行から融資を受けるよりも、「多額の資金調達は銀行融資」「少額の資金調達はファクタリング」と使い分けることによって、資金繰りにメリハリが生まれます。
ファクタリングで短期資金を機動的かつ柔軟に調達すれば、資金ショートの危険にも効果的です。
政府がファクタリングを推奨する理由
近年、政府がファクタリングを推奨している理由も、融資とファクタリングの定義の違いにあります。
日本の企業は銀行融資への依存度が高く、政府はその改善に取り組んできました。
銀行融資とファクタリングの定義の違いをうまく嚙合わせることで、銀行融資への依存を緩和できるため、政府はファクタリングを推奨しているのです。
ファクタリングの定義によるデメリット
ファクタリングにはデメリットもあります。
使い方によっては資金繰りが悪化する危険もあるため注意が必要です。
ファクタリングの主なデメリットは以下の4つです。
1.調達できるとは限らない
ファクタリングは、定義の異なる他の資金調達方法に比べて、資金調達のハードルが低いといえます。
しかし、必ず調達できるわけではありません。
ファクタリングにも審査がある
ファクタリングは定義的に「債権譲渡」であり、利用会社は譲渡人、ファクタリング会社は譲受人となります。
ファクタリング会社は、この債権譲渡取引のリスクを測る必要があるため、必ず審査を行います。
当然ながら、売掛金・売掛先に何らかの問題があれば、債権譲渡を拒否するのです(=審査落ち)。
この場合、別の売掛先の売掛金で再度申し込むか、同じ売掛金を別のファクタリング会社に申し込む必要があります。
ファクタリング会社ごとに審査難易度が異なる
また、ファクタリング会社によって方針が異なり、審査難易度にも差があります。
ファクタリング会社の系列でいえば、審査難易度が高い順に並べると「銀行系>ノンバンク系>独立系」です。
したがって、確実に資金調達したい場合には、独立系ファクタリングを利用することとなります。
ただし、同じ独立系でも大手ほど審査が厳しい傾向があります。
大手のファクタリング会社では、手数料が安い代わりに審査が厳しく、2社間ファクタリングでも「最短2営業日」「初回取引は最短2~5営業日」といったケースがしばしばです。
大手・中小に関係なく、ファクタリングであれば定義は同じ(債権譲渡)ですが、審査難易度は一様ではありません。
初回利用時は要注意
特に注意したいのは、初回利用時の審査です。
初めてファクタリングを利用する場合、どのファクタリング会社に申し込んでも必ず「初回利用」となります。
ファクタリングの定義は売掛金の早期資金化であるため、審査では売掛金・売掛先を重視し、利用会社はさほど重視しません。
ただし、初回利用時は利用会社も審査対象と考えてください。
なぜならば、売掛金の買い取りには「利用会社による詐欺のリスク」が伴うからです。
実際に、利用会社がファクタリング会社に対して詐欺行為を働き、摘発されたケースが多々あります。
主な詐欺行為は以下の4つです。
- 架空債権詐欺…実在しない売掛金をファクタリングする行為
- 二重譲渡…すでに譲渡した売掛金を、複数の相手に譲渡(ファクタリング)する行為
- 計画倒産詐欺…利用会社と売掛先が共謀し、ファクタリング後に売掛先を計画的に倒産させる行為
- 使い込み(横領)…2社間ファクタリングの際、支払期日に売掛先が入金した代金を利用会社が使い込み、ファクタリング会社に決済しないこと
これらの詐欺を避けるには、利用歴が少ないうち(特に初回利用時)は利用会社にも審査を行い、申込内容の健全性や合理性を測る必要があります。
だからこそ、ファクタリングの必要書類として利用会社に関する書類(決算書など)を求められるのです。
利用会社に悪意がなく、売掛金・売掛先に問題がなかったとしても、申込内容によっては不健全・非合理と判断され、審査に落ちることがあります。
2.手数料がかかる
既に書いた通り、ファクタリングには手数料がかかります。
ファクタリングの定義は「売掛金の早期資金化・債権譲渡」ですから、この手数料は「早期資金化・債権譲渡に伴う手数料」と考えてください。
具体的には、売掛金を買い取るための事務手数料、債権譲渡登記費用、ファクタリング会社に訪問を依頼する場合の出張費用などが請求されます。
ファクタリングの調達コストは他の資金調達方法に比べて高く、資金繰りが悪化する危険もあります。
これが、ファクタリングの最大のデメリットです。
手数料は、ファクタリング方式や売掛先の信用力によって変動します。
方式別の手数料相場は以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
- 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
額面100万円の売掛金をファクタリングする場合、2社間ファクタリングならば10~30万円、3社間ファクタリングならば1~10万円の手数料を支払います。
利益率が低い業種では、特に注意が必要です。
ファクタリング手数料によって利益がほとんどなくなってしまう、あるいは赤字になってしまう可能性があり、ファクタリングを繰り返すにつれて資金繰りが悪化していきます。
したがって、ファクタリングを利用する際には、手数料が安いファクタリング会社を選びましょう。
優良ファクタリング会社は、上記の相場よりも安い手数料で利用できることが多いです。
No.1も、以下の手数料でご利用いただけます。
- 2社間ファクタリング:額面金額の5~15%(オンラインファクタリングは2~8%)
- 3社間ファクタリング:額面金額の1~5%
3.売掛先の信用を損なうリスクがある
ファクタリングの利用を売掛先に知られると、信用を損なうリスクがあります。
まだまだファクタリングは一般的な資金調達方法ではなく、ファクタリングの定義を正しく認識していない人も多いです。
ファクタリングを定義通りに捉えず、「資金繰りに行き詰まった会社がやむを得ず利用するもの」「法律に違反する資金調達方法」などと捉える人も少なくありません。
これもファクタリング特有のデメリットといえるでしょう。
売掛先が関与しない2社間ファクタリングであれば、このリスクはほとんどありません。
ただし、2社間ファクタリングには債権譲渡登記がつきものです。
債権譲渡登記とは、ファクタリングによって債権者が「自社→ファクタリング会社」に変化したことを、登記所で公示する仕組みです。
2社間ファクタリングを利用する場合、ほとんどのファクタリング会社が債権譲渡登記を求めます。
登記した内容は公示され、誰でも閲覧可能となります。
これは、売掛先でも閲覧できるということです。
可能性としては低いですが、登記内容を売掛先や関係者が確認し、ファクタリングの利用を知られることがあります。
2社間ファクタリングだからといって、売掛先に知られるリスクがゼロではないのです。
もっとも、債権譲渡登記を留保できるファクタリング会社に依頼すれば、このリスクを避けることができます。
No.1でも、債権譲渡登記の留保に対応しています。
4.ファクタリング会社選びが難しい
最後に、ファクタリング会社の数が非常に多いため、会社選びが難しいことがデメリットです。
近年、ファクタリング会社の数は増加の一途をたどっています。
これは、ファクタリングの参入障壁がほとんどないためです。
定義によれば、ファクタリングは債権譲渡の一種であり、貸金業とは定義が異なります。
貸金業は、貸金業法や出資法による規制が厳しく、参入のハードルは極めて高いといえます。
しかしファクタリングは、貸金業のような厳しい規制がなく、法整備も追い付いていない状況です。
現時点では、「ファクタリング=債権譲渡」という定義に基づく規制があるのみで、債権譲渡取引の中でも特にファクタリングを対象とする規制はほとんどありません。
だからこそ、大手業者や中小業者の新規参入が相次いでおり、中には悪質業者も紛れ込んでいる状況です。
ファクタリング会社ごとに、得意な業種、手数料や利用金額の設定、必要書類、オンライン対応の可否など、様々な違いがあります。
このため、自社に適しているファクタリング会社を見極め、好条件で利用することが重要です。
しかし、ファクタリング会社は非常に多く、それぞれの条件を見比べるだけでも大変です。
また、各社がホームページに記載しているファクタリング条件は絶対ではありません。
実際に利用してみなければわからず、利用したところ「思っていた条件と全く違う」という失敗も珍しくありません。
自社に最適なファクタリング会社を選ぶことは、現実的にかなり困難といえます。
ファクタリング業者には悪質業者も存在するため、独自に選んだ結果、悪質業者を利用してしまう危険もあります。
会社選びで失敗しないためにも、ファクタリングをご利用の際にはぜひNo.1にご相談ください。
No.1は、中小ファクタリング会社のなかでも業歴が長く、優良業者として高い評価を得ています。
手数料は相場よりも安く設定しており、コンサルティングによる最適なファクタリングプランのご提案も可能です。
まとめ:資金繰りの問題はファクタリングで解決
ファクタリングは、ここ数年で急速に広がってきた資金調達方法です。
歴史が浅く、立場によって定義も異なりますが、基本的には「売掛金の譲渡による早期資金化」と考えておけば問題ありません。
政府もファクタリングを推奨しているため、長期的に普及率が高まり、ファクタリング環境の整備も進んでいくと考えられます。
資金繰りに問題を抱えている会社は、ファクタリングの活用をおすすめします。
ファクタリングを初めてご利用の方は、No.1へお気軽にお問い合わせください。
弊社のコンサルタントが、ファクタリングの活用をサポートいたします。
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。
よく見られているファクタリング記事