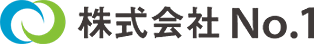カテゴリー: ファクタリング
ファクタリングの会計処理!仕訳方法・勘定科目・消費税はどうなる?
ファクタリングを利用するケースですが、会計処理についても確認しておかなければなりません。
ファクタリングを利用する時には会計処理上、売掛債権(売掛金)が減ることになります。
その時にどのように処理するのでしょうか?
またファクタリングを利用すると、予定していた金額よりも少ない金額しか入金されてこないことになります。
減ってしまった分はどのように会計処理していけばよいのでしょうか?
こちらではファクタリング利用時の会計処理について徹底解説します。
これからはじめてファクタリングを利用しようと思っている方は必見です。
- ファクタリングとは?
- ファクタリング方式と会計処理
- ファクタリング利用時の会計処理:仕訳のタイミングは3回
- 契約日と入金日が同じ:即日ファクタリングの会計処理
- ファクタリング手数料を「割引料」で仕訳けても良いのか?
- 会計ソフトに「売上債権売却損」の勘定科目がない場合は?
- 2社間ファクタリングの利用と会計処理の流れ
- オンラインファクタリングの利用と会計処理の流れ
- 3社間ファクタリングの利用と会計処理の流れ
- ファクタリングの税務処理:消費税・法人税・所得税の解説
- ファクタリングのオフバランス化
- 売掛債権(売掛金)担保融資を利用した時の仕訳とは?
- 会計処理にみる資金繰り改善効果
- まとめ:ファクタリングの会計処理でお悩みの方はNo.1にお任せください
ファクタリングとは?
世界的にみると、ファクタリングは古い歴史をもつ資金調達方法です。
しかし、日本でファクタリングが普及してきたのはごく最近のこと。
銀行融資などに比べると、ファクタリングはまだまだマイナーであり、正しい知識もさほど浸透していません。
ファクタリングの会計処理を理解するためにも、まずはファクタリングの基本について解説します。
売掛金で資金調達
簡単にいうと、ファクタリングは売掛金の売却による資金調達です。
自社が所有している売掛金(ただし請求内容が確定しており、支払期日前であること)をファクタリング会社に譲渡し、その対価を受け取ります。
売掛金は信用取引によって発生する売掛債権であり、支払期日を待たなければ現金にはなりません。
これが資金繰りの負担になり、黒字倒産を引き起こすことも。
ファクタリングは、支払期日前の売掛金を売却するため、売掛金を早期に回収でき、資金繰りの負担を軽減できます。
詳しくは後述しますが、会計処理もいたって簡単です。
利便性や資金調達スピードにも優れ、近年急速に普及が進んでいます。
以上のように、ファクタリングは売掛金の早期資金化という認識が一般的です。
金融庁も、ファクタリングを以下のように定義しています。
一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。
ファクタリングの法的側面
初めてファクタリングを利用する際、色々と気になることがあるでしょう。
会計処理が分からない、コスト負担が気になる、さらには安全性に不安があるなどなど。
近年、ファクタリングは加速度的に普及が進んでいます。
それに伴い、問題視されているのが悪質業者です。
ファクタリングが急速に普及していくのに対し、法整備が追い付かない状況です。
例えば、ファクタリング業の新規開業にあたっては登録や免許などが必要なく、手数料率の上限規制もありません。
誰でも開業でき、サービス内容に関する規制も少ないとなれば、悪質業者には好都合です。
したがって、現在のファクタリング業界に悪質業者が紛れ込んでいます。
実際に、悪質業者が摘発されて話題になることもしばしばです。
これにより、ファクタリングにネガティブなイメージを抱く人が少なくありません。
ファクタリングを違法・危険と考えるならば、もはや会計処理以前の問題です。
しかしながら、ファクタリングは完全に合法的な仕組みです。
ファクタリングの法的根拠は、金融庁の定義にある「ファクタリングは法的に債権譲渡」という点にあります。
民法第466条をみてみましょう。
(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
出典:出典:e-Gov法令検索「第四節 債権の譲渡」
民法第466条は、債権譲渡を明らかに認めています。
譲渡禁止特約の売掛金でさえ、法的には譲渡が認められているのです。
ファクタリングは債権譲渡の一種ですから、同様に合法といえます。
ファクタリングで注意すべきは、「ファクタリングを装って違法行為をはらたく悪質業者」であって、ファクタリングそのものは合法・安全です。
正規のファクタリングを利用している限り、合法的に、安全に資金を調達できます。
会計処理も債権譲渡を中心に考える
ファクタリングが売掛金の早期資金化であること、法的に債権譲渡であることを知れば、ファクタリングの会計処理も見えてきます。
ファクタリングを利用した際の会計処理は、他の債権譲渡取引の会計処理と基本的に同じです。
例えば、手形の譲渡と会計処理。
手形取引によって生じる受取手形も、売掛債権に含まれます。
受取手形は、裏書譲渡や手形割引などによって資金繰りに活用でき、これらは債権譲渡取引です。
日本では手形取引が根強く、手形の譲渡と会計処理は広く知られています。
ファクタリングも手形割引も債権譲渡取引であり、会計処理の考え方も大差ありません。
ファクタリング方式と会計処理
ファクタリングとその他の債権譲渡では、会計処理が異なる場合があります。
例えば、手形割引は譲渡人である自社と、譲受人である調達先(銀行や手形割引業者など)の2社間で取引し、会計処理の流れとタイミングは一定です。
しかし、ファクタリングにはいくつかの方式があり、会計処理にもいくらか影響してきます。
ファクタリング方式を大きく分けると、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングです。
そして最近では、オンラインを活用したオンラインファクタリングも徐々に普及しています。
それぞれの方式を簡単にまとめると以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:ファクタリングの利用会社(以下、利用会社)とファクタリング会社の2社間で取引する方式
- オンラインファクタリング:2社間ファクタリングの取引を全てオンラインで行う方式
- 3社間ファクタリング:利用会社、ファクタリング会社、売掛先の3社間で取引する方式
方式の違いは、売掛先の関与とオンライン対応にあります。
どの方式も、会計処理はいたって簡単です。
会計処理の流れが大きく変わることもありません。
しかし、方式ごとの特徴により、会計処理のタイミングが異なります。
詳しい会計処理は後述するとして、ここでは方式別の特徴と、会計処理への影響を簡単にみていきましょう。
2社間ファクタリングの特徴と会計処理
2社間ファクタリングは、売掛先が一切関与しない方式です。
申し込みから契約・入金まで、売掛先が関与することはありません。
利用会社とファクタリング会社だけで取引することから、簡単な手続きでスピーディに資金を調達できるのが特徴です。
実際に、2社間ファクタリングの多くは即日対応に力を入れています。
この場合、契約後に即座に入金されるため、「譲渡時の会計処理」と「入金時の会計処理」をまとめて行います。
ただし、100%即日中に調達できるとは限りません。
2社間ファクタリングの中にも、「最短翌営業日に入金」「初回利用は最短〇営業日で入金」といったケースがあります。
その場合、契約と入金のタイミングがずれることから、譲渡(契約)時と入金時にそれぞれ会計処理を行う必要があります。
このほか、2社間ファクタリングは他の方式に比べて、手数料が割高です。
後述の通り、ファクタリングの会計処理では売掛債権の譲渡損失を計上しなければなりません。
2社間ファクタリングで高い手数料を支払えば、会計処理で計上する損失は膨らみ、資金繰りが悪化することも。
手数料の負担を逐一確認する意味でも、ファクタリングの会計処理を適切に行うべきです。
オンラインファクタリングの特徴と会計処理
オンラインファクタリングは、2社間取引を全てオンラインで行います。
手続きの一部だけではなく、全てをオンラインで完結するのが特徴です。
オンラインの活用により、通常の2社間ファクタリング以上に利便性と資金調達スピードに優れています。
通常の2社間ファクタリングは最短即日対応が基本ですが、オンラインファクタリングは最短数時間で対応できることも多いです。
No.1のオンラインファクタリングでも、最短60分入金の実績が多数ございます。
オンラインで即日中に契約、その後速やかに入金となれば、まとめて会計処理を行います。
オンラインファクタリングは、通常の2社間ファクタリングよりも即日対応を受けやすく、会計処理も簡単といえるでしょう。
さらに、オンラインファクタリングは手数料も安いです。
会計処理で計上する損失は小さく、資金繰りの負担軽減にも役立ちます。
3社間ファクタリングの特徴と会計処理
3社間ファクタリングは、利用会社・ファクタリング会社・売掛先の3社間で取引します。
売掛先が債権譲渡を禁止・制限したり、ファクタリングをネガティブに考えていたりする場合、3社間取引が成立しないため利用できません。
このように、3社間ファクタリングは利用のハードルが高い方式です。
もちろん、売掛先が関与することによって、手続きが煩雑になり、資金調達にやや時間がかかります。
例えば、3社間ファクタリングの際には債権譲渡通知が必須です。
利用会社とファクタリング会社で債権譲渡契約を結んだ後、利用会社から売掛先に債権譲渡通知書を郵送します。
債権譲渡通知の後に入金となるため、契約と入金に数日のズレが生じます。
したがって、会計処理のタイミングも「譲渡時の会計処理」と「入金時の会計処理」に分ける必要があるのです。
なお、ファクタリング方式の中で最も手数料が安いのは3社間ファクタリングです。
3社間ファクタリングの会計処理の際、計上する損失は小さく、資金繰りの負担も軽くなります。
通常の「掛取引」の会計処理:仕訳方法のポイントは?
ファクタリングの会計処理を理解するには、通常の掛取引と比較するのが近道です。
例題として、100万円の売上が掛取引で発生した場合の仕訳方法を見てみましょう。
売掛債権(売掛金)発生時の会計処理
下記は、通常の掛取引で売掛債権(売掛金)が発生した時点の貸借対照表(B/S)です。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛債権(売掛金) | 100万円 | 売上 | 100万円 |
▼ポイント
- 勘定科目は「売掛債権(売掛金)」として仕訳ける
- まだ現金が入金されていなくても、売上が発生したタイミングで計上する
- 入金されてから会計処理を行った帳簿は、納税申告で「差し戻し」される
売掛先から入金時の会計処理
売掛債権(売掛金)100万円が入金された場合は、以下のように仕訳します。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 100万円 | 売掛債権(売掛金) | 100万円 |
ちなみに入金時の勘定科目は現金としましたが、「預金」などでも構いません。
状況に合わせて記載しましょう。
以上が通常の会計処理となります。
問題となってくるのは、ファクタリングを利用した時に会計処理がどのように変化していくのか、という部分です。
変化についてはしっかりと理解して確実に処理しなければなりません。
誤った処理をしてしまうと、決算時の業務が増えてしまいます。
ファクタリング利用時の会計処理:仕訳のタイミングは3回
ここからは、下記の条件でファクタリングを利用した際の会計処理について見ていきましょう。
▼例題の条件
- ファクタリング契約のタイプ:債権譲渡契約(買取型)で資金化
- 売掛債権(売掛金):100万円
- ファクタリング手数料:10%
特筆すべきは、会計処理の回数が増えるという点です。
通常の掛取引では2回の会計処理でしたが、ファクタリンでは3回のタイミングで仕訳なければなりません。
売掛債権(売掛金)発生時の会計処理
売上時に売掛債権(売掛金)が発生した時点の会計処理は、通常の掛取引と全く同じです。
現金が入金されるまで待たずに、売掛債権(売掛金)が発生したタイミングで仕訳けましょう。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛債権(売掛金) | 100万円 | 売上 | 100万円 |
ファクタリング契約時の会計処理
100万円の売掛債権(売掛金)をファクタリング契約した時の仕訳は以下の通りです。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未収金 | 100万円 | 売掛債権(売掛金) | 100万円 |
注目すべきは、勘定科目が売掛債権(売掛金)から「未収金」へ変化する点です。
未収金とは、売掛債権(売掛金)以外の金銭債権に関わる勘定科目を指しています。
「通常の営業取引以外で発生した未入金のもの」と言った方がイメージしやすいかもしれません。
ファクタリング契約を結んでから資金供給を受けるまで、ある程度のタイムラグが生じます。
したがって、実際にファクタリング会社から入金されるまでは、あくまで入金予定として扱う「未収金」で計上しておく必要があるのです。
なお、売掛債権(売掛金)と未収金の違いについては「売掛金と未収金の違いとは?時効とファクタリングへの影響を解説」にて詳しく解説しております。
▼ポイント
- ファクタリング会社と債権譲渡契約を締結したタイミングで仕訳ける
- 勘定科目を売掛債権(売掛金)から「未収金」に振り替える
売掛債権(売掛金)譲渡代の入金時の会計処理
では次に、ファクタリング会社から入金があった時の仕訳を以下に示します。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 90万円 | 未収金 | 100万円 |
| 売上債権売却損 | 10万円 |
まずはファクタリング利用によって発生した未収金を会計処理したうえで、手数料分を差し引かなければなりません。
ファクタリング手数料のマイナス分は「売上債権売却損」として仕訳けます。
その際、必ず「借方勘定科目」と「貸方勘定科目」の合計金額が一致していなければなりません。
今回の例題では、「現金90万円+売上債権売却損10万円」=「譲渡した売掛債権(売掛金)の合計金額100万円」が正しい会計処理となります。
売上からマイナスしなければならないので損益計算書(P/L)にも反映させましょう。
ちなみに、手数料は「売上債権売却損」ではなく「雑損失」として仕訳けることも可能です。
普段から「雑損失」を使っているのであれば、「雑損失」で仕訳けるとよいでしょう。
▼ポイント
- 売掛債権(売掛金)譲渡代の勘定科目は、「現金」または「預金」などで仕訳ける
- ファクタリング手数料の勘定科目は、「売上債権売却損」または「雑損失」で仕訳ける
- 「借方勘定科目」と「貸方勘定科目」の合計金額を一致させる
- 損益計算書(P/L)にも反映させる
契約日と入金日が同じ:即日ファクタリングの会計処理
「今すぐ現金が必要!」という事業主様に注目されている資金調達方法として、2社間ファクタリングが挙げられます。
2社間ファクタリングに特化しているファクタリング会社の中には、「最短即日で売掛債権(売掛金)譲渡代を入金!」と謳っているケースもあるほどです。
ただし、即日ファクタリングの場合は通常であれば発生する契約から入金までのタイムラグがありません。
したがって、通常のファクタリングよりも仕訳のタイミングが減り、特別な問題がない限り2回の会計処理で完了するのです。
売掛債権(売掛金)発生時の会計処理
下記の通り、売掛債権(売掛金)発生時の会計処理は通常のファクタリング契約と同一です。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛債権(売掛金) | 100万円 | 売上 | 100万円 |
ファクタリング契約時と入金時の会計処理
ファクタリング契約と「同時」または「同日」に入金された場合、下記のように「まとめて仕訳」します。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 90万円 | 売掛債権(売掛金) | 100万円 |
| 売上債権売却損 | 10万円 |
通常のファクタリング契約であれば、売掛債権(売掛金)譲渡代がファクタリング会社から入金されるまで一時的に売掛債権(売掛金)を未収金として計上します。
一方、即日ファクタリングの場合は契約から入金までのタイムラグがないため、一連の会計処理で未収金という勘定科目は登場しません。
▼ポイント
- 貸方勘定科目は「未収金」ではなく「売掛債権(売掛金)」になる
- 売掛債権(売掛金)譲渡代の勘定科目は「現金」または「預金」などで仕訳ける
- ファクタリング手数料の勘定科目は、「売上債権売却損」または「雑損失」で仕訳ける
- 「借方勘定科目」と「貸方勘定科目」の合計金額を一致させる
- 損益計算書(P/L)にも反映させる必要がある
ファクタリング手数料を「割引料」で仕訳けても良いのか?
ファクタリング手数料の最も望ましい勘定科目は「売上債権売却損」ですが、「割引料」として仕訳けることも可能です。
なぜなら、手形割引とファクタリングでは「対象の金融商品」が異なるだけで、ほぼ同じ仕組みになっているからです。
▼手形割引とファクタリングの違い
- 手形割引:「手形」を本来の入金予定日より早く資金化する方法
- ファクタリング:「売掛債権(売掛金)」を本来の入金予定日より早く資金化する方法
次に、お客様が手にする金額が満額よりも目減りする仕組みを見てみましょう。
▼ディスカウントの仕組み
- 手形割引:「利息」が「手形割引」として差し引かれる
- ファクタリング:「手数料」が「売上債権売却損」として差し引かれる
つまり、どちらも営業外損失ですから会計上「ファクタリング手数料=割引料」という解釈が認められているのです。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 90万円 | 未収金 | 100万円 |
| 割引料 | 10万円 |
※ファクタリング契約と入金が同時だった場合、貸方勘定科目は「売掛債権(売掛金)」になります。
ただし、「支払利息割引料」に関しては2018年3月30日以降、基本的に会計上の使用が認められていませんので注意が必要です。
詳しくは、企業会計基準委員会の公式Webサイトで公開されている「収益認識に関する会計基準」にてご確認ください。
会計ソフトに「売上債権売却損」の勘定科目がない場合は?
結論から言うと、たとえ会計ソフトの勘定科目に「売上債権売却損」が無かったとしても、ファクタリング手数料の仕訳に支障はありません。
ファクタリングは新しい資金調達方法ですから、特に古い市販の会計ソフトには「売上債権売却損」という勘定科目が存在していないケースが多いようです。
そんな時は、一般的な会計ソフトで使われている下記の勘定科目でファクタリング手数料を仕訳しましょう。
▼ファクタリング手数料の仕訳に使える勘定科目
- 雑損失
- 債券割引料
- 支払手数料
2社間ファクタリングの利用と会計処理の流れ
ファクタリングの会計処理について詳しく解説しました。
さらに理解を深めるためにも、ファクタリングを実際に利用した場合を想定して、会計処理の流れをみていきましょう。
まずは2社間ファクタリングの会計処理をみていきます。
1.売掛金の確定
ファクタリングは売掛金の譲渡取引ですから、手元に売掛金がなければなりません。
ただし、ファクタリングの対象となるのは、支払期日前の確定債権だけです。
すでに支払期日を過ぎた売掛金は不良債権となり、ファクタリングには利用できません。
また、支払期日や支払額など、請求内容が確定していることが前提ですから、請求内容が確定していない(近い将来確定する予定の)将来債権などもファクタリングの対象外です。
売掛金の発生(取引の完了)と売掛金の確定(請求の受理)は必ずしも一致しません。
売掛金が発生したタイミングで会計処理を行ったからといって、請求内容が確定していなければファクタリングは利用できないのです。
このことは、ファクタリング会社の必要書類に請求書が含まれることからもよくわかります。
「売掛金が発生→会計処理→請求内容の確定→2社間ファクタリング」という流れを意識して考えてください。
2.ファクタリング会社の選定
初めてファクタリングを利用する場合、あるいは現在のファクタリング会社に不満がある場合は、ファクタリング会社を選ぶ必要があります。
多くのファクタリング会社の中から、2社間ファクタリングに対応している業者を選びましょう。
ファクタリング会社によっては、2社間ファクタリングに対応していない(3社間ファクタリングのみ対応)こともあります。
ファクタリング会社の選び方によって、会計処理が変わることはありません。
しかし、ファクタリング会社の強みや特徴が異なり、相性の良し悪しは様々です。
悪質業者を避け、好条件で利用するためにも、自社に適したファクタリング会社を選びましょう。
3.ファクタリングの申し込み
ファクタリング会社を選んだら、いよいよ申し込みです。
申し込み方法は業者によって異なりますが、電話・メール・FAXのほか、公式HPのフォームから申し込めることもあります。
利用を急ぐならば、電話で申し込むのがおすすめです。
他の申し込み方法の場合、業者の確認が遅れ、資金調達が遅れることがあります。
電話申し込みならばすぐに受け付けてもらえるほか、条件や会計処理などについて直接尋ねることも可能です。
申し込みにあたり、ファクタリング会社から2社間ファクタリングの流れや必要書類について説明があります。
説明に問題がなければ、申し込みは完了です。
4.書類提出
申し込み時に求められた書類を提出します。
ファクタリングは、他の資金調達方法に比べて必要書類が少ないのが特徴でありメリットです。
求められる書類は業者によって異なり、初回利用・継続利用で変わることもあります。
とはいえ、会計処理が簡単であるのと同じように、必要書類も簡単なものばかりです。
例えば、No.1の2社間ファクタリングをご利用の際には、以下の4点をご提出いただきます。
- 直近3ヶ月の取引入金が確認できる書類(入金通帳・当座通帳・当座照合表)
- 決算書直近2期分(勘定科目明細付で税務申告済みの捺印のあるもの)
- 成因資料(請求書・発注書・納品書など)
- 取引先企業との基本契約書
このように、手元にある書類だけで揃うことも多いです。
スムーズに利用するためにも、以上の4点は事前に揃えておくと良いでしょう。
5.審査の実施
必要書類が揃い次第、ファクタリング会社は審査を実施します。
書類に不備があったり、追加書類を求められたりした場合、全ての書類が揃わなければ審査を開始できません。
当然ながら、契約と入金、そして会計処理のタイミングにも影響するため注意してください。
ファクタリングの審査は、売掛金を基準に行います。
売掛金の内容に問題がなければ、経営に問題がある会社でも審査に通り、資金を調達できるのがメリットです。
連続赤字の会社、債務超過の会社、起業したばかりの会社、リスケ中の会社なども、安心して審査結果を待ちましょう。
6.契約の締結
2社間ファクタリングの審査はスピーディに行うことが多いです。
申し込みから数時間で審査結果が出ることも。
審査が終われば、ファクタリング会社から審査結果の通知を受けます。
審査に通り、条件に異存がなければ契約手続きに進みましょう。
2社間ファクタリングでは、以下の契約を結びます。
- 債権譲渡契約…売掛金の譲渡に関する契約
- 債権譲渡登記代行契約…債権譲渡登記に関する契約
- 売掛金回収委託契約…売掛金の回収に関する契約
債権譲渡契約は、2社間ファクタリングの契約の軸となるものです。
債権譲渡契約を結ぶことで、売掛金の債権者は利用会社からファクタリング会社に変わります。
契約の締結を以て譲渡の完了とみなし、会計処理を行います。
次に、2社間ファクタリングの際には債権譲渡登記を求められることが多いです。
売掛先が関与しないため、ファクタリング会社が第三者対抗要件を備えるには、債権譲渡登記が欠かせません。
債権譲渡登記は、ファクタリング会社から司法書士に依頼して行うことから、債権譲渡登記代行契約を結ぶ必要があります。
そして、売掛金回収委託契約。
これは、支払期日後の売掛金の回収について取り決めるものであり、2社間ファクタリングでは必須の契約です(詳しくは「8.清算」を参照)。
なお、契約に伴い会計処理を行うのは、債権譲渡契約だけです。
債権譲渡登記・売掛金回収に関する契約は、会計処理には影響しません。
7.入金
契約締結後、ファクタリング会社は利用会社に買取代金を支払います。
入金は、契約締結のタイミングと銀行の営業時間によって変化し、会計処理が変わることも。
銀行の振込対応時間内に契約を結べば、当日中に入金となります。
この場合、契約と入金がほぼ同時ですから、会計処理もまとめて行うのが普通です。
しかし、契約完了の時点で銀行の振込対応時間を過ぎていれば、入金は翌営業日の朝一番となります。
金曜日の夕方に契約を結んだ場合、早くても月曜日の朝に入金ですから、数日のズレが生じます。
このように、契約と入金がズレた場合は、契約時の会計処理と入金時の会計処理を分けてください。
8.清算
2社間ファクタリングの会計処理は、契約時と入金時に行います。
しかし、会計処理が終わっても、手続きは残っています。
最後は清算手続きです。
2社間ファクタリングは売掛先が関与せず、売掛先は売掛金を譲渡したこと(債権者が変わったこと)を知りません。
そのため、支払期日になると、売掛先は利用会社に代金を支払います。
この時点で譲渡と会計処理は完了しており、債権者はファクタリング会社です。
つまり、ファクタリング会社が受け取るべき代金を、利用会社が一時的に預かり、ファクタリング会社に振り込まなければなりません。
売掛金の回収委託契約を結ぶのもこのためです。
清算の期日に遅れると、違約金などのペナルティが発生する恐れがあります。
契約に沿ってしっかり清算しましょう。
清算が終われば、2社間ファクタリングの手続きは全て完了です。
オンラインファクタリングの利用と会計処理の流れ
次に、オンラインファクタリングの利用と会計処理の流れをみていきます。
既述の通り、オンラインファクタリングは2社間取引です。
会計処理を含め、基本的な流れは2社間ファクタリングと変わりません。
オンラインの活用に注目しながら、会計処理を行いましょう。
1.売掛金の発生・確定
オンラインファクタリングも、ファクタリングの対象は支払期日前の確定債権です。
取引先と信用取引を行い、取引が完了した時点で1回目の会計処理(売掛金の発生)。
その後、売掛先に請求することで売掛金が確定します。
オンラインファクタリングが利用できるのは、売掛金の確定後です。
2.ファクタリング会社の選定
売掛金の発生後に会計処理、そして請求した後、ファクタリング会社を選定します。
オンラインファクタリングを取り扱っている業者は、さほど多くはありません。
業界全体でみると、2社間ファクタリングを取り扱っている業者は多いものの、オンラインに対応している業者は少数派です。
No.1をはじめとする一部の優良ファクタリング会社のほか、近年、オンライン専業の業者が徐々に増えている状況です。
オンラインファクタリングを利用するには、オンラインファクタリングを取り扱っている業者を選ぶ必要があります。
この時に注意したいのが、オンライン対応の範囲です。
通常の2社間ファクタリングにも、一部をオンラインで対応するものがあります。
しかし、一部に限ってオンラインで対応するだけでは、オンラインファクタリングとはいえません。
オンラインファクタリングは、手続きの全てをオンラインで対応するものです。
これは、利便性や手数料、さらには会計処理まで影響することなので、必ずオンライン完結のファクタリング会社を選んでください。
3.ファクタリングの申し込み
オンラインファクタリング業者を選んだら、ファクタリングを申し込みましょう。
繰り返す通り、オンラインファクタリングは、手続きをオンラインで完結するものです。
したがって、申し込みもオンラインで行います。
公式HPのフォームから申し込むのが一般的です。
No.1のように、2社間ファクタリング・3社間ファクタリング・オンラインファクタリングの全てを取り扱っている業者もあります。
その場合、オンラインファクタリングの専用フォームから申し込んでください。
業者が申し込み内容を確認した後、商談を行います。
オンラインファクタリングは、商談にもオンラインツールを活用することが多いです。
例えば、No.1のオンラインファクタリング(Easy Factor)では、Web会議アプリのZoomを利用しています。
この時、オンラインファクタリングの流れや必要書類の説明、利用に関するヒアリングを受けます。
会計処理その他の疑問点は、申し込みの際に解消しておきましょう。
なお、オンラインファクタリングの中には、申し込み時に登録を求めるケースもあります。
その際、登録に必要な書類や手続きの流れは業者によって異なるため、業者の説明に従って登録してください。
4.書類提出
申し込み後、必要書類を提出します。
オンラインファクタリングの必要書類は、通常の2社間ファクタリングよりも少ない傾向があります。
例えば、No.1のオンラインファクタリングをご利用の際には、以下の3点をご用意ください。
- 直近の決算書
- 請求書
- 通帳のコピー
通常の2社間ファクタリングよりも、書類が少ないことが分かるでしょう。
資金調達の際、利便性を追求する会社は、必要書類がより少ないオンラインファクタリングをおすすめします。
なお、必要書類はオンライン(Webアップロード、メールなど)で提出するのが一般的です。
5.審査の実施
必要書類が揃い次第、審査を実施します。
オンラインファクタリングの審査も、売掛金を基準に行うため、銀行融資を受けられない会社も審査に通りやすいのがメリットです。
また、オンラインファクタリングはAIの活用が進んでおり、とりわけAI審査に注目したいところ。
通常の2社間ファクタリングは、人の手で審査します。
ファクタリング会社のノウハウ・データの蓄積、さらには審査担当者の能力や経験値によって、審査のスピードや結果が変わります。
審査能力の高い業者であれば、スピーディに審査を行い、好条件も期待できるでしょう。
逆に、審査能力が低い業者は、審査に時間がかかるほか、条件が不適切(売掛金の価値に見合わない条件の設定)になることも珍しくありません。
その点、オンラインファクタリングはAIによって機械的に審査します。
提出書類の数値などをもとに定量的な審査を行うため、定性的な要素(審査担当者の能力や感情)に左右されず、過不足ない審査結果が期待できます。
会計処理で計上する損失が過度に膨らむことはなく、資金繰りの負担も軽微です。
6.契約の締結
契約手続きは、オンラインファクタリングの真骨頂といえます。
通常のファクタリングは、対面または郵送で契約します。
契約手続きに手間がかかるため、「契約は当日中、入金は翌日以降」というケースもしばしばです。
その場合、契約時の会計処理と入金時の会計処理に分ける必要があります。
しかし、オンラインファクタリングは全ての手続きをオンラインで完結します。
もちろん、契約もオンラインです。
No.1のオンラインファクタリングならば、弁護士ドットコム株式会社のクラウド契約システム「CLOUDSIGN」を利用します。
オンライン契約のツールは業者によって異なるため、業者指定のツールを利用してください。
この時、債権譲渡契約と売掛金回収委託契約を結びます。
オンラインファクタリングも売掛金の譲渡取引のため、軸となるのは債権譲渡契約です。
オンラインファクタリングはスピード対応が最大の強みですから、契約後に即入金(会計処理もまとめて)ということが多いです。
売掛金回収委託契約は、オンラインファクタリングでも必須と考えてください。
通常の2社間ファクタリングと異なるのは、債権譲渡登記に関する契約がないこと。
オンラインファクタリングは、債権譲渡登記不要のサービスが主流です。
債権譲渡登記が不要であれば、その代行契約も必要なく、会計処理にも何ら影響しません。
7.入金
オンラインで契約を締結した後、ファクタリング会社は利用会社に買取代金を入金します。
銀行が振込対応時間内に契約を完了すれば、当日中に入金を受けられるでしょう。
この場合、契約と入金を同じ日に行うため、会計処理はまとめて行います。
オンラインでスピーディに対応するだけに、オンラインファクタリングは「譲渡による会計処理」と「入金による会計処理」を一度で行うことも多いです。
例えば、No.1のオンラインファクタリングは最短60分入金のスピード対応に定評があります。
申し込みから入金までが最短60分ですから、特に問題がなければ契約と入金が同日(会計処理もまとめて)になることでしょう。
ただし、一部のオンラインファクタリングには、「審査・契約は最短当日、入金は翌営業日」を基本とするサービスもあります。
その場合、契約と入金のタイミングがずれるため、会計処理も分けなければなりません。
会計処理の負担を減らすには、No.1のようにスピード対応のオンラインファクタリングがおすすめです。
8.清算
基本の流れと会計処理は「7.入金」を以て完了します。
とはいえ、オンラインファクタリングも2社間取引である以上、清算を行わなければなりません。
売掛金の譲渡を知らない売掛先は、支払期日になると利用会社に代金を支払います。
利用会社は、受け取った代金を速やかにファクタリング会社に入金してください。
オンラインファクタリングも、売掛金の回収の流れは「売掛先→利用会社→ファクタリング会社」です。
オンラインファクタリングの契約は、クラウド上に保存されています。
契約内容をしっかりと確認し、契約に沿って清算を行いましょう。
清算後、オンラインファクタリングの手続きは完了となります。
3社間ファクタリングの利用と会計処理の流れ
最後に、3社間ファクタリングの会計処理の流れを解説します。
3社間ファクタリングは、売掛先が関与する方式です。
売掛先が関与することで手続きがやや煩雑となり、契約と入金にもずれが生じます。
これが会計処理にも影響します。
1.売掛金の発生・確定
3社間ファクタリングも債権譲渡取引ですから、手元に売掛金があることが大前提です。
支払期日前の確定債権が対象であることは変わりません。
売掛先と信用取引を行い、商品・役務の提供が完了した時点で売掛金が発生(一度目の会計処理)。
その後、契約に基づき請求することで売掛金が確定します。
2.売掛先の内諾
2社間ファクタリングとは異なり、3社間ファクタリングは売掛金が確定しただけでは利用できません。
3社間ファクタリングには、売掛先の同意が必須です。
売掛先がファクタリングを拒否すれば、3社間取引は成立しません。
法的には、売掛先が譲渡を禁止・制限した場合でも、債権譲渡は有効です。
しかしながら、法的に有効であることと、売掛先がファクタリングを認めることは別問題です。
実際に、売掛先がファクタリングに否定的であれば、回収時のトラブルは避けられないでしょう。
そのようなリスクはファクタリング会社としても避けたいところ。
3社間ファクタリングの手続きは、売掛先の協力があって初めて成立します。
ファクタリング会社の中には、申し込み段階で売掛先の内諾を求めることも多いです。
3社間ファクタリングを利用するならば、まずは売掛先に3社間ファクタリングの利用を申し入れ、手続きへの協力を取り付けてください。
3.ファクタリング会社の選定
手元に支払期日前の確定債権があり、なおかつ売掛先の内諾を得られた会社は、ファクタリング会社を選定します。
選択肢は、3社間ファクタリングを取り扱っている業者だけです。
ファクタリング会社の系列には、銀行系・ノンバンク系・独立系の三つがあります。
銀行系は3社間ファクタリングに特化しており、2社間ファクタリングを取り扱っていないことも多いです。
ノンバンク系は3社間ファクタリングに強く、一部は2社間ファクタリングに対応。
独立系は2社間ファクタリングに強く、一部が3社間ファクタリングに対応しています。
いずれの系列も3社間ファクタリングを利用できますが、銀行系・ノンバンク系は審査難易度や資金調達スピードに問題があることも。
最も無難なのは、独立系の3社間ファクタリングでしょう。
独立系で3社間ファクタリングを取り扱っているのは、No.1などの優良業者に限られます。
優良業者は柔軟審査・スピード対応に強く、会計処理のサポートを受けられることも多いです。
独立系を中心に、自社に適切な3社間ファクタリングを選んでください。
4.ファクタリングの申し込み
ファクタリング会社が決まったら、3社間ファクタリングに申し込みます。
申し込み方法は、電話やメール、Webフォームなど。
独立系の3社間ファクタリングは、申し込みの流れを明確にしているのが普通ですが、銀行系・ノンバンク系の3社間ファクタリングは問い合わせるまで不明ということが多いです。
まずは業者の指定する方法で申し込んでください。
申し込み後、手続きや必要書類、条件に関する説明を受け、正式に申し込み完了となります。
5.書類提出
申し込み後、業者指定の必要書類を提出します。
独立系の必要書類は、2社間ファクタリングも3社間ファクタリングも基本的に同じです。
決算書・請求書・入金確認書類などの基本書類を揃えておくと良いでしょう。
銀行系・ノンバンク系は必要書類もブラックボックスです。
独立系とは必要書類が異なり、書類の作成・取得に思いがけず手間がかかることも有り得ます。
もっとも、3社間ファクタリングはスピード対応を前提としておらず、ある程度時間をかけて手続きするものです。
必要書類の準備にある程度の手間をかけても、資金調達にはさほど影響しないはずです。
6.審査の実施
必要書類の提出後、ファクタリング会社が審査を実施します。
3社間ファクタリングは、審査時にファクタリング会社から売掛先に直接連絡し、請求内容その他を照会することも多いです。
売掛先の内諾を得ていなければ、売掛先とファクタリング会社のやり取りがスムーズにいかず、審査に時間がかかることもあり得ます。
もっとも、3社間ファクタリングは売掛先の内諾が前提ですから、審査・照会時にトラブルになることは少ないです。
むしろ、確かな情報をもとに正確な審査を行い、適正な手数料を設定できるのはメリットといえます。
7.契約の締結
審査結果に問題がなければ、利用会社とファクタリング会社の間で債権譲渡契約を結びます。
3社間ファクタリングの契約はシンプルです。
債権譲渡契約は必須ですが、債権譲渡登記や売掛金回収に関する契約は不要です。
まず、3社間ファクタリングは債権譲渡登記が必要ありません。
というのも、「8.債権譲渡通知・承諾」があるためです。
あえて債権譲渡登記をせずとも、「売掛先に対する債権譲渡の通知」または「売掛先による債権譲渡の承諾」によって、ファクタリング会社は第三者対抗要件を具備できます。
したがって、債権譲渡登記代行契約は不要です。
また後述の通り、3社間ファクタリングの売掛金は「売掛先→ファクタリング会社」の流れで回収します。
利用会社は回収に関与せず、売掛金回収委託契約も不要となります。
契約を結んだ時点(債権譲渡契約を結んだ時点)で会計処理を行ってください。
8.債権譲渡通知・承諾
3社間ファクタリングは、契約と入金のタイミングに数日のズレがあります。
債権譲渡契約を結んで会計処理を行った後、債権譲渡通知・承諾手続きを必ず行うためです。
基本的には、利用会社から売掛先に対して債権譲渡通知を行います。
一部、利用会社とファクタリング会社の連名で債権譲渡通知を行うケースもあるようです。
いずれの場合も、債権譲渡通知書を内容証明郵便で送付します。
売掛先が遠方であれば、債権譲渡通知に二日以上を要することもあるでしょう。
債権譲渡通知が完了するのは、早くても契約完了から数日後。
譲渡承諾書に署名・返送を求めるならば、さらに数日を要するはずです。
9.入金
債権譲渡通知・承諾手続きの完了後、ファクタリング会社は利用会社に買取代金を入金します。
申し込みから入金まで、早ければ一週間程度のイメージです。
手続きの流れからも分かる通り、3社間ファクタリングは契約と入金が同日に行われることはありません。
必ず数日のズレが生じるため、会計処理は「譲渡時の会計処理」と「入金時の会計処理」に分けてください。
10.清算
3社間ファクタリングの利用・会計処理の流れは、「9.入金」で完了です。
「8.債権譲渡通知・承諾」で、売掛先は売掛金の譲渡に承諾しています。
これは、単にファクタリングの利用・売掛金の譲渡だけではなく、売掛金の譲渡によって支払先が変わることも含めて承諾します。
支払期日になれば、売掛先はファクタリング会社に直接支払うため、利用会社が売掛金の回収に関与することはありません。
ただし、売掛金が回収不能になった場合、必要に応じて回収実務への関与・協力を求められます。
それを除けば、3社間ファクタリングの手続きは「9.入金」を以て完了と考えて構いません。
ファクタリングの税務処理:消費税・法人税・所得税の解説
資金調達の手段としてファクタリングを検討しているなら、あらかじめ税務処理についても把握しておきましょう。
ここからは、下記の3点について解説します
- ファクタリングに消費税はかかるのか?
- ファクタリングは法人税や所得税の課税対象なのか?
- ファクタリングは節税に役立つのか?
ファクタリングは消費税の対象外
通常の掛取引の場合、帳簿に計上した売掛債権(売掛金)そのものが消費税の対象となります。
一方、ファクタリングで得た売掛債権(売掛金)譲渡代および手数料は、2社間であろうと3社間であろうと消費税の対象にはなりません。
なぜなら、売掛債権(売掛金)譲渡の対価が、「非課税取引」に含まれている「有価証券等の譲渡」に該当するからです。
株式取引で得た利益に消費税がかからないのと同じ意味合い、と言った方がイメージしやすいかもしれません。
ちなみに、印紙代は消費税の対象外ですが、司法書士報酬は消費税の対象ですから、登記の代行を依頼する時は注意が必要です。
ファクタリングは法人税・所得税の対象
ファクタリング会社から入金された売掛債権(売掛金)譲渡代は、あくまで「売上」です。
したがって、「法人税」や「所得税」の対象となります。
▼対象となる税金
- 株式会社:法人税
- 個人事業主様:所得税、個人事業税
ただし、ファクタリング手数料は売上債権売却損として計上する経費ですから、損金算入が可能です。
ファクタリングは節税にも役立つ
ファクタリングも通常の掛取引も法人税がかかるのは同じですが、支払うタイミングに違いがあります。
▼法人税を支払うタイミングの違い
- 通常の掛取引:入金前でも法人税の支払い義務がある
- ファクタリング:入金前に法人税を支払う必要がない
ここで注目したいのが、売上債権売却損として会計処理できるファクタリング手数料の存在です。
赤字決算によって節税するには、その年の損益が利益を上回っていなければなりません。
つまり、ファクタリングには「法人税を支払うタイミングを先送りできる」、「節税目的の赤字決済に役立つ」という2つのメリットがあるのです。
ファクタリングのオフバランス化
オフバランス化とは、合法の範囲内で企業の会計状態が「健全であるように見せる」方法です。
具体的には、帳簿に計上される資産・負債を賃借対照表(B/S)から除く、または勘定科目を置き換えることで可能となります。
▼賃借対照表(B/S)の状態
- 銀行融資:入金を待っている間は「売掛債権(売掛金)」、融資後は「負債」として計上
- ファクタリング:入金を待っている間は「未収金」、入金後は「現金」として計上
銀行融資では負債として扱う勘定科目が増えますが、現金として資金化できるファクタリングでは負債である売掛債権(売掛金)が消えます。
つまり、ファクタリングによって総資産額が減少する反面、帳簿上から「負債」が取り除かれる分、ROA(総資産利益率)と自己資金比率の向上に繋がるのです。
売掛債権(売掛金)担保融資を利用した時の仕訳とは?
ファクタリングと同様に、売掛債権(売掛金)を利用した資金調達方法として「売掛債権(売掛金)担保融資」があります。
ファクタリングを検討している方は、売掛債権(売掛金)担保融資も検討しているケースが多いようです。
ここからは、売掛債権(売掛金)担保融資を利用した場合の会計処理について解説します。
売掛債権(売掛金)担保融資の借入れ実行時の仕訳例
例題として、売掛債権(売掛金)担保融資で100万円の借入れを受けたケースを見てみましょう。
借入れ実行時には以下のような仕訳となります。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 100万円 | 借入金 | 100万円 |
売掛債権(売掛金)担保融資は「借入れ」であり、売掛債権(売掛金)を売却するファクタリングとは本質的に異なります。
よって、ファクタリングのように売掛債権(売掛金)を減少させるような会計処理は行いません。
あくまで「負債」が発生するのです。
返済時の仕訳例
借入金の返済を行った場合には以下のように仕訳します。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 借入金 | 100万円 | 現金 | 100万円 |
上記の通り、借入金と現金を減らすような会計処理を行うのです。
利息の仕訳例
売掛債権(売掛金)担保融資では利息が発生しますので、忘れずに計上しなければなりません。
仮に利息が50万円かかった場合には以下のように仕訳します。
| 借方勘定科目 | 金額 | 貸方勘定科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払利息 | 50万円 | 現金 | 50万円 |
会計処理にみる資金繰り改善効果
ファクタリングの会計処理を理解すれば、ファクタリングのメリット・デメリットがわかります。
中でも注目したいのが、ファクタリングの資金繰り改善効果です。
会計処理の視点から、ファクタリングの効果と注意点をみていきましょう。
ファクタリングが資金繰り改善につながる
ファクタリングのメリットとして広く知られているのが、資金繰りの改善です。
会計処理を考えると、このメリットが一層はっきりします。
売掛金の負担
資金繰りが悪化する原因は色々ありますが、売掛金の負担によって悪化するケースが少なくありません。
ご存じの通り、売掛金は信用取引によって発生します。
売掛金の発生時に会計処理を行いますが、実際には支払期日を待たなければお金は入ってきません。
つまり、売掛先が支払うべき代金を、一時的に自社が立て替えている状態です。
売掛金は立替金であり、この立替負担が資金繰りを圧迫します。
手元の売掛金が増加することは、立替負担が大きくなることにほかなりません。
逆に、手元の売掛金が減少すれば、立替負担は軽くなります。
したがって、売掛金の増加は資金繰り悪化に、売掛金の減少は資金繰り改善につながるというのが、資金繰りの大原則です。
会計処理で売掛金が減少
信用取引を行っている以上、売掛金は必ず発生します。
多かれ少なかれ、売掛金が資金繰りの負担になるのです。
信用取引の比率が高い会社や、回収サイトが長い会社ほど資金繰りが悪化しやすいです。
売掛金の負担によって資金繰りが悪化した際、資金繰りを改善するには、売掛金を減らすことで容易に資金繰りを改善できます。
ファクタリングは債権譲渡取引であり、手元の売掛金をファクタリング会社に譲渡することで資金を調達します。
利用会社からファクタリング会社に売掛金を譲渡した際、その旨の会計処理を行い、売掛金の勘定科目は未収金に変化。
その後、ファクタリング会社から買取代金の受け取った際には、現金・預金として会計処理を行います。
この会計処理から、手元の売掛金が未収金に、さらに現金へと変化する様子が分かるでしょう。
つまり、ファクタリングによって手元の売掛金が減少するのです。
手元の売掛金が減少すれば、資金繰りが改善するのが原則です。
単に会計処理上のことではなく、現実的に資金繰りが改善します。
売掛金の負担、資金繰り悪化に悩んでいるならば、ファクタリングで改善するのがおすすめです。
手数料負担に要注意
ただし、手数料の負担には注意してください。
手数料が高ければ、ファクタリングの資金繰り改善効果はなくなってしまいます。
場合によっては、資金繰り悪化の原因になりかねません。
ファクタリング手数料の相場
ファクタリングの手数料は、額面金額から差し引く形で、入金時に一括で支払います。
入金されたものは現金や預金として、手数料は売掛債権売却損として会計処理を行います。
会計処理の際、手数料が高ければ売掛債権売却損が増大。
これは、売掛金が目減りすることを意味します。
手数料を甘く考えると、利益がなくなるだけではなく、赤字になることもあるでしょう。
赤字の部分は手元資金から補填しなければなりません。
手元資金の流出は資金繰り悪化を招きます。
無計画にファクタリングし、しばしば高い手数料を支払った結果、資金繰りが悪化する会社もあるのです。
資金繰りの悪化を避けるには、少なくとも手数料を相場の範囲内に抑えることが重要です。
ファクタリングの手数料は、方式によって異なります。
方式別の手数料率の相場は以下の通りです。
- 2社間ファクタリング:額面金額の10~30%
- 3社間ファクタリング:額面金額の1~10%
- オンラインファクタリング:額面金額の10%以下
現在、ファクタリングの手数料に関する上限規制はありません。
業者が自由に設定でき、グレーゾーンが大きいです。
よほど高くなければ違法にならず、相場を超える手数料を請求されることもあり得ます。
額面金額の30%以上もの手数料を支払い、会計処理を行えば、利益の確保は困難です。
利益率を超える部分は赤字となり、資金繰りの悪化は避けられません。
優良ファクタリング会社を選ぼう
ファクタリングで資金繰りを改善するには、手数料を抑える必要があります。
そのために、最も簡単・確実なのは優良ファクタリング会社を選ぶことです。
優良ファクタリング会社は、その他の業者に比べて手数料を安く設定しています。
相場よりも安くなることが多いため、資金繰り悪化を防ぐだけではなく、改善に効果的です。
例えば、No.1のファクタリングは、以下の条件でご利用いただけます。
- 2社間ファクタリング:額面金額の5~15%
- 3社間ファクタリング:額面金額の1~5%
- オンラインファクタリング:額面金額の2~8%
相場と比較して、おおむね半分以下の手数料でファクタリングでき、資金繰り改善に役立ちます。
また、No.1をはじめ、優良ファクタリング会社はコンサルティングを手掛けていることも多いです。
うまく活用すれば、資金繰り改善に最適なファクタリングプランの提案を受けたり、会計処理のフォローを受けたり、様々なメリットが期待できます。
つまり、売掛債権(売掛金)担保融資の仕訳は通常の借入れ処理と同じなのです。
まとめ:ファクタリングの会計処理でお悩みの方はNo.1にお任せください
ファクタリングに興味があっても、「会計処理が難しそう…」と利用を見合わせている事業主様も多いでしょう。
そんな時は、ファクタリング会社の担当者に遠慮なく相談してみて下さい。
優良なファクタリング会社であれば、快く相談に乗ってくれるはずです。
その際、迷惑そうな態度をとったり誤魔化したりするようであれば、資金調達のパートナーとして相応しいとは言えません。
No.1は長年にわたり、ファクタリング業とコンサルティング業に携わってきました。
資金調達・資金繰りの専門家が多数在籍しています。
ファクタリングの会計処理でお悩みの方は、No.1までお気軽にご相談ください。
経験豊富なスタッフがヒアリングを行い、お客様ごとに適切な会計処理をご案内します。
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。
よく見られているファクタリング記事