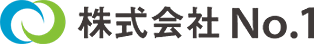カテゴリー: 経営情報
社内預金制度の企業にとってのメリットとは?
企業の資金調達法としてあまり有名ではありませんが、「社内預金制度」と呼ばれるものがあります。
簡単に言ってしまえば、企業が労働者の委託を受けて企業内で貯蓄金を管理することを社内預金制度、と呼んでいるわけです。
珍しいタイプの資金調達法ですが、借り入れの審査で落ちてしまった経験がある企業としては資金繰りを改善させる有効な方法にもなります。
その内容については理解しておくべきです。
こちらでは社内預金制度の基本的な事柄と、企業としてのメリットについてお伝えします。
社内預金制度の基本
社内預金制度とは、従業員の給与の一部を会社が預かり、管理を代行する制度です。
普通、預金するのは銀行であって、会社ではありません。
しかし、社内預金制度を導入することによって、従業員は会社に預金できるようになります。
まずは、社内預金制度の基本を簡単にみていきましょう。
社内預金制度とは?
社内預金制度は福利厚生を目的としています。
従業員からお金を預かる際、預金金利は市場金利よりも高く設定するのが一般的です。
これにより、従業員の資産形成を支援し、福利厚生につながります。
もちろん、社内預金制度があるからといって、預金は強制ではありません。
会社にお金を預けるかどうかは従業員の自由です。
社内預金制度の大目的は福利厚生にあり、これは従業員側のメリットです。
しかしながら、後述の通り、社内預金制度は会社側にもメリットがあります。
例えば、社内預金制度は資金調達に役立つのです。
資金調達方法を多様化ならば、社内預金制度が役立ちます。
社内預金制度の普及度
社内預金制度は、会社・従業員の双方に双方にメリットがあり、古くから確立されている制度です。
ところが、社内預金制度はあまり普及していません。
実際に社内預金制度を導入している会社は少ないです。
2020年の調査(独立行政法人労働政策研究・研修機構「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」)によれば、社内預金制度を導入している会社は7.9%に過ぎません。
従業員側も社内預金制度にはあまり関心がないようで、「特に必要性が高い福利厚生」として社内預金制度を挙げた従業員は、全体の5.2%という結果になりました。
それだけに、社内預金制度を導入することで、他社(社内預金制度を導入していない会社)にはない強みになるでしょう。
社内預金制度の導入に一定のハードル
社内預金制度の普及率が低いのは、導入に一定のハードルがあるためです。
社内預金制度を導入するには、以下の要件をクリアしなければなりません。
- 社内預金制度の導入について労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ること
- 社内預金の管理に関する規程を作成し、労働基準監督署へ届け出ること
- 社内預金の金利が下限利率(年0.5%)以上に設定されており、月ごとに利息を支払うこと
- 毎年3月31日現在の社内預金の金額について、保全措置を講じること(金融機関と保証契約を結ぶ、信託会社と信託契約を結ぶ、預金保全委員会を設置するなど)
- 年に一度、社内預金の管理状況を労働基準監督署に報告すること
- 従業員の返還請求(社内預金の引き出し)を受けた際には、速やかに応じること
社内預金制度で預かったお金は、会社の資金繰りにも活用できますが、あくまでも従業員のものです。
したがって、社内預金制度を導入した会社は、責任をもって管理しなければなりません。
自社で管理するか、もしくは信託機関に管理してもらいます。
社内預金制度の導入要件も、全て社内預金の管理に関するものです。
実際の管理に当たっては、自社と従業員だけではなく、労働基準監督署や預金保全委員会といった第三者も関与します。
社内預金制度の運用に問題がある場合、労働基準法違反となり罰則が課せられることも。
社内預金制度をしっかりと運用していくには、相応の負担が伴います。
ただでさえ労働力が不足している昨今、社内預金制度に無関心な会社が多いのも無理はありません。
社内預金制度のメリット
どんなメリットがあるから社内預金制度を企業は利用するのでしょうか?
ここからは、社内預金制度の代表的なメリットを解説します。
預金を自由に利用できる
社内預金制度の大きなメリットのひとつは、資金使途を制限されないことです。
調達と使途
企業の資金調達の中には、使途が限定されているものも少なくありません。
特定の運転資金にしか利用できなかったり、設備投資資金としてしか利用できなかったりすることも珍しいわけではありません。
特に顕著なのが融資です。
例えば銀行から融資を受ける際には、資金使途の説明を必ず求められます。
なぜ融資が必要なのか、調達した資金についてどのような利用を考えているかを伝えるわけです。
資金使途を説明できなかったり、説明できても銀行の理解を得られなかったりすれば、融資審査に落ちると考えてください。
資金使途に違反すると?
資金使途がネガティブな場合、審査に落ちるのでは…と考えて、嘘の資金使途を伝える会社もあります。
しかし、これは資金使途違反にあたるため絶対にNGです。
資金使途に限らず、決算書の粉飾などもそうですが、銀行はとにかく嘘を嫌います。
そもそも銀行は、本業からの利益だけを返済原資とみなし、返済できない相手には融資しません。
貸し付けたお金が事業に活用され、利益を生み出し、そこから回収できると見込んで融資するわけです。
もし、伝えた内容と全く異なるような利用をしてしまえば、銀行の回収見込みは根本から崩れます。
それ以前に、嘘をつくような相手にお金は貸したくない、貸した後に嘘と分かればすぐに返してほしいと考えるのは、誰でも同じです。
回収不能リスクがそれほど悪化していなくても、銀行は回収に乗り出すでしょう。
資金使途違反の際、全額一括返済を請求できることは、金銭消費貸借契約に明記されています。
いわゆる「期限の利益喪失」というもので、契約にある以上、拒否することは不可能です。
融資での調達が困難に
さらに、全額一括返済すれば終わりというわけではなく、銀行との関係悪化は避けられません。
資金使途違反によって信用を損なった場合、再びその銀行から融資を受けることは極めて困難です。
前回嘘をついた相手が、今回は嘘をつかないという保証はどこにもなく、むしろ「今回も嘘をつくかもしれない」と考えるのが自然です。
他行からの信用も悪化するかもしれません。
例えば、資金使途に違反したために、メインバンクから支援を打ち切られた場合。
数ある銀行の中で、最も親身に支援すべきメインバンクが手を引くには、相当の理由があるはずです。
サブバンクもそこを疑います。
表面的には問題がなくとも、疑いの目を以て審査するのですから、それだけでハードルは高くなります。
一度の資金使途違反をきっかけに、資金調達が極端に困難になるケースも珍しくありません。
社内預金制度は使途が自由
様々な制約がある企業の資金調達ですが、社内預金制度に関しては使途が限定されることがありません。
社内預金制度で調達した資金は、設備投資資金として利用してもOKですし、事業の運転資金としての活用もOKです。
何も金融機関の審査を受けて資金調達をしているわけではないので、利用方法に口を出されることもありません。
複数の利用目的があるようなケースにおいては、社内預金制度がおすすめ、というケースもあるわけです。
資金繰りの安定につながる
資金繰りを安定させるには、手元資金を厚くすることが重要です。
したがって、「特に理由はないけれども、資金を確保しておきたい」という会社もあるでしょう。
しかしながら、資金使途がないのですから、銀行融資では調達できません。
その点、社内預金制度は資金使途を問いませんから、ただ資金を確保したい会社にも役立ちます。
社内預金制度を導入しておけば、社内預金としてプールされた資金がそのまま「調達余力」となり、実質的には手元資金と同じ効果をもたらします。
使途に制限がない社内預金制度は、自由に使えるだけではなく、資金繰りの安定にも効果的です。
金利が低い
社内預金制度は、銀行やノンバンクに比べて金利が低いため、調達コストを抑えることができます。
融資の調達コスト
銀行融資は調達コストが安い資金調達方法として有名ですが、それでも金利の目安は年2~3%。
信用保証協会の保証付きで融資を受けるならば、保証料も支払わなければなりません。
銀行融資で資金を調達できない会社が、次善策として考えるのがビジネスローンです。
ビジネスローンを利用した場合にはどれだけの金利が発生するでしょうか?
借入額や業者によっても異なってきますが、年利で10.0%から15.0%になることもあるのです。
特に、ノンバンクのビジネスローンは金利が高いことで有名です。
それだけの金利を支払い続ける、ということは簡単なことではありませんよね。
社内預金制度の調達コスト
しかし社内預金制度で支払わなければならない金利に関しては、かなり低く設定できるのです。
ただし下限金利が設定されているので注意してくださいね。
社内預金制度の下限金利は0.5%となっています。
厚生労働省令と呼ばれるもので決定しており、どの企業も社内預金制度を利用する場合には年0.5%の金利が設定されることに。
通常の預金(従業員個人が銀行の預金口座に預ける場合)の金利を考えると0.5%でも高いですよね。
しかし資金調達をする側として考えると、0.5%の金利というのはかなり有利であることは間違いありません。
調達コストの比較
実際のところ、社内預金制度の調達コストはどの程度なのでしょうか。
銀行融資・ビジネスローン・社内預金制度で資金調達した場合の調達コストを、簡単に比較してみましょう。
【銀行融資】
資金繰りの要ともいえる銀行融資。
低金利・低コストで調達できる方法として有名です。
ここでは、信用保証協会の保証付融資で1000万円した場合の調達コストを考えてみましょう。
金利は年2.5%、保証料率は借入総額に対して1.5%、1年後に一括返済の短期借入とします。
この場合、まず融資実行時に信用保証協会に保証料15万円を支払い、1年後の返済期日に利息25万円を支払います。
諸経費を考えなければ、銀行融資の調達コストは40万円です。
【ビジネスローン】
次に、高金利で有名なビジネスローンをみていきます。
ビジネスローンの上限金利は融資総額によって変わり、100万円以上では年15%が上限です。
ノンバンクのビジネスローンで1000万円を調達し、借入条件を年利15%・1年返済とする場合、調達コストは単純計算で150万円にもなります。
【社内預金制度】
最後に社内預金制度をみていきましょう。
上記で挙げた社内預金制度の「年0.5%」という金利は、あくまでも下限であって、それ以上に設定することも可能です。
とはいえ、資金調達を見据えて社内預金制度を導入するならば、年0.5%に近い水準に設定したいところ。
仮に年0.5%とすれば、社内預金制度で1000万円を調達した場合のコストは、わずかに5万円です。
実際には、社内預金制度の運用に様々なコスト(管理コスト、信託コストなど)がかかります。
しかし、諸経費を織り込んだとしても、社内預金制度が銀行融資よりも高くなることは考えにくいです。
ましてや、社内預金制度がビジネスローンより高くなることはあり得ません。
超優良企業ならば、銀行から年1%台で調達できることもありますから、社内預金制度と良い勝負になるでしょう。
そのような特殊な場合を除いて、銀行融資・ビジネスローン・社内預金制度の三者のうち、調達コストが最も安いのは社内預金制度です。
審査を受ける必要がない
社内預金制度は、他の資金調達方法のように審査がありません。
無審査で調達できるため、融資審査にいつも苦労している会社や、すでに融資審査に落ちてしまった会社でも安心して調達できます。
資金調達に審査はつきもの
ビジネスローンや銀行融資、さらにはファクタリングや売掛金担保融資などなど様々な企業の資金調達のほとんどは審査が行われています。
融資をはじめとする外部資金調達はもちろんのこと、内部資金調達にも審査はつきものです。
ファクタリングは売掛金を審査し、手形割引は受取手形を審査し、リースバックも対象資産を審査します。
回収不能リスクや資産価値などを把握し、対応の可否や条件(手数料、買取り金額など)を決めるためです。
審査落ちになってしまえば、借り入れ調達ができない、ということになってしまうわけです。
無審査の危険性
無審査で調達したいと考える人もいるでしょうが、無審査には危険が潜んでいます。
大抵の資金調達方法において、無審査は成り立ちません。
分かりやすいのが融資です。
無審査で融資するということは、貸倒れリスクが一切わからない状態で融資することを意味します。
当然ながら、返済力がない相手に融資してしまう危険があります。
そもそも、銀行や貸金業者が融資先を厳しく審査するのは、貸倒れリスクを避けるためです。
無審査で融資できるはずがないのです。
もし、無審査で融資する業者があるならば、それは無審査で融資して、なおかつ貸倒れリスクを回避できるカラクリがあると考えるべきでしょう。
無審査を謳う業者として、最も分かりやすいのがヤミ金。
法外な利息の請求、支払えない場合の違法な取り立てなどによって、無審査で融資できるというわけです。
資金調達が自社の中だけで完結しない限り、(違法業者を除いて)無審査での調達はあり得ません。
金融庁の公式HPでも、違法な金融業者への注意喚起として、「無審査」を謳う業者は避けるべきとしています。
社内預金制度は無審査
もっとも、無審査で安全に調達できる方法がないわけではありません。
社内預金制度もその一つです。
「審査が必須」「無審査は危険」というのは、自社と他社の間で調達するためです。
資金を提供する他社の立場を考えると、無審査では成り立たないのは当然でしょう。
逆に、資金調達に他社が関与せず、自社だけで完結すれば審査は必要ないわけです。
社内預金制度は、外部から借り入れるわけではなく、金融機関などの審査を受けることはありません。
資産を売却するわけでもなく、買取業者の審査も不要です。
社内預金制度の運用には、保全や管理に他社(銀行や信託会社、労働基準監督署など)が関与するため、社内預金制度自体は自社だけで完結しません。
しかし、「社内預金制度を活用した資金調達」ということで考えると、むしろ審査がある方がおかしいでしょう。
社内預金の管理も、社内預金による資金調達も、全ては社内預金制度の中で行われます。
社内預金制度の運用者として、自社で自社を審査することとなり、全く無意味です。
だからこそ、社内預金制度は無審査で調達できるのです。
融資審査に落ちた会社も安心
社内預金制度は無審査のため、会社の状況に関係なく調達できます。
深刻な経営悪化により、融資審査に落ちてしまった会社も安心です。
融資ならばそうはいきません。
銀行Aで審査に落ちた会社は、銀行Bでも調達できない可能性が高いです。
銀行は、融資先を格付けしています。
銀行格付けは、金融庁の「金融検査マニュアル」の債務者区分を基本としているため、格付けの基準が銀行によって極端に変わることはありません。
債務者区分のうち、スムーズに借りられるのは「正常先」のみで、「要注意先」以下になると融資を受けられなくなります。
銀行Aで債務者区分が「要管理先」となれば、他の銀行でもやはり「要管理先」となり、銀行格付けに関係なく「融資不可」となるのです。
貸金業者は独自の格付けを行っていません。
とはいえ、ビジネスローンを利用する会社の多くは、すでに銀行融資に落ちています。
つまり、債務者区分・格付けに問題があることを前提に審査するのです。
大きな問題を抱えている会社は、銀行の融資審査に落ち、ビジネスローンの審査にも落ち、どこからも借りられないケースもよくあります。
審査のおかげで計画的な資金調達ができなくなることも珍しいわけではありません。
しかし社内預金制度は無審査です。
無審査である以上、審査落ちということもありません。
銀行の融資審査に落ちた会社も、その上さらにビジネスローンの審査に落ちた会社でも、社内預金制度は確実に調達できます。
労働者に対する福利厚生になるケースも
ここまで、社内預金制度の資金調達メリットを中心にお話してきました。
しかし、冒頭でも述べた通り、社内預金制度の本来の目的は福利厚生です。
調達する側にとって、社内預金制度の下限金利(0.5%)は低いといいましたが、預金する側としてはどうでしょうか?
ここ数年で、銀行の預金金利は上昇傾向にあります。
一部の銀行では、年0.5%前後の預金プランも出てきました。
今後、預金金利の上昇が続けば、社内預金制度の金利引き上げも必要になってくるでしょう。
年0.5%では従業員が納得せず、「会社より銀行に預けよう」ということにもなりかねません。
とはいえ、三菱UFJ銀行の普通預金は年0.2%ですから、年0.5%の金利はまだまだ高い水準です。
同じお金を預けるなら、金利が高いに越したことはありません。
要は社内預金制度が社員に対する福利厚生にもなるわけです。
社員のモチベーションを上げることにもなるでしょう。
人材の流出を防ぐことにもなるかもしれません。
実際に福利厚生を全面に押し出して社内預金制度を利用している企業もあるのです。
まとめ:資金調達方法の多様化が重要
この記事では、社内預金制度の基礎知識とメリットについて解説しました。
社内預金制度は、従業員と会社の双方にメリットがあります。
特に会社にとっては、社内預金制度で資金調達が可能となり、資金繰りの安定にも効果的です。
資金繰りには資金調達が欠かせず、必要資金を確実に調達するには様々な資金調達方法を確保しておくことが大切です。
資金調達方法の多様化のために、社内預金制度を検討してみると良いでしょう。
近年、新たな資金調達方法として人気なのが売掛金の早期資金化です。
No.1でも、売掛金の買い取りを行っています。
資金調達にお困りの方は、No.1までお気軽にお問い合わせください。
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。
よく見られているファクタリング記事