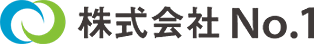カテゴリー: 助成金・社内制度
2025年、活用すべきキャリアアップ助成金とは?各コースの概要・メリット・注意点
いま、企業にとって優秀な人材を確保する必要性が高まっています。
一方で、契約社員やアルバイト、派遣社員などの非正規雇用の従業員の待遇改善も求められています。
しかしながら中小企業にとって、財務の状況が厳しい中で従業員の雇用環境の改善や、正規雇用の推進に取り組むことは難しいのではないでしょうか。
このような中小企業の経営者や、そこで働く人の待遇改善を図るための助成金が「キャリアアップ助成金」なのです。
この記事では、キャリアアップ助成金の最新情報(令和7年度版)や活用のポイントについて詳しく解説します。
キャリアアップ助成金とは?
キャリアアップ助成金は、厚生労働省が実施している助成金のひとつです。
ここ数年で、助成金の方向性は大きく変わってきました。
政府の雇用政策が変化したことで、助成金も「雇用の維持・創出」から「労働環境の整備」「生産性向上」などにシフトしているのです。
この傾向が顕著に表れているのが、キャリアアップ助成金。
例えば、キャリアアップ助成金のひとつに「正社員化コース」があります。
この制度を利用することにより、採用時点では自社の戦力になるかどうかわからない候補者を契約社員やアルバイトとして採用し育成をして、確かに自社の戦力として活躍してくれそうだということになれば正社員として採用して助成金をもらうことが可能になるのです。
どのような企業が受給対象になるのか?
キャリアアップ助成金を受給するためには、まず雇用保険に加入している事業主であることが求められます。
そして、キャリアアップ助成金を受けるにあたり
・取り組みの責任者として「キャリアアップ管理者」を任命すること
・自社の「キャリアアップ計画」を作成して、所轄の労働局長の認定を受けること
・「キャリアアップ計画」で定めた期間内に従業員のキャリアアップに取り組むこと
・対象となる従業員の賃金の支払い状況等がわかるよう賃金台帳や出勤簿を整備していること
などが求められます。
つまり普通に従業員を雇用している企業であれば労働局長の認定を受けた上で「キャリアアップ管理者」の任命や「キャリアアップ計画」の作成・実施を行えば受給できる比較的ハードルが低い助成金ともいえるでしょう。
キャリアアップ助成金の概要
一口にキャリアアップ助成金といっても、キャリアアップ助成金は複数のコースによって構成されています。
キャリアアップ助成金のうち、最も有名なのは正社員化支援のための「正社員コース」です。
このほか、処遇改善支援として、キャリアアップ助成金には「賃金規定等改定コース」「賃金規定等共通化コース」「賞与・退職金制度導入コース」「社会保険適用時処遇改善コース」の4つが設けられています。
キャリアアップ助成金に限らず、助成金制度は年々変化するものです。
キャリアアップ助成金も、受給のための要件、受給金額などが変わるため、最新情報を常にチェックする必要があります。
コース自体も変化するため、その時々で自社に最適なコースを活用してください。
キャリアアップ助成金の正社員化コース
ここからは、キャリアアップ助成金のそれぞれのコースについて、制度の概要を紹介します。
まずは、キャリアアップ助成金の目玉ともいえる正社員化コースです。
キャリアアップ助成金の正社員化コースとは?
キャリアアップ助成金の正社員化コースは、企業に従業員の正社員化を促し、雇用条件の改善を目指すものです。
これまで正社員化に取り組んでこなかった会社は、正社員化のための就労規則または労働協約などを整備する必要があります。
キャリアアップ助成金の正社員化コースは、就労規則・労働協約(その他これに準ずるもの)に規定した制度に基づき、有期雇用労働者・無期雇用労働者を正社員化することで受給できる助成金です。
正社員化コースのメリット
キャリアアップ助成金のうち、最も人気が高い正社員化コース。
なぜ人気かといえば、活用しやすいこと、そしてメリットが大きいことです。
正社員化コースのメリットは、人材確保に役立つことです。
有期雇用労働者は、定められた期間を満了すれば、契約を更新しない限り解雇となります。
無期雇用労働者には定められた雇用期間がないものの、正規雇用などに適用される労働条件が適用されず、どうしても離職率は高くなるものです。
当然、雇用期間は短くなる傾向があり、専門性や生産性は期待できません。
これらの労働者は正社員化してこそ、長期にわたって雇用でき、教育や経験を積んだ優秀な戦力にもなります。
とはいえ、正社員化にはコストがかかるため、人件費の問題から有期・無期雇用を続けざるを得ない会社も少なくありません。
そのような会社は、キャリアアップ助成金の正社員化コースを活用し、助成金を受給しながら取り組むことで、正社員化が容易となります。
正社員化コースの支給額
キャリアアップ助成金の正社員化コースの支給額は、重点支援対象者かどうか、正社員化以前の雇用形態(有期雇用か無期雇用か)、企業規模(中小企業か大企業か)によって変わります。
具体的な支給額は以下の通りです。
- 中小企業が重点支援対象者を正社員化する場合、有期雇用は80万円(40万円×2期)、無期雇用は40万円(20万円×2期)
- 大企業が重点支援対象者を正社員化する場合、有期雇用は60万円(30万円×2期)、無期雇用は30万円(15万円×2期)
- 中小企業が重点支援対象者以外を正社員化する場合、有期雇用は40万円(40万円×1期)、無期雇用は20万円(20万円×1期)
- 大企業が重点支援対象者以外を正社員化する場合、有期雇用は30万円(30万円×1期)、無期雇用は15万円(15万円×1期)
コースに限らず、キャリアアップ助成金は拡充傾向にあります。
正社員化コースも、数年前の支給額は有期雇用57万円、無期雇用28.5万円でした。
中小企業がキャリアアップ助成金の正社員化コースを利用し、重点支援対象の有期雇用労働者を正社員化すれば、80万円もの助成金を受給できます。
詳しくは後述しますが、令和7年からは重点支援対象者かどうかによって支給額が大きく変わるため、この点が活用のポイントになってくるでしょう。
令和7年の変更ポイント
今年、キャリアアップ助成金の正社員化コースは、いくつかの点が変更となっています。
重点支援対象者とは
まず、支給額の区分です。
支給額の区分のうち、「重点支援対象者」の概念は、今年から導入されたものです。
これにより、支給額が大きく変わってくるため、よく理解しておく必要があります。
重点支援対象者は以下の3パターンです。
- 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
- 雇入れから3年未満であり、「過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下」かつ「過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない」有期雇用労働者のうち
- 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
なお、雇入れから3年以上の有期雇用労働者であっても、雇用期間が通算5年を超える場合には無期雇用労働者とみなされるため注意が必要です。
支給額の加算要件・加算額
キャリアアップ助成金には、コースによって支給額の加算を受けられる場合があります。
正社員化コースも、一定の要件を満たすことで加算を受けられるため、ぜひとも狙っていきたいところ。
加算の要件と金額も、年々変化するため注意が必要です。
令和7年度の加算要件と加算額は以下の通りです。
- 正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合、中小企業は20万円、大企業は15万円の加算
- 多様な正社員制度(勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれか一つ以上)を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合、中小企業は40万円、大企業は30万円の加算
去年の正社員化コースは、上記に加えて「派遣労働者を正社員化」「母子家庭の母または父子家庭の父を正社員化」「人材開発支援助成金の特定の訓練修了者を正社員化」が加算要件となっていました。
令和7年度は、これらが「重点支援対象者」という枠組みに変わったため、加算額ではなく根本的な支給額に関わってきます。
この変更も、キャリアアップ助成金の正社員化コースを活用する上では重要になってくるでしょう。
正社員化コースの注意点
キャリアアップ助成金の正社員化コースを活用する上での注意点をみていきましょう。
申請期間
数年前まで、キャリアアップ助成金の正社員化コースは1回でまとめて支給されていました。
有期雇用労働者を正社員化した場合、57万円を数期にわけるのではなく、1回で受け取っていたのです。
令和7年の正社員化コースは、重点支援対象者の正社員化に限り、2期に分けて支給されます。
例えば、中小企業が重点支援対象の有期雇用労働者を正社員化する場合、40万円を2期に分けて支給します。
このとき、申請期間に注意してください。
大まかにいえば、正社員化後、正社員として6ヶ月雇用した時点で1期目を支給、その後さらに正社員として6ヶ月雇用した時点で2期目を支給する流れです。
もちろん、この期間中に事業主の都合で雇用保険被保険者を解雇したり、正社員化を取りやめたりした場合には助成金は支給できません。
キャリアアップ助成金の正社員化コースを活用するには、1期目の受給で気を抜かず、満額受給することが重要です。
支給申請の上限
注意点は、支給申請に上限があることです。
キャリアアップ助成金の正社員化コースを1年間のうちに申請できるのは、1事業所あたり20人が上限となっています。
正社員化の条件に関係なく20人が上限ですから、対象者が多い会社はよく考えなければなりません。
例えば、中小企業がキャリアアップ助成金の正社員化コースを利用する場合、重点支援対象者以外の無期雇用労働者を20人とすれば、支給額の合計は600万円です。
一方、重点支援対象者の有期雇用労働者20人を正社員化すれば、支給額は1600万円になります。
どの労働者を正社員化するかによって、支給額が大きく変わってくるのです。
キャリアアップ助成金の正社員化コースを利用する際には、20人という上限の中で、できるだけ受給額を増やすように工夫してください。
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コース
次に、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースをみていきましょう。
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースとは
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、有期雇用労働者と無期雇用労働者の基本給の賃金規定を3%以上増額改定し、適用した場合に受給できる助成金です。
就業規則や労働協約には、賃金の定めがあります。
この部分を改定し、その内容が対象労働者の過去3ヶ月の賃金支給実態と比較して3%以上増額していれば、助成対象となります。
賃金規定等改定コースは、正社員化コースとともにキャリアアップ助成金を中心となってきました。
その他のコースが年々変化している中、正社員化や賃金規定に関するキャリアアップ助成金は、常に変わらず実施されています。
今後も引き続き実施され、拡充も十分に考えられるでしょう。
賃金規定等改定コースのメリット
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースのメリットは、年々高まっています。
というのも、最低賃金の引き上げが毎年続いているためです。
全国平均の最低賃金(加重平均)は、令和元年には時給901円でしたが、令和5年には1004円まで上昇。
令和6年、51円もの大幅な引き上げにより、2025年8月現在、最低賃金は時給1055円となっています。
一部では、今年度の最低賃金は過去最大となる63円前後の引上げが予想されています。
その場合、最低賃金は1100円を突破することに。
予想が外れたとしても、今後長期にわたって引き上げが続くことは間違いないでしょう。
コロナ禍でさえ、賃金の引上げは続いたのです。
このような急激な引き上げにより、人件費の増大に苦しむ会社が増えています。
政府の賃金引上げに対応するためにも、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースを活用すべきです。
資金繰りが苦しい会社も、最低賃金の引き上げに対応しなければなりません。
最低賃金以下で働かせた場合、最低賃金法により罰則が科せられます。
必ず引き上げなければならないものですから、何もせずにただ引き上げるのではなく、引き上げると同時にキャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースを利用し、負担軽減を図りましょう。
賃金規定等改定コースの支給額
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、賃金の引き上げ率と、企業規模によって支給額が変わります。
引き上げ率ごとの支給額は以下の通りです。
- 中小企業…3%以上4%未満は4万円、4%以上5%未満は5万円、5%以上6%未満は6.5万円、6%以上は7万円
- 大企業…3%以上4%未満は2.6万円、4%以上5%未満は3.3万円、5%以上6%未満は4.3万円、6%以上は4.6万円
引き上げ率3%以上といえば、現実には困難のように感じるかもしれません。
しかし、近年の傾向から考えると、決して無理な引き上げではないでしょう。
例えば、2024年から2025年にかけて、全国平均の最低賃金は1004円から1055円へと引き上げられました。
引き上げ率にすると約5.1%です。
政府の方針に合わせて賃金規定を改定し、時給を1004円から1055円にアップした会社は、賃金規定等改定コースの「5%以上6%未満6.5万円」の対象となります。
対象労働者が10人であれば、65万円もの助成金を受給できるのです。
キャリアアップ助成金のうち、賃金規定等改定コースは利用しすいものの一つといえるでしょう。
令和7年の変更ポイント
令和7年、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースもいくつかの点で変更されています。
それらをまとめてみていきましょう。
支給額
まず、賃金規定等改定コースの支給額です。
数年前と比較して、令和7年の賃金規定等改定コースは支給の仕組みが大きく変わっています。
数年前まで、キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースの支給額は、引き上げ率と対象労働者数によって変化していました。
例えば、引き上げ率2%の場合、対象労働者が1~3人の場合には1事業所当たり9万5000円、11~100人の場合には1人当たり2万8500円といった塩梅です。
この場合、対象労働者が増えるにつれて、1人当たりの支給額が減る傾向がありました。
ところが、令和7年の支給額は、対象労働者数ではなく引き上げ率で決まります。
対象労働者数が増えても、1人当たりの支給額が減ることはありません。
賃金を大幅に引き上げ、なおかつ対象労働者が多い会社は、多額の助成金を受給できるのです。
もっとも、これは令和7年に変更されたものではなく、令和6年の枠組みを引き継いだものです。
この点から、政府がキャリアアップ助成金の中でも、賃金関連の支援に力を入れていることが分かります。
今後の拡充に注目です。
引き上げ率
次に、引き上げ率の変更です。
令和6年と比較して、令和7年の賃金規定等改定コースは引き上げ率の区分が細分化されています。
令和6年の賃金規定等改定コースでは、引き上げ率の区分は「3%以上5%未満」または「5%以上」の二つだけでした。
これに対し、令和7年の賃金規定等改定コースは、上記の通り引き上げ率の区分を4種に細分化しています。
引き上げ率が6%以上の場合、令和6年は「5%以上」の区分で一人当たり6.5万円の受給でしたが、令和7年は「6%以上」の区分として一人当たり7万円を受給できるようになったのです(中小企業の場合)。
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、引き上げ率が細分化されたことで、一層利用しやすくなったといえるでしょう。
加算要件
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースは、一定の要件を満たすことで支給額の加算を受けられます。
この点も、令和7年は変更となりました。
令和6年は、職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合に、中小企業は20万円、大企業は15万円を加算する仕組みです。
令和7年も、令和6年と同様の措置によって中小企業は20万円、大企業は15万円の加算を受けられるほか、「有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合」にも同様の加算を受けられます。
いずれの加算要件も、1事業所当たり1回のみです。
令和6年は加算要件が一つしかなく、加算額は最大で20万円でした。
しかし、令和7年は加算要件が二つとなり、最大40万円の加算を受けられるようになります。
無理のない範囲で、積極的に狙っていきたいところです。
賃金規定等改定コースの注意点
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースを利用する際の注意点をまとめます。
賃金は一律で引上げ
まず注意したいのが、賃金規定等改定コースはあくまでも「一律で引上げ」が要件となることです。
賃金規定の増額改定にあたり、すべての等級(対象労働者が位置付けられていない等級も含め)で増額改定することになります。
数年前までは、支給額の区分が「全ての有期雇用労働者の賃金を増額」と「一部の有期雇用労働者の賃金を増額」で分かれており、必ずしも一律で引き上げる必要はありませんでした。
しかし、令和7年の賃金規定等改定コースは、一部だけを引き上げても受給できないため注意してください。
支給申請上限
キャリアアップ助成金の賃金規定等改定コースも、支給申請に上限があります。
1年間で賃金規定等改定コースを申請できるのは、1事業所当たり100人までです。
上記の通り、令和7年の賃金規定等改定コースは「一律引き上げ」が要件となるため、規模が大きい会社では対象労働者が100人を超えるかもしれません。
その場合、100人超の部分は支給対象外となるため注意してください。
引き上げ率3%以上をしっかりクリア
引き上げ率にも注意が必要です。
数年前、賃金規定等改定コースは引き上げ率2%から支給の対象となっていました。
これに対し、令和7年の支給対象は引き上げ率3%以上ですから、2%の引き上げでは助成金を貰えません。
引き上げ率3%をしっかりクリアしましょう。
キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コース
賃金に関するキャリアアップ助成金は、賃金規定等改定コースだけではありません。
キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースもそのひとつです。
キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースとは?
キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースは、雇用している全ての有期雇用労働者・無期雇用労働者に対し、正規雇用労働者と共通の賃金規定を作成・適用した場合に受給できる助成金です。
正規雇用と非正規雇用は、賃金規定が異なる場合が少なくありません。
能力や職務、責任の範囲など、あらゆる点で異なるためです。
ただし、非正規雇用の中にも、長期にわたって勤務を続け、高い専門性を有し、幅広い職務に対応するケースがあります。
その場合、正規雇用と同じ職務をこなしても、非正規雇用の賃金規定が適用され、十分な賃金を受け取れません。
キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースは、このような不公平の解消を目的としています。
賃金規定等共通化コースのメリット
賃金規定等共通化コースのメリットは、不公平感の解消により離職率の低減につながることです。
正規雇用と非正規雇用で職務を明確に分けている会社であれば、賃金規定等共通化コースはあまり役に立ちません。
その場合、賃金規定が異なるのが当然であり、なんら不公平感はないからです。
しかし、両者の職務が共通しており、非正規労働者が不公平感を抱いている場合、早急に解消すべきです。
このような不公平感は会社への不満となり、離職率の上昇に直結します。
人手不足が社会問題になっている昨今、非正規労働者の確保も容易ではありません。
離職率が高ければ、せっかく人材を確保しても、なかなか定着しないでしょう。
その根本的な原因が「賃金の不公平感」にある場合、離職率は高止まりし、常に人手不足に悩まされることになります。
思い切って賃金規定を共通化し、不公平感の解消によって定着率が高まれば、人材確保にかかるコストを削減できます。
とはいえ、賃金規定を共通化すれば、人件費の増加は避けられません。
そこで、キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースを利用し、負担を軽減しましょう。
非正規労働者の定着率が高まり、長期にわたって雇用できれば、その人材の能力や適性も見えてくるでしょう。
非正規労働者の中から、正規雇用に耐えうる人材を選び、的確に正社員化することも可能です。
この場合、賃金規定の共通化にあたってはキャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースを、正社員化にあたってはキャリアアップ助成金の正社員化コースを利用することで、キャリアアップ助成金の受給額を伸ばすこともできます。
賃金規定等共通化コースの支給額
キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースの支給額は以下の通りです。
- 中小企業…60万円
- 大企業…45万円
このように、賃金規定等共通化コースの支給額はごくシンプルです。
支給額の加算措置もありません。
数年前までは、共通化の対象労働者数が2人以上の場合、人数に応じて支給額が増額されていました。
この措置は令和4年から廃止されており、令和7年も同様です。
なお、キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースを受給できるのは、1事業所当たり1回のみとなっています。
賃金規定を複数回にわけて改定し、共通化した場合も1回しか受給できません。
令和7年の変更ポイント
令和7年、キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースに変更はありません。
令和6年と全く同じ仕組みで運用されています。
賃金規定等共通化コースの注意点
キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースの利用にあたり、注意したいのは負担の増加です。
賃金規定等共通化コースは、「雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合」に助成するものです。
共通化の対象が一部の有期雇用労働者だけであれば、助成金を受給できません。
全ての有期雇用労働者を対象に共通化することで、負担が想像以上に重くなることも考えられます。
職務に応じて賃金規定を共通化する以上、対象労働者の賃金は正規雇用並みになるということです。
例えば、特定の職務に従事する正社員の月給と、同じ職務に従事する有期雇用労働者の時給は同水準(正社員の月給÷正社員の月の労働時間≦有期雇用労働者の時給)でなければなりません。
具体的には、正社員Aの月給が20万円、月の労働時間数が160時間の場合、有期雇用労働者Bの時給は1250円(20万円÷160時間=1250円)以上になります。
共通化後の賃金テーブルをもとに計算し、実際の負担増を織り込むことが大切です。
キャリアアップ助成金の賞与・退職金制度導入コース
かつて、キャリアアップ助成金には「諸手当制度等共通化コース」というものがありました。
現在、このコースは「賞与・退職金制度導入コース」と名前を変えています。
キャリアアップ助成金の賞与・退職金制度導入コースとは?
政府が推奨している働き方改革のスローガンのひとつに「同一労働・同一賃金」があります。
キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースは、職務に応じて賃金を共通化するものです。
しかし、待遇の一律化は賃金に限ったことではありません。
諸手当制度等共通化コースでは、手当の共通化を目的としていました。
対象となる手当は、賞与・役職手当・特殊作業手当・皆勤手当・食事手当・地域手当・家族手当・住宅手当・時間外労働手当など。
令和4年から、対象となる手当の大部分が廃止され、賞与・退職金の二つのみとなりました。
それに伴い、「諸手当制度等共通化コース」から「賞与・退職金制度導入コース」へと名称が変わったのです。
全ての非正規労働者を対象に、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積み立てを実施した場合に助成金を受給できます。
すでに廃止された手当については、共通化しても助成金は受け取れません。
共通化を先延ばししていたために、助成金を受給できなかった会社も多いことでしょう。
キャリアアップ助成金には、しばしばこういったことがあるため注意が必要です。
賞与・退職金制度導入コースのメリット
キャリアアップ助成金の賞与・退職金制度導入コースのメリットは、非正規労働者のモチベーションアップや、定着率アップが期待できることです。
賞与とは、定期または臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)を指します。
労働者の勤務成績に応じて支給するのが一般的です。
賞与がない場合、非正規労働者はいくら頑張っても給与に反映されず、モチベーションも低下しがちです。
賞与制度を導入することで、非正規労働者にも働きがいが生まれ、モチベーションのアップが期待できます。
退職金は、労働者が退職する際、在職年数等に応じて支給するものです。
退職金制度は、退職金を積み立てるための制度であり、就業規則または労働協約に則り、会社の負担で積み立てなければなりません。
退職金制度がない場合、従業員は退職時に一銭も受け取ることができず、「いつ辞めてもいい」といった考えになりがちです。
退職金がないことが不安につながり、退職金制度がある会社へ転職したいと考える人も少なくないでしょう。
つまり、退職金制度がないことにより、離職率が高くなるのです。
退職金制度を導入すれば、勤続年数が長くなるほど退職金の積み立ても増えていき、安心して長く勤めることができます。
これが定着率の向上につながり、人手不足の解消に役立つのです。
賞与・退職金制度導入コースの支給額
キャリアアップ助成金の賞与・退職金制度導入コースは、導入する制度と企業規模によって支給額が変わります。
具体的な支給額は以下の通りです。
- 中小企業…賞与または退職金制度のいずれかを導入すれば40万円、賞与・退職金制度を同時に導入すれば56.8万円
- 大企業…賞与または退職金制度のいずれかを導入すれば30万円、賞与・退職金制度を同時に導入すれば42.6万円
賞与・退職金制度導入コースに加算措置はありません。
諸手当制度等共通化コースでは、多くの手当が対象となっていたため、複数の手当を共通化することで支給額が加算されていました。
共通化する手当の2つ目以降について、1つ当たり16万円の加算を受けることができたのです。
しかし、賞与・退職金制度導入コースの対象は賞与と退職金だけですから、このような加算は廃止されています。
なお、賞与・退職金制度導入コースを受給できるのは、1事業所当たり1回のみです。
令和7年の変更ポイント
令和7年、キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースに変更はありません。
令和6年と全く同じ仕組みで運用されています。
賞与・退職金制度導入コースの注意点
キャリアアップ助成金の賞与・退職金制度導入コースを利用する際、以下の点に注意してください。
受給できないケースがある
まず、受給できないケースに注意が必要です。
上記の通り、キャリアアップ助成金の賞与・退職金制度導入コースは、元々諸手当制度等共通化コースとして運用されていました。
過去に諸手当制度等共通化コースを利用し、助成金を受給した会社もあるはずです。
その場合、賞与・退職金制度導入コースの支給対象外となります。
例外的に支給対象となるのは、健康診断制度の新設に伴い、諸手当制度等共通化コースを利用している場合です。
それ以外は、手当の内容に関係なく支給対象外となるため注意してください。
賞与・退職金制度を“同時に”導入
賞与・退職金制度導入コースを受給できるのは、1事業所当たり1回だけです。
賞与と退職金制度の両方を導入する際は、同時に導入することが要件となっています。
もっとも、これは「新たに就業規則等に規定されたタイミング」が同時ということで、「初回の賞与支給日と、初回の退職金積立日が同日」ということではありません。
とはいえ、導入(新たに就業規則等に規定したタイミング)が異なる場合、「賞与・退職金制度を同時に導入」したものとはみなされず、あくまでも「賞与または退職金制度のいずれかを導入」の区分となります。
同時に導入すれば56.8万円を受給できたものが、40万円に減ってしまうのです。
両方の導入を検討している会社は、同時に導入してください。
金額をしっかりクリア
賞与・退職金制度導入コースは、導入するだけではなく実際に支給して、はじめて助成対象となります。
この時、賞与の支給額または退職金の積立額に注意が必要です。
賞与制度を導入する場合、初回の賞与は6ヶ月分相当として5万円以上を支給する必要があります。
退職金制度については、1ヶ月分相当として3000円以上を6ヶ月分、または6ヶ月分相当として1.8万円以上を積み立てることが要件です。
同時導入によって受給するならば、賞与5万円・退職金1.8万円をクリアしなければなりません。
また、賞与・退職金制度は事業主の負担で運用することが前提です。
特に退職金にいえることですが、基本給や諸手当を減額して退職金に振り替えるケースがあります。
この場合、会社の負担で退職金を積み立てたとはいえず、助成金を受給することもできません。
キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コース
最後に、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースを解説します。
キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースとは?
以前から、キャリアアップ助成金には短時間労働者の処遇改善に関するものがありました。
令和5年まで、「短時間労働者労働時間延長コース」として運用されていたものです。
有期雇用労働者の労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成金を支給していました。
これが、令和6年から「社会保険適用時処遇改善コース」に変わり、支給要件も変更となっています。
キャリアアップ助成金の他のコースに比べて、やや複雑なため注意が必要です。
現時点では、社会保険適用時処遇改善コースは令和8年3月31日までの暫定措置とされています。
令和8年度、暫定措置が延長されるのか、あるいは短時間労働者労働時間延長コースに戻るのか、はたまた新たなコースが設置されるのか要チェックです。
社会保険適用時処遇改善コースのメリット
キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースのメリットは、人手不足の解消に役立つことです。
人手不足を解消するには、新たな人材を確保する、既存の人材の能力を上げる、既存の人材の労働時間を延長する、といった方法があります。
短時間労働者が多い会社は、その労働時間を延長することで人手不足の解消が期待できます。
しかし、労働時間の延長には負担がつきものです。
労働者の中には、被保険者になることで社会保険料などが差し引かれ、賃金総額が減ることを嫌う人もいます。
会社側としても、労働時間が伸びた分だけ支払う給与は増え、人件費の負担は避けられません。
そこで、キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースが役立ちます。
後述の通り、社会保険適用時処遇改善コースには、手当等支給メニューと労働時間延長メニューの二つがあります。
手当等支給メニューは、新たに被保険者になった労働者の賃金総額を増やすことで、助成金を受け取るものです。
労働時間延長メニューは、労働時間の延長によって助成金を支給します。
二つのメニューを併用し、ダブルで受給することも可能です。
キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースをうまく活用すれば、労働時間の延長に伴う負担を労働者・会社の双方で軽減できます。
社会保険適用時処遇改善コースの支給額
キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースの支給額を、メニュー別にみていきましょう。
手当等支給メニュー
手当等支給メニューは、新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組みを行った場合に助成するものです。
賃金増額の取り組みは、3年間にわたって行います。
1年目~2年目は、労働者負担分の社会保険料相当額の手当支給または賃上げの実施。
これにより、中小企業は40万円(10万円×4期)、大企業は30万円(7.5万円×4期)の助成金を受給できます。
6ヶ月を1期とするため、2年間の取り組みでは4期にわたって分割で受給するわけです。
3年目は、恒常的な所得の増加を目指し、基本給の総支給額を18%以上増額します。
これにより、中小企業は10万円、大企業は7.5万円の助成金を受給できます。
3年間の取り組みを全てクリアすれば、中小企業は50万円の助成金を受給できるのです。
なお、加算措置はありません。
労働時間延長メニュー
労働時間延長メニューは、週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施することで、当該労働者が社会保険の被保険者となった場合に助成するものです。
延長時間が4時間以上の場合、賃金は据え置いたまま中小企業30万円、大企業22.5万円が支給されます。
延長時間が4時間未満であっても、賃金を引き上げることで同額の支給対象となります。
延長時間が3時間以上4時間未満の場合には5%以上の引き上げ、2時間以上3時間未満の場合には10%以上の引き上げ、1時間以上2時間未満の場合には15%以上の引き上げが要件です。
労働時間延長メニューにも加算措置はありません。
令和7年の変更ポイント
令和7年、キャリアアップ助成金の賃金規定等共通化コースに変更はありません。
令和6年と同じ仕組みで運用されています。
社会保険適用時処遇改善コースの注意点
キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースを利用する際は、併用に注意してください。
手当等支給メニューと労働時間延長メニューは併用できます。
ただし、併用できるパターンは「社会保険加入後、手当等支給メニューの1年目の取り組みを実施し、2年目に労働時間延長メニューの取り組みを実施した場合」だけです。
この場合、手当等支給メニューとして20万円、労働時間延長メニューとして30万円、合計50万円が支給されます。
上記以外の併用は認められていません。
例えば、労働時間延長メニューを先に取り組んでしまうと、手当等支給メニューは受給できなくなります。
併用した際の支給総額は、手当等支給メニューを3年にわたって実施した場合と同じです。
自社に適した方法で取り組みましょう。
まとめ:キャリアアップ助成金で経営改善を促進しよう
この記事では、キャリアアップ助成金の最新情報をまとめました。
キャリアアップ助成金を活用すれば、負担を軽減しつつ経営改善に取り組むことができます。
ただし、実際の活用には専門家の協力が欠かせません。
キャリアアップ助成金は、毎年のように改定されています。
令和7年も様々な点で変更されました。
変更点を逐一チェックし、柔軟に活用していくことは容易ではありません。
また、助成金は後払いですから、先行コストの負担を資金繰りに織り込む必要があります。
キャリアアップ助成金の活用でお困りの方は、No.1までお気軽にご相談ください。
No.1は、売掛金の早期資金化とコンサルティングを行っています。
キャリアアップ助成金の活用を「助成金による経営改善」「売掛金の早期資金化による先行コストの確保」の両面からサポートします。
ファクタリングなら株式会社No.1 詳細情報
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。
よく見られているファクタリング記事