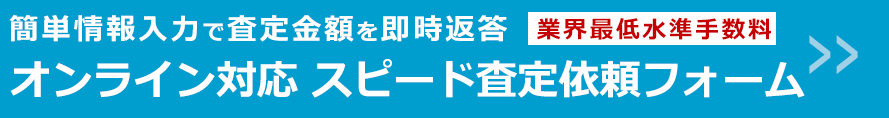カテゴリー: 資金調達情報
株式発行で資金調達する仕組みを解説!メリット・デメリット、銀行融資との比較・使い分けも解説
「資金調達」に関する悩みを抱えている中小企業や個人事業主様は少なくありません。状況次第では資金繰りが上手くゆかないことが、経営に大きな影響を与えてしまうという可能性も考えられます。事業を継続し会社を発展させていくためには資金調達が重要であり、「株式発行」はその選択肢の1つとなります。
融資ほど一般的ではないことから利用を検討されていないかも知れませんが、会社の状況によっては資金繰りの助けになる可能性が大きいです。本稿では一度は検討してみるべき「株式発行」について、仕組みやメリット・デメリット、銀行融資との比較による使い分けなどを解説させていただきます。
「株式発行」とは?
まず「株式」とは、株式会社が発行する有価証券であり、企業の中での権利や地位を指すことにもなるものです。株式を有していると「株主」となることができ、その持ち株数に応じて配当金や経営権(株主総会においての議決権)などが得られるようになります。そして株式発行とは、株式を発行し投資家などからの出費を募る行為のことを呼びます。
株式発行はエクイティファイナンス
株式発行は「エクイティファイナンス」とも呼ばれます。エクイティ(Equity)には、返済に関する取り決めのない資金というような意味があり、株式資本や自己資本を現すこともあります。そしてファイナンス(Finance)には金融という意味のほか、資金の管理や供給という意味も含まれています。ちなみに銀行融資や社債による資金調達方法は、「デッドファイナンス(Debt finance)」と表現されることが多々あります。
株式発行の資金調達コスト(株主資本コスト)
資金調達の際、調達コストについてよく考えるべきです。
調達コストは資金繰り負担に直結するため、安いに越したことはありません。
株式発行で資金調達する場合に必要なコストを「株主資本コスト」といいます。
株式発行する会社からみると「資金調達コスト」であり、株主(出資者)からみると出資によって期待できる「収益率」といえます。
株式発行の際、出資者が期待する収益は、大きく分けて以下の2種類です。
- キャピタルゲイン:株価の値上がりによって期待できる差益
- インカムゲイン:配当(利益の還元)によって期待できる収益
上場企業の株主資本コスト(全業種平均)の中央値は3.5% となっており、これが株式発行の資金調達コストの目安となります。
これは、「出資額に対して3.5%程度の収益率が期待できる場合、株式発行に成功するケースが最も多い」ということです。
もちろん、会社によって株式発行の環境は大きく異なります。
将来性のある会社は、主にキャピタルゲインによる収益を期待されるため、配当ゼロでも株式発行できる可能性があります。
逆に、将来性があまりない会社が株式発行する場合、キャピタルゲインによる収益は期待できません。
期待収益は主にインカムゲインによるものですから、それなりの配当を設定する必要があるでしょう。
将来性が危ぶまれる会社が株式発行するならば、出資者は株価下落リスクを考えなければなりません。
値下がりをカバーできるだけの配当を出せば株式発行もあり得ますが、株主資本コストが膨らみます。
そもそも、配当金の原資は利益剰余金であり、分配できる配当金には限度があります。
株式発行を成功させたいからといって、配当金を自由に(高く)設定することはできません。
このように、株主資本コストの中央値が3.5%といっても、実際には中央値から上振れ・下振れする可能性があります。
ここで挙げた3.5%の数値は、あくまでも目安と考えてください。
株式発行による資金調達のメリット・デメリット
株式発行(エクイティファイナンス)は非常にメリットの多い資金調達方法ではあるのですが、やはり気をつけるべきデメリットも存在しています。この資金調達方法は融資などよりも複雑な面があることから、メリットだけに意識を向けるのではなく、どのような危険性が潜んでいるかも正しく理解しておくことが大切です。
株式発行による資金調達のメリット
株式発行による資金調達のメリットは以下が挙げられます
負債にならず返済義務がない
株式発行によって調達した資金は、「負債」として扱われることはありません。利益が発生した際には配当金を支払う必要はありますが、返済義務はもちろんなく、株価が下がったとしても補償を求められることもありません。さらに融資のように負債の額が増え債務超過に陥る恐れもなく、利息の支払いに追われる負担もないのは大きなメリットと言えます。
自己資本比率が高まる
企業の総資本に対して自己資本がどれほどの割合を占めているのかは、「自己資本比率」を見ればわかります。総資産が多くとも負債の割合が多くては安定した運営を行うことが難しくなりますが、自己資本比率が高ければ安定した経営が行いやすい企業と判断することができます。株式発行は負債を増加させずに資産を増やすことができますので、自己資本比率を高めることができるのです。
企業としての評価が向上する
株式を発行しても、出資する投資家の目に留まらなければ資金調達は失敗します。逆に言えば、株式発行を行い資金調達に成功しているということは、投資家から見て魅力を感じる企業であるという証拠です。つまり株式発行で資金調達に成功すれば、他社から見た企業としての評価も向上することが期待できます。
株式発行による資金調達のデメリット
株式発行による資金調達のデメリットは以下が挙げられます
経営権を失う可能性がある
株式とは企業内の地位を示すものでもあり、数多くの株を所持している株主は経営に対して影響力を持つことができます。これにより株主の意向を意識した運営を行う必要性が発生することになり、場合によっては企業の運営権そのものを奪い取られてしまう危険性も考慮しなくてはなりません。
新株発行で株主から反発を受けるリスク
株式を活用した資金調達では、追加で資金を得るために新株の発行を行うことが可能です。しかし新株発行を行うことで一株あたり価値が下がることになり得ることから、株主からの反発が起きる可能性があります。
新株の発行が企業の成長に必要であり、企業価値が高まる期待が高いと株主に納得してもらえないと、理解を得るのは容易ではないでしょう。
複雑な手続きや税務・法規制に対応する必要性
株式発行による資金調達は、法規制への対応や資金調達後の税務処理など、様々な手続きが必要です。そのため、弁護士や税理士などの専門家からサポートを受けて手続きを行わなくては、思わぬトラブルを引き起こすことになりかねません。
融資など資金調達には様々な選択肢がありますが、株式発行はその中でも手続きに大きな手間と労力が必要になる資金調達方法であることは確かです。それだけに大きなリターンも期待できますが、利用するかは慎重に判断するべきかも知れません。
株式発行の流れ
ここからは株式発行の流れを簡単に説明します。多くの場合は専門家による主導の元、順を追って様々な項目に関しての決断をくだし手続きを進めることになります。実際の株式発行の際には、これからご紹介する手続きの進め方や内容と違いが出ることが予想されますが、ある程度スケジュールを理解しておくことで対応もしやすくなるはずです。
「株式の設計」を行う
まずは「株式の種類・対象・募集数・一株あたりの金額・払込期日」などを決定します。新株発行に関する募集事項を決めることを「株式の設計」と呼び、内容を確定するためには株主総会での承認や取締役会での決議などが状況によって必要になります。株式の設計が完了すれば、株式の引受人の募集へと進みます。
出資者を募り割当を決定する
募集項目に対して納得した出資者は、必要な事項を記載した書類とともに株式の引受人としての申し込みを行います。企業側は申し込みを受けた出資者に対して割り当てる株式の数などを決定していきます。「割当自由の原則」により、誰に何株を割り当てるかは企業側の判断次第です。
出資者が払込を実行する
割り当てられた株式の数に応じて、出資者は期限内に出資の履行を行います。期限内に支払いを完了できない場合には権利は失効し、出資が完了した日から株主として認められることになります。
登記事項を変更
登記簿には資本金の額や発行している株式の総数などが記載されています。ですから新株の発行により資金調達を行った後には、登記の変更手続きを行わなくてはなりません。株式の出資の履行期日から2週間以内に、企業の本社を管轄する法務局で手続きを行いましょう。
「3種類」の株式発行による資金調達
株式発行には大きく分けて新規発行と増資のふたつがあります。
新規発行は、株式会社の設立時に行う株式発行です。
増資は、株式会社設立後、資金調達その他を目的として行います。
新規発行と増資は、準備や手続きの面で大きく異なります。
とはいえ、株式発行による資金調達という意味では、新規発行も増資も同じと考えることもできますから、ここでは「株式発行=増資」と考えてみていきましょう。
増資には、割り当てる対象によって
「公募増資・第三者割当増資・株主割当増資」の3つの選択肢があります。3つの選択肢はそれぞれにメリットもデメリットもあり、特徴をよく理解した上で選択しなくてはなりません。選択肢によって、資金調達が成功できる確率にも大きな違いが発生するかも知れませんので、専門家と相談しながら検討することが重要です。
公募増資
特に対象を指定すること無く、不特定多数を対象として新株を時価で発行するのが「公募増資」です。公募増資の特徴は、株式発行の対象者を既存の株主、特定の出資者、金融機関などの的確機関投資家に限定せず、一般の投資家を対象に広く株式発行を行うこと。
主に上場企業が行う資金調達方法であり、会社の評価や知名度次第では大きな額の資金調達が期待できます。
公募増資のメリットとしては、時価で発行するため、会社の評価が高ければ多額の資金調達が行える期待が高くなります。しかし逆に評価が低い場合には、株主が集まったとしても思ったように資金調達が行えない可能性もあります。主に上場企業が行う株式発行の選択肢であることもあり、株の売買が積極的に行われやすいことも株主から見たメリットとなります。
このほか、株式発行で資金調達すると同時に、株主の層を厚くするのにも効果的です。
一方公募増資のデメリットとして、対象が不特定多数であることで株主の保有株数の比率が把握しにくく、経営権の維持に細心の注意を払う必要があることが挙げられます。また、既存株主以外に対して広く株式発行するということは、とりもなおさず「新たな株主が加わり、株主権を有する」ということです。
既存株主が不利益を被る可能性があるため、公募増資として株式発行を選ぶには、株主総会の特別決議が必要になることもあります。
株主割当増資
既存の株主を対象に、各株主が保有している株数に応じた新株を割り当てるのが「株主割当増資」です。もっとも、全ての既存株主に自動的に株式発行を行うのではなく、「新たに発行する株式の割り当てを受ける権利」を付与する形を取ります。
この権利の割り当てが、全ての既存株主に平等に付与されるのが、株主割当増資の特徴です。
既存株主がこの権利を行使し、資金を払い込めば資金調達は完了です。
もちろん、株主は権利を行使しない選択もできます。
株式発行の条件が不利と判断すれば、株主は権利を行使しなければよいだけですから、株式発行の条件は会社が自由に設定できます。
例えば、市場の実勢価格を考慮せず、発行価格を決めることも可能です。
全ての株主が新株を引き受ければ保有株数の比率に変動はありませんが、
企業側は権利を与えるだけであり、割り当てられた新株をどれだけ引き受けるかは株主次第となります。
株主割当増資のメリットとして、対象が既存の株主であることから、理解を得ることができれば手続きは素早く進む可能性が高くなります。また各株主の保有株数に大きな変動が出ないことが期待され、経営権の維持が行いやすいのも特徴です。
株主割当増資のデメリットは、株主側からするとメリットを感じにくく、理解を得られず新株の引受を拒否された場合には資金調達が上手く行かないだけでなく、保有比率に想像以上の変動が現れる可能性も否定できません。
第三者割当増資
「第三者割当増資」では対象は既存の株主であるかは問わず、特定の第三者に対して新株を引き受ける権利を与えます。自社の役員や親族、取引先や出資者など縁の深い企業などを選ぶのが一般的であり、主に未上場企業が行う資金調達方法です。
株式発行のうち、第三者割当増資を選んだ場合、新たな株主が加わることで持ち株比率が変化します。
これが第三者割当増資を選ぶメリットになります。
分かりやすいのが、敵対的買収の回避。
自社が敵対的買収を受けた際、第三者に積極的に株式発行を行うことで、買収を仕掛けている会社の持ち株比率を下げることができます。
また、新株の引受対象を自社と関係の強い人物・企業とすることで、お互いの関係性強化が期待できます。他社との業務提携を目的とする場合、第三者割当増資で相互に出資し合うことも多いです。
ですが特定の株主の保有株数が増加することになることから、対象とならなかった株主から反発を受ける可能性も考えられます。第三者割当増資で気を付けるべきは、株式発行価格が市場の実勢価格より低いケース。
この場合、割り当ての権利を付与されなかった既存株主が不利益を被り、反発を招く可能性が高いです。
したがって、第三者に有利な価格で株式発行を発行する場合、株主総会の特別決議が必要となります。
株式発行と株主権
上記の株式発行によって資金調達した場合、必ず直面する問題が「株主権」です。
株式発行で調達した資金には、原則として返済期限がありません。
とはいえ、株主も経済的利益を目的としており、株主権として自益権と共益権を持っています。
株式発行で資金調達するならば、株主の権利をよく知り、株式発行によって受ける経営干渉を詳しく理解することが重要です。
株式発行と自益権
自益権は、株主の経済的利益に直接結びつくものです。
自益権の代表的なものに、利益配当請求権・残余財産分配請求権・株式買収請求権などがあります。
利益配当請求権
利益配当請求権とは、株式発行後、株主総会の決議によって配当金の支払いが決定した場合、株主が配当の支払いを請求する権利です。
株式発行で資金調達した会社にとって、これが資金調達コストのひとつになります。
残余財産分配請求権
残余財産分配請求権は、株式発行会社が解散し、清算手続き終了後に財産が残っていた場合、株主が持ち株に応じて残余財産の分配を請求する権利です。
株式発行で資金調達しながらも事業が立ち行かなくなって解散・清算というケースがほとんどですから、財産が残っていないのが普通です。
ただし最近では、後継者不足により解散を余儀なくされる会社も増えています。
その場合、株式発行会社に残余財産があることも十分に考えられ、残余財産分配請求権の行使も可能です。
株式買収請求権
株式買収請求権は、株式発行会社に対し、持ち株の買取を請求する権利です。
ただし、一般的な株式の売買とは異なり、返済・償還の意味合いがあります。
例えば、株主総会で事業譲渡の決議がなされる場合、株主が受ける影響は小さくありません。
決議に反対する株主も出てくるでしょう。
とはいえ決議されたものはどうしようもありませんから、反対する株主は株式発行会社に対し、持ち株を公正価格で買い取るよう請求します。
この場合、株主から株主へ株式を売却・譲渡するのではなく、株式発行会社に直接買い取りを求めるのが特徴です。
当然ながら、買い取りに応じることで、株式発行会社の資金は流出します。
また、株式発行したものを買い戻すという意味では、返済・償還にほかなりません。
株式発行による資金調達の大きなメリットは、返済不要ということです。
しかし、株式発行の「返済不要」はあくまでも原則であって、原則があれば例外があります。
株主が株式買収請求権を行使した場合、「返済不要」の原則から外れます。
株式発行は、絶対に返済不要とは限らないのです。
株式発行と共益権
共益権は、株主が会社経営に参加する権利です。
共益権には、1株でも持っていれば行使できる「単独株主権」と、一定の株式を保有することで孔子できる「少数株主権」があります。
単独株主権の代表的なものは、差し止め請求権や訴訟提起権です。
なお、自益権は全て単独株主権に属します。
少数株主権は、株主総会招集請求権、会計帳簿閲覧請求権など。
持ち株が多くなるほど共益権は強くなり、株式発行会社も影響を受けやすくなります。
株式発行で資金調達し、なおかつ経営への干渉をできるだけ避けたい場合には、少数株主権を抑えるのがポイントです。
特定の機関投資家に多くの株式発行をするよりも、不特定多数の個人投資家に株式発行するよう意識しましょう。
種類株式という選択肢
株式発行の種類はまだまだあります。
種類株式も、株式発行による資金調達のひとつです。
株式発行の一種である以上、株式発行の仕組みは公募増資・第三者割当増資・株主割当増資と基本的に変わりません。
ただし、一般的な株式発行と、種類株式の発行は、戦略的な意味合いが異なります。
種類株式は、株式に様々な権利を付けて発行するのが特徴です。
これにより、通常の株式発行における株主権(自益権・共益権)とは異なる権利・制限が生まれ、戦略的な意義も生まれるというわけです。
株式発行で資金調達する際、あえて種類株式を選ぶことによって、自社のニーズに合わせた株式発行が可能となります。
種類株式の仕組み
種類株式で資金調達する場合、株式発行する会社は種類株式を発行し、払い込みを受けることで資金を調達します。
株式発行の仕組みは、通常の増資とほとんど同じ同じです。
ただし、種類株式を引き受けた株主は、種類株式を保有している期間中、普通株主とは異なる権利を得ることになります。
種類株式に付帯する権利の内容は様々ですが、株主側に有利な権利(株式発行した会社の権限を制限するもの)と、発行者に有利な権利(株主の権利を制限するもの)に大別されます。
種類株式の区分
種類株式の区分はふたつ。
会社法では、通常とは権利の異なる株式発行を行う際、株主間の権利に格差が生じない場合と生じる場合を明確に分けています。
法律上、「種類株式発行会社」に位置付けられているのは後者です。
株主間の権利に差が生じない場合とは、株式発行の全ての株式が同じ種類であることを意味します。
株主に格差が生じない種類株式
株式発行によって株主に格差が生じない種類株式として、会社法が認めているのは3種類です。
まず、譲渡制限付きの種類株式。
これは、株式を譲渡する際、株式発行会社の承認が必要となる種類株式です。
会社が望まない者への譲渡を防ぐことを目的としています。
次に、取得請求権付きの種類株式。
これは、株式発行会社に対し、株式の取得を請求する権利を付帯した種類株式です。
取得請求権を行使した株主は、取得対価として社債や新株予約権、その他財産などを受け取ります。
最後に、取得条項付きの種類株式。
これは、一定の条件の下で、株式発行会社が株主から株式を取得できるよう定められた種類株式です。
取得対価として社債や新株予約権、その他の財産が株主に付与されます。
株式発行にあたり、上記3種の種類株式のうち1種類だけを発行することが条件です。
この3種類の種類株式であっても、2種類以上を同時に発行すれば後述(種類株式発行会社)となります。
株主に格差が生じる種類株式
株式発行にあたり、異なる2種類以上の種類株式を発行する場合、会社法により「種類株式発行会社」に指定されます。
会社法が挙げている、9種類の種類株式を簡単にみていきましょう。
- 剰余金の配当…配当の金額や優先度の異なるもの。金額や優先度を高く設定する代わりに、議決権を制限するケースが一般的。経営への干渉を避けながら株式発行できる。
- 残余財産の分配…残余財産分配の金額や優先順位が異なるもの。精算時のインセンティブにより、経営が苦しい会社でも株式発行しやすくなる。
- 議決権制限株式…議決権の一部または全部を制限する種類株式。議決権以外の権利(配当など)を重視する株主を集めやすい。株式発行で資金調達したいが、経営への干渉を避けたい場合に効果的。
- 譲渡制限株式…株式の譲渡にあたり、株式発行会社の承認を必要とする種類株式。株式発行会社が取締役会を設置している場合には取締役会の承認、それ以外は株主総会での承認が必要となる。株式発行会社に不利な株式譲渡を避けるのに有効。
- 取得請求権付株式…株式発行会社に対し、株主が持ち株の取得を請求できる種類株式。これにより、株主は譲渡以外の方法で投資資金を回収でき、株式発行会社は望まない譲渡を防ぐことができる。
- 取得条項付株式…一定の条件で、株式発行会社が株主から株式を取得できる種類株式。株主の意思に関係なく取得できるため、持ち株比率のコントロールも可能となる。
- 全部取得条項付き株式…株主総会の決議によって、株式発行会社が株主から全株を取得できる種類株式。反対株主には買取請求権を認めるのが一般的。
- 拒否権付株式…決議の際、株主総会と当該種類株主総会の決議を必要とする種類株式。譲渡制限株式などと組み合わせることで、拒否権は更に強力となる。
- 選解任株式…当該種類株主総会で、取締役や監査役の選解任を可能とする種類株式。
種類株式による資金調達の特徴
種類株式の特徴は複雑であり、通常の株式発行で資金調達する場合に比べて活用の幅は広く、難易度は高めです。
種類株式の中には、株主の権利を制限するものがあり、2種類以上の種類株式を組み合わせることで、株式発行の意図が見えにくくなることも。
したがって、株式発行会社は、株主に目的を理解させることが重要となります。
もちろん、単に理解させるだけではなく、目的達成のための運営力(とりわけ資金活用管理能力)も求められるでしょう。
つまり、株式発行の際、特に種類株式を選ぶ会社は、投資家への説明負担、そして株式発行後の運営負担をよく検討する必要があります。
また、種類株式を選んだことで、株式発行の「返済不要」というメリットが減退することもしばしばです。
このことは、取得請求権や取得条項付きの種類株式を考えると分かります。
種類株式は、株式発行による資金調達に加えて、投資家のニーズと自社のニーズをうまくかみ合わせながら設計できるのが魅力です。
自社が株式発行を検討する理由は様々ですが、自社の事情(株式発行の目的や資金使途)をよく理解していなければ、種類株式は不向きといえるでしょう。
場合によっては、株式発行のメリットを損なうこともあり得るのです。
種類株式の発行はハードルが高く、資金調達に活用できる会社は限られます。
特に種類株式を選ぶべき理由がなければ、通常の株式発行(普通株式による増資)を選ぶのが無難でしょう。
新株予約権も株式発行の一種
株式発行による資金調達はほかにもあります。
増資、種類株式の次は、新株予約権についてみていきましょう。
新株予約権とは?
新株予約権は、その名の通り権利の一種です。
会社が株式発行する際、事前に設定した価格で取得する権利を新株予約権といいます。
新株予約権は、ここまで解説した株式発行の中でも、比較的新しい資金調達方法です。
かつては新株引受権と呼ばれており、株式発行のパターンは社債と組み合わせる、もしくは取締役や従業員にストックオプションとして付与するかのいずれかしか認められていませんでした。
2002年の商法改正により、現在はそのような規制はなくなっており、株式発行・資金調達への活用範囲が大きく広がりました。
新株予約権で資金調達する仕組み
新株予約権は、株式発行にあたって出資者が対価を支払い、株式を購入する形で権利を行使します。
つまりコール・オプションであり、新株予約権を保有しているということは、株式のコール・オプションを購入したことにほかなりません。
コール・オプションの買い手は出資者、売り手は株式発行会社という関係です。
これが、増資や種類株式発行と、新株予約権の大きな違いといえます。
通常の株式発行は、株式発行会社から出資者に株式を割り当て、その対価を受け取ることで資金調達します。
特に段階を経ることはなく、株式発行すなわち資金調達です。
これに対し、新株予約権は「新株予約権の発行」と「権利の行使」の二段階を経て資金調達します。
段階ごとに簡単にみてみましょう。
一段階目の新株予約権の発行は、「募集事項の決定→新株予約権の募集→申し込みの受け付け→新株予約権の割り当て」という流れで行います。
この時点では、株式発行会社は新株予約権の募集と割り当てを行うだけで、出資者から対価を受け取ることもありません。
二段階目の権利の行使は、「株式発行→新株予約権の行使→対価の支払い→株式の交付」という流れです。
二段階目でようやく、出資者は新株予約権を行使して株式を購入します。
株式発行会社が新株予約権の対価を受け取り、資金調達するのも二段階目です。
ただし、中には新株予約権そのものに対価を支払うタイプもあります。
この場合、一段階目(新株予約権の発行)と二段階目(権利の行使)の両方で資金調達することになります。
とはいえ、新株予約権を販売する場合、これはコール・オプションの販売ということであって、後の株式発行・権利行使と紐づけられたものです。
したがって、新株予約権による資金調達は、あくまでも権利行使が資金調達の本体と考えてください。
新株予約権と社債の関係
新株予約権を考えるとき、ややこしいのが社債との関係です。
前述のように、かつて新株予約権は社債の発行とセットになっていました。
株式発行にあたり、新株予約権と社債を組み合わせたものが「新株予約権付社債」です。
現在も、新株予約権付社債がなくなったわけではなく、社債の発行を伴うかどうかによって新株予約権の構造が大きく変わってきます。
新株予約権の発行に社債を伴う場合、上記の新株予約権発行の流れに「社債発行」の要素が加わります。
ただし、「新株予約権発行→社債発行」という流れではなく、「新株予約権付社債の発行」というように一体で行うものです。
この場合、「新株予約権付社債の発行」と「権利の行使」の二段階に分けて資金調達します。新株予約権付社債のうち、新株予約権の部分は権利の行使と紐づけられており、発行の時点では資金調達にならないことも多いのですが、社債の部分は権利の行使とは無関係であり、発行の時点で対価を受け取ります。
新株予約権付社債は「新株予約権の行使に伴う株式対価の払い込み」と「社債対価の払い込み」の二段階で資金を調達するのが特徴です。
さらに、新株予約権付社債には、転換型か否かの区別もあります。
転換型の場合、株式の交付を受けるとき、払い込みを社債で行うことにより社債を消滅させます。
新株予約権の行使に伴い、社債から株式へと転換するわけです。
このタイプを「転換社債型新株予約権付社債」といい、資金調達は社債対価のみとなります。
その他のバリエーション
新株予約権は、社債付き・転換型などのほかにもいくつかのバリエーションがあります。
株式発行による資金調達で比較的利用されているのは、価格修正や権利行使要求などの要素を加えた新株予約権です。
前述の通り、新株予約権は「株式発行の際、事前に決まった価格で株式を取得する権利」であり、通常は価格修正が行われません。
しかし、株式発行会社の株価変動に応じて価格修正が行われる新株予約権も存在します。
行使価格修正条項付新株予約権というものです。
また本来、新株予約権の行使は権利者の意思によって行われるものですが、株式発行会社から権利行使を要求できるものがあります。
このような新株予約権を、特に「エクイティ・コミットメント・ライン」とよびます。
新株予約権を活用した株式発行
ここまでの解説からも分かる通り、新株予約権は通常の株式発行よりも複雑です。
それだけに、上手く活用すれば株式発行の幅が広がります。
株式発行に新株予約権を活用する際、ポイントとなるのは社債の有無です。
社債付きの新株予約権で資金調達する場合、株式発行に公募債の特徴が加わります。
社債を付けない新株予約権は、第三者割当増資の特徴がベースと考えてよいでしょう。
いずれにせよ、通常の株式発行よりも新株予約権の方が資金調達の難易度は高くなります。
というのも、新株予約権はオプションであり、権利の行使は出資者の意思に任されるため、資金調達の見通しを立てにくいのです。
例えば、1株1万円の価格を設定し、1万株分の新株予約権を発行したとしましょう。
この新株予約権を全て割り当てても、1億円の資金調達になるとは限りません。
あくまでも、資金調達は株式発行時の権利行使・払い込みによって決まります。
権利が全く行使されなければ、株式発行したところで全く資金調達できないのです。
新株予約権付社債も同様です。
株式発行で資金調達すれば返済不要ですが、社債には返済義務があります。
権利が行使されれば株式発行で資金調達できますが、そうでなければ社債(負債)が残るだけです。
このような資金調達の不透明さは、新株予約権ならではの特徴といえるでしょう。
その反面、新株予約権を事前に割り当てておくことで、実際の株式発行と資金調達がスムーズとなり、安定的な資金確保につながるのが利点といえます。
株式発行に新株予約権を利用する際には、資産と負債のバランス管理(社債付きの場合)や、資金調達・資金使途などの管理体制をしっかり構築する必要があります。
新株予約権は、通常の株式発行とは異なり、「将来の成長のための追加的な資金手当て」と位置付けるのが良いでしょう。
「株式発行=上場」ではない
株式発行の色々な形をみてきました。
ところで、「株式発行」と聞いたとき、「上場」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
確かに、上場の際には株式発行を行います(いわゆるIPO)。
上場企業が資金調達の際、「社債付き」「新株予約権」といった応用的な株式発行を活用することもしばしばです。
しかしながら、株式発行と上場はイコールではありません。
出資による資金調達も株式発行のひとつ
上場せずとも、株式発行によって資金調達することはできます。
いわゆる「出資」という資金調達方法です。
会社の資金調達には様々な方法がありますが、大まかに分けると内部資金調達と外部資金調達があります。
内部資金調達は自社の内部留保から資金調達します。
受取手形の割引、売掛金の早期資金化、不動産の売却などがその代表です。
これに対し、外部資金調達は外部から資金調達するものです。
銀行や貸金業者からの融資が代表的ですが、社債発行や株式発行も外部資金調達に含まれます。
もちろん、社債付きの株式発行も外部資金調達の一種です。
株式発行による資金調達は、株式を買ってくれる人がいて初めて成り立ちます。
つまり出資者の存在が大前提です。
株主割当増資・第三者割当増資・公募増資などの増資は、既存株主や新規株主に対して株式発行を行います。
これが「出資を受ける」ということです。
上場・未上場に関係なく、出資者がいれば株式発行は成立します。
出資と融資は審査基準が大きく異なるため、銀行融資を受けられない会社でも、出資者がいれば株式発行で資金調達できるのです。
出資は難易度の高い資金調達方法のひとつであり、「融資が無理なら出資で」といった簡単なものではありません。
とはいえ、自社の状況や将来性次第で多額の資金調達につながることもあります。
株式発行の相手(出資者)の色々
増資・種類株式・新株予約権…と、株式発行のパターンを複数解説しましたが、実際のところ、誰に対して株式発行を行うのでしょうか。
株式発行の相手、すなわち出資者の代表はベンチャーキャピタルですが、それだけではありません。
主な出資者をみていきましょう。
ベンチャーキャピタル
出資で資金調達する場合、株式発行の相手として真っ先に挙げられるのがベンチャーキャピタルです。
名前からも分かるように、ベンチャーキャピタルは主にベンチャー企業に出資しています。
ベンチャー企業は事業実績が乏しく、業歴による信用の裏付けがありません。
また、担保を保有していないのが普通ですから、銀行から融資を受けることが困難です。
しかし、ベンチャー企業でも株式発行は可能です。
ベンチャー企業が株式発行し、それをベンチャーキャピタルが引き受けることで資金調達します。
ベンチャーキャピタルの目的は、キャピタルゲイン(株価の上昇による売却益)を得ることです。
株式発行会社が成長していき、やがて上場することで、ベンチャーキャピタルは多額のキャピタルゲインを得ることができます。
したがって、ベンチャーキャピタルに株式発行し、資金調達するためには、「非上場であること」「上場の見込みがあること」が条件です。
ベンチャー企業でなくとも、この条件を満たせばベンチャーキャピタルの出資対象となり、株式発行で資金調達できる可能性があります。
逆にいえば、上場の見込みがない会社や、あるいは上場を目指したくない場合は、ベンチャーキャピタルから資金調達することはできません。
非上場株式は、上場株式のように市場で自由に売買できず、ベンチャーキャピタルの「キャピタルゲインで稼ぐ」という目的に合わないため、「上場の見込み」が最大のポイントとなります。
上場を目指すにあたり、持ち株比率はさほど問題にならないため、ベンチャーキャピタルは必要以上の保有を目指しません。
株式発行会社は、必要調達額に合わせて株式発行を行います。
持ち株比率が低いことから、ベンチャーキャピタルは他の出資者よりも経営への干渉が軽く、出資を受けても比較的自由に経営できるのが利点です。
企業再生ファンド
上場を目指していない会社が株式発行で資金調達するならば、ベンチャーキャピタルは選べません。
その場合、企業再生ファンドへの株式発行が考えられます。
企業再生ファンドは、企業再生を専門とする出資者です。
経営悪化が深刻な会社に資金を提供し、再生を支援することで利益を得ています。
このことからも分かる通り、企業再生ファンドは上場にこだわりません。
非上場のままでも、再生の結果として利益が出れば良いと考えます。
したがって、企業再生ファンドが株式発行を引き受けるのは、再生の余地がある会社に限られます。
企業再生ファンドの資金提供は、株式発行によって行うのが基本です。
このとき、企業再生ファンドはある程度高い持ち株比率を目指します。
持ち株比率が低ければ、企業再生ファンドの影響力も小さく、支援対象の会社に強く働きかけることはできません。
経営にまずいところがあって経営が悪化したのですから、会社任せでは企業再生はおぼつかないでしょう。
そこで企業再生ファンドは、再生の主導権を握るために一定以上の支配権(保有率)を求めます。
それだけに、株式発行によって多額の資金調達も可能ですが、経営への干渉度はベンチャーキャピタルよりも高いと考えてください。
株式発行会社が再生すれば、株式の価値は上がり、キャピタルゲインを得ることができます。
再生後に上場し、企業再生ファンドが上場益を得ることもないわけではありません。
しかし、他のファンドや事業会社に株式を売却するのが一般的です。
再生を目指す会社が株式発行で資金調達する場合、企業再生ファンドも出資者の候補になるでしょう。
事業会社
ベンチャーキャピタルや企業再生ファンドは、投資・出資を専門とする会社・機関です。
もちろん、出資を専門としていない会社に株式発行し、資金調達することもできます。
例えば、事業会社への株式発行が考えられます。
株式発行を引き受ける事業会社にも本業があり、その事業戦略の一環として出資するのが特徴です。
したがって、同業他社や取引先、隣接業界などが株式発行を引き受けることが多いです。
あくまでも事業会社の戦略に基づいて出資するため、「戦略上、必要かどうか」が判断基準となります。
戦略に欠かせないと思えば、事業会社は積極的に出資してくるでしょう。
事業会社の出資は大規模なものです。
小規模の出資では持ち株比率が低くなり、株式発行会社への影響力も小さいため、事業会社自身の戦略に協力させることはできません。
たくさんの株式を保有して支配権を強めてこそ、事業会社の戦略に役立つのです。
事業会社にとって最も好都合なのは、事業会社の意思によって株式発行会社を自由に動かすことです。
そのために、事業会社は子会社化を目指して出資します。
株式発行会社を子会社化するために、必要となる持ち株比率は1/2超です。
事業会社に株式発行すれば、既存株主が受ける影響はかなり大きく、経営への干渉も甚大になります。
子会社になった以上、常に親会社(出資者・事業会社)の意向に左右され、自由な経営はできません。
事業会社の経営戦略に必要である限り、その状況は続きます。
ベンチャーキャピタルの影響は「株式発行から上場まで」、企業再生ファンドの影響は「株式発行から再生完了まで」というように明確な区切りがありますが、事業会社にはそのような区切りがないのです。
近年、M&Aが企業戦略に活用されるようになり、事業会社に対する株式発行のケースが増えています。
存続のためには子会社化もやむなしと考えているならば、事業会社への株式発行も十分にあり得るでしょう。
個人投資家
最後に、個人に対する株式発行。
ベンチャーキャピタル・企業再生ファンド・事業会社に株式発行する場合、第三者割当増資が一般的です。
既存株主に株式発行する株主割当増資や、不特定多数に株式発行する公募増資では、出資者の目的に適いません。
これに対し、個人投資家に株式発行する場合、株主割当増資や公募増資も考えられます。
既存株主が株式発行に応じてくれるならば、株主割当増資でも資金調達できます。
従業員が多い会社は、小口の出資を集めることで、それなりの規模で株式発行することも可能でしょう。
しかしながら、小規模な会社は既存株主が少なく、株主の資金力が乏しいことも多いです。
公募増資となると、広く募ったところで出資者が見つからず、資金調達に全く不向きということも考えられます。
そこで、個人に出資を募る場合にも第三者割当増資が役立ちます。
いわゆる「エンジェル投資家」などが株式発行の対象です。
もっとも、エンジェル投資家は創業期のベンチャー企業に出資するケースがほとんどですから、業歴の長い会社はマッチングの段階でつまずくことが多いです。
個人投資家も株式発行の対象ではありますが、「選択肢のひとつ」「機会があれば」程度に考えておくのが無難でしょう。
上場を目指す場合のコスト
上記に挙げた出資者のうち、最もポピュラーなのはベンチャーキャピタルです。
ベンチャー企業でも、業歴が長い会社でも、ベンチャーキャピタルの目的にマッチすれば株式発行で資金調達できます。
とはいえ、ベンチャーキャピタルの出資は慎重に検討しなければなりません。
ベンチャーキャピタルに出資を受けた会社は、自社の方針とは無関係に上場を目指すことになります。
上場すれば株式発行で資金調達しやすくなる半面、上場するまでが大変です。
特に、上場するまでには多額のコストがかかります。
上場を目指さなければ、株式発行の調達コストは配当金が中心であり、配当率次第で抑えることも可能です。
しかし、ベンチャーキャピタルに株式発行して資金調達する場合、多額の上場コストを含めて調達コストを考えておく必要があります。
具体的にはどれくらいのコストがかかるのか、上場準備・上場時・上場後に分けてみていきましょう。
上場準備コスト
上場するまでに、一番コストがかかるのは上場準備です。
もちろん、上場準備期間が長期化するほどコストはかさんでいきます。
上場準備コストは以下の通りです。
- 上場準備のために採用する人材の人件費
- 監査報酬(年間1000~2000万円程度)
- 証券会社引受指導料(年間500万円程度)
- コンサルティング料(委託範囲によって年間500~1000万円程度)
- 内部統制システムの整備費用(2000~5000万円程度)
上場を見据えたシステムの整備には数千万円単位のコストがかかり、それ以外のコストも決して小さくありません。
一般的に、上場準備には1億円以上かかるといわれています。
上場時のコスト
上場時にも様々なコストがかかります。
コスト負担は上場時の一度きりですが、やはり数千万円はかかると考えてください。
- 上場審査費用(500~1000万円程度)
- 上場申請書類の印刷費用(500万円程度)
- 有価証券届出書・目論見書などの印刷費用(500万円程度)
- 広告費用(100~500万円程度)
- 証券会社引受手数料(株式発行規模により変動)
- IR関連費用(内容により変動)
上場時には新たに株式発行し、公募を実施します。
この時の公募価格・公募株数・引受手数料によって証券会社引受手数料が決まります(スプレッド方式)。
株式発行の規模が大きければ証券会社引受手数料も高額になるわけです。
ただし、この手数料は株式発行で調達した金額から差し引かれるため、実際にキャッシュアウトが生じることはなく、負担にもなりません。
引受手数料が大きいほど資金調達総額も大きいわけですから、むしろ望ましいといえるでしょう。
上場維持コスト
上場後は、上場の維持にコストがかかります。
具体的には以下の通りです。
- 証券取引所への支払手数料(年間50~200万円程度)
- 有価証券報告書等の印刷費用(年間500万円程度)
- 監査費用(年間1000~2000万円程度)
- 証券代行(株主名簿の書き換え業務など)に伴う手数料(年間300万円程度)
- 事業報告書・アニュアルレポート等の作成費用(年間500~1000万円程度)
- IRイベント実施費用(年間500万円程度)
- 内部統制システムの運用費用
上場維持コストも、年間で数千万円になります。
上場を廃止しない限り、多額のコストがかかり続けるのです。
自社にとって、株式発行で市場から資金調達できるメリットと、多額の上場コストがかかるデメリットはどちらが大きいでしょうか。
株式発行の際、ベンチャーキャピタルの出資を受ける会社は、この点を慎重に考えなければなりません。
株式発行と銀行融資を徹底比較!
株式発行以外にも様々な資金調達方法があります。
資金調達を円滑に行い、資金繰りを安定させるためには、自社の状況に応じて最適な資金調達方法を選ぶことが大切です。
株式発行以外の資金調達方法のうち、最も利用されているのは銀行(民間金融機関)融資です。
銀行融資は調達コストが安く、多額の資金調達にも対応しています。
まさに資金調達の王道であり、株式発行よりもポピュラーな資金調達といえるでしょう。
したがって、株式発行を検討する際、真っ先に比較したいのが「株式発行と銀行融資」です。
複数の観点から株式発行と銀行融資の違いを比較すると、株式発行の使いどころ、銀行融資との使い分けなどもみえてきます。
資金調達の難易度
資金調達方法の比較検討において、非常に重要なのが資金調達の難易度です。
基本的に、資金調達は明確な目標を以て行います。
「経常的な運転資金を資金調達したい」「売上が増加したので運転資金の増加分を資金調達したい」「設備投資のために資金調達したい」「赤字補填のために資金調達が必要になった」などなど、会社の状況によって資金調達の目的は異なります。
その目的を達成できない資金調達方法は選ぶべきではありません。
また、資金調達方法としては適切でも、資金調達の難易度が高ければ不適切です。
株式会社にとって魅力的な株式発行と、資金調達の王道である銀行融資を比較する場合にも、資金調達の難易度は最優先事項といえます。
結論からいえば、株式発行と銀行融資はどちらも難易度が高いです。
ただし、難易度が高い理由は異なります。
株式発行の難易度
株式発行の難易度が高い理由は、出資者がいなければ株式発行が成り立たないためです。
未上場の企業は知名度が低く、特に将来性がない限り不特定多数から出資を募ることができません。
特定の出資希望者と協議して株式発行に至るわけですが、そもそも出資者がいなければ株式発行で資金調達できないのです。
その場合、株式発行では1円も資金調達できないのですから、「株式発行は銀行融資よりもはるかに難しい」といえます。
銀行融資の難易度
銀行融資の難易度は、資金調達する会社によって大きく変わります。
それなりに業歴があり、業績・財務が良好な会社は、比較的簡単に資金調達できるでしょう。
逆に、業歴が短い会社や、業績・財務が悪化している会社は資金調達できない可能性が高いです。
株式発行と銀行融資の難易度と使い分け
資金調達の難易度を比較すると、使い分けもおのずから見えてきます。
株式発行の難易度は、主に出資者の募集によるものであり、銀行融資の難易度は、自社の信用力と経営状況によるものです。
銀行から高い評価を受けられる状況であれば、株式発行よりも銀行融資のほうがスムーズに資金調達できるでしょう。
銀行融資での資金調達が難しい場合、特に「現状の経営は苦しいが、将来性には自信がある」という会社は、株式発行を検討してみてください。
銀行融資の審査では、あくまでも現状を重んじます。
現在の返済力に問題がなければ融資しますが、問題があれば融資しません。
いくら将来性があっても、返済力が低い会社は明るい未来が訪れる前に倒産してしまう可能性が高いです。
銀行はそのような貸倒れリスクを負いません。
その点、株式発行は現状よりも将来性を重視します。
出資者は、将来的に得られるリターンを目的として出資するため、将来性があれば株式発行は成り立つのです。
将来性がある会社にとって、株式発行は銀行融資よりも資金調達しやすいでしょう。
資金調達の手間
次に、株式発行と銀行融資の手間を比較します。
株式発行の手間
株式発行は、資金調達に多くの手間がかかります。
株式発行など「出資による資金調達」は、資金調達方法の中でも特に手間がかかる方法です。
株式発行のデメリットでも述べた通り、株式発行は法規制への対応、株式発行後の税務処理などが複雑です。
株式発行を専門とする弁護士・税理士・コンサルタントなど、専門家の支援がなければ株式発行はできません。
銀行融資の手間
銀行融資の手間は、自社と銀行との関係によって異なります。
既に複数の銀行と取引しており、それなりに関係を構築している会社であれば、さほど手間をかけずに資金調達できるでしょう。
逆に、取引がない銀行から新規融資を引き出す場合は手間がかかります。
よくあるのが、まず預金口座を開設して自社を認知してもらい、徐々に取引を深めていく流れです。
当然ながら、融資実行に至るまでに手間がかかります。
ただし、銀行融資の実務負担はさほど大きくありません。
融資担当者や支店長との面談、書類の提出などによる負担はありますが、株式発行のように煩雑ではなく、どの会社でも対応できるレベルです。
株式発行と銀行融資の手間と使い分け
株式発行と銀行融資の手間を比較すると、株式発行は銀行融資よりもはるかに手間がかかります。
株式発行に至るまでの手間と労力を考えると、調達金額や資金使途によっては「株式発行よりも銀行融資のほうがはるかに簡単」というケースが少なくありません。
新規融資と比較しても、株式発行のほうが実務負担は大きいでしょう。
新規融資を受けるために、専門家のサポートはさほど重要ではありません。
税理士と相談しながら、普段から新規融資に有利な決算書を作っておくくらいのものです。
しかし株式発行は、専門家のサポートがなくては不可能です。
これは、専門的な知識・経験がなければ株式発行の実務に耐えられないということであり、株式発行の手間をよく表しています。
資金調達コスト
すべての資金調達にはコストがかかります。
資金調達コストは確実に資金繰りの負担になるため、コストが安いほど好都合です。
株式発行と銀行融資の資金調達コストを比較してみましょう。
株式発行の資金調達コスト
株式発行の資金調達コストは、株式発行する会社によって異なるため一概には言えません。
仮に、上場企業の中央値である3.5%と考えた場合、1000万円の資金調達に伴うコストは35万円です。
株式発行総数が1000株であれば、1株当たりの株価は1万円ですから、配当金を350円として株式発行します。
株式発行の資金調達コストを考える際のポイントは、株式発行後は配当金を毎年支払うという点です。
これは、「過去の利益剰余金の累積+今期の総利益」が、配当金の分だけ目減りすることを意味します。
株式発行で資金調達したことで利益率が低下し、経営が悪化しては本末転倒です。
なお、上記の通り、「株式発行=上場」として考える場合、上場(資金調達)に至るまでに多くのコストがかかります。
また、上場維持コストの負担も大きいです。
その意味では、株式発行の資金調達コストはかなり高いといえるでしょう。
銀行融資の資金調達コスト
銀行融資の資金調達コストは、主に金利です。
信用保証協会の保証付融資であれば、保証料を支払う必要があります。
銀行融資の金利は、優良企業ならば1%台での融資もあり得ますが、ごく普通の会社が信用金庫や信用組合から融資を受ける場合には3%近い設定になることもしばしばです。
基本的には、金利は年率2%、信用保証協会の保証料率は1.5%を目安にするとよいでしょう。
ただし、利息は借入期間中にわたって支払うのに対し、保証料は借入れの際に一括で支払うのが基本です。
金利2%、保証料率1.5%の条件で1000万円の融資を受ける場合、資金調達時に信用保証協会に対して15万円の保証料を支払うほか、銀行に対して約20万円の利息が発生します。
長期融資であれば、初年度は保証料と利息で約35万円、2年目以降は残債に対して年率2%の利息だけを支払う流れです。
株式発行と銀行融資の資金調達コストと使い分け
株式発行と銀行融資の資金調達コストの関係は、「株式発行>銀行融資」と考えるのが無難です。
特に、未上場企業が株式発行する場合、上場企業の中央値3.5%での株式発行は困難でしょう。
未上場企業は上場企業に比べて、将来性・成長力・収益力など様々な点で劣ります。
出資者にとってはリスクが高まるため、それなりのリターン(配当)がなければ株式発行は成り立ちません。
銀行融資も、融資先によって金利や保証料が変動しますが、変動の幅は軽微です。
貸倒れリスクが高いと判断すれば、高い金利で融資するよりも融資謝絶を選びます。
基本的には、金利2%・保証料1.5%の水準で調達可能です。
さらに、株式発行は一定の条件で配当を続けるのに対し、銀行融資の支払利息は返済とともに減っていきます。
総合的な資金繰り負担であれば、返済義務がない株式発行の方が優れていますが、純粋に資金調達コストだけを比較した場合、「株式発行>銀行融資」と考えましょう。
資金繰りの負担
調達コストは資金繰りの負担になります。
株式発行と銀行融資の資金調達コストの違いから、実際の資金繰りへの影響を比較してみましょう。
株式発行の資金繰り負担
株式発行の主なコストは配当金です。
株式発行の時点では資金繰り負担はほとんどありませんが、次回の配当日から配当金を支払う必要があります。
実際の資金繰り負担は配当金の設定によって異なりますが、配当金の分だけ利益が減少することは避けられません。
会社経営の目的は「利益を出すこと」ですから、本業から得られる利益は会社にとって非常に重要なものです。
利益率が高いほど多くの現金が残り、手元資金は潤沢になり、資金繰りに余裕が生まれます。
逆に、利益率が低下すれば手元資金が不足しやすくなり、資金繰りが苦しくなります。
株式発行をすれば、配当金として利益を分配しなければならず、利益率の低下は避けられません。
したがって、株式発行の際には配当による資金繰り負担に注意が必要です。
ただし、株式発行には資金繰りに対するメリットもあります。
株式発行によって資金調達した資金には返済義務がありません。
株式発行後、出資者の期待に反して利益が出なかったり、倒産したりした場合にも、株式の買戻しや弁済などは不要です。
銀行融資の資金繰り負担
銀行融資の主な調達コストは利息です。
信用保証協会を利用する場合には保証料もかかります。
銀行融資では、融資実行時の保証料(保証付融資の場合)、そして借入期間中の支払利息が資金繰りの負担となります。
ただし、銀行融資の資金繰り負担はこれだけではありません。
銀行融資は返済義務を伴うため、銀行に支払うのは「利息だけ」ではなく「元金+利息」です。
借入期間によって元金の返済額が変わるため、借入条件次第で資金繰り負担が大きく変わってきます。
借入期間が短い場合、毎回の元金返済額が膨らみ、資金繰りの負担が大きくなるため注意が必要です。
資金調達スピード
最適な資金調達方法を考えるにあたり、特に重要なのは資金調達スピードです。
株式発行と銀行融資の資金調達スピードを比較すると、使い分けが明確にわかります。
株式発行の資金調達スピード
株式発行の資金調達スピードには、これといった目安がありません。
基本的には、「株式発行でスピーディな資金調達は不可能」と考えてください。
株式発行に至るまでには多くの手続きが必要です。
専門家のサポートを受け、出資者と協議を重ね、多くの手続きを踏んでようやく株式発行に至ります。
この手続きが難航するほど資金調達に時間がかかり、途中で頓挫して一からやり直しということもあり得ます。
株式上場の現場でも、予定日の直前で上場を中止するケースが珍しくありません。
上場中止の理由は様々ですが、内部管理体制や社内規程が問題となるケースが多いです。
上場を目指している会社でさえ手続きに失敗することがあるのですから、一般の会社が株式発行に失敗する、株式発行までに予想以上の期間を要するといったことは十分に考えられます。
銀行融資の資金調達スピード
銀行融資も資金調達スピードが遅いとされます。
銀行は時間をかけて審査するため、融資実行までに早くて数週間、一般的には1ヶ月程度を要するのです。
もちろん、融資の申し込みから数週間後に「融資不可」となり、他の銀行に融資を申し込んだ場合にはもっと時間がかかります。
株式発行と銀行融資の資金調達スピードと使い分け
株式発行と銀行融資の資金調達スピードは明らかに異なります。
株式発行で分かっているのは「資金調達に手間と時間がかかる」ということだけで、具体的な目安はありません。
もちろん、株式発行をサポートする専門家は「これくらい」という目安を教えてくれるでしょう。
しかし、あくまでも「株式発行での資金調達を決定→専門家に依頼→株式発行の時期が徐々に具体化」という流れですから、資金調達方法を検討している時点では不明です。
一方、銀行融資には「1ヶ月程度」という目安があり、銀行や会社によって極端にブレることはなく、2ヶ月、3ヶ月と長期化することはありません。
つまり、株式発行は計画的な資金調達には不向き、銀行融資は計画的な資金調達が可能、という違いがあるのです。
事前に立てた資金繰り計画に基づき、「〇日に〇万円の不足が発生、×日までに株式発行」といった資金調達はできません。
このようなリミットがある場合、銀行融資で計画的に資金調達するべきです。
財務への影響
資金調達を行った際には、財務に様々な影響が表れます。
株式発行と銀行融資の財務影響度を比較していきましょう。
株式発行の財務影響度
株式発行は、財務への好影響が期待できます。
この記事の冒頭でも述べた通り、株式発行はエクイティファイナンスに分類される資金調達方法です。
株式発行で調達した資金には返済義務がなく、返済義務がない資金のことを特に「自己資本」といいます。
総資本は、返済義務がある「他人資本」と返済義務がない「自己資本」によって構成されており、総資本に対する自己資本の比率を自己資本比率といいます(自己資本÷総資本=自己資本比率)。
様々な財務指標の中でも、自己資本比率は特に重要です。
株式発行で調達した資金は自己資本となるため、「自己資本の増加→自己資本比率アップ→財務改善」という影響が期待できます。
株式発行の財務改善効果を具体的にみてみましょう。
例えば、他人資本が8、自己資本が2であれば総資本は10、自己資本比率は20%です。
自己資本比率の目安は、50%以上を優良、30%以上を良と考えます。
業種にもよりますが、30%以下の場合には問題視されることが多く、20%は危険な水準です。
この会社が株式発行で2の資金を調達した場合、他人資本8、自己資本4、総資本12へと変化し、自己資本比率は約33%に上昇します。
つまり、株式発行によって自己資本が「20%→33%」へ、危険な水準から適正な水準に改善したのです。
このように、株式発行は財務に良い影響を与えます。
銀行融資の財務影響度
銀行融資は、株式発行とは真逆の影響を受けます。
銀行融資で資金調達すると、財務が悪化するのです。
これも、自己資本比率を考えるとよくわかります。
銀行融資には返済義務があるため、借入金は他人資本に分類されます。
自己資本が増えることはないため、総資本に占める他人資本の比率が上がり、自己資本の比率は相対的に下がるというわけです。
こちらも簡単に計算してみましょう。
他人資本が6.5、自己資本が3.5の場合、総資本は10、自己資本比率は35%となります。
自己資本比率35%は、特に良いとはいえないものの悪くない数値です。
この会社が銀行融資で3.5の資金を調達すると、他人資本10、自己資本3.5、総資本13.5に変化し、自己資本比率は約26%に低下します。
つまり、銀行融資で資金調達したことにより、自己資本比率が適正な水準の35%から危険な水準の26%に低下したのです。
このように、銀行融資は「他人資本の増加→自己資本比率の低下→財務悪化」という影響が生じます。
株式発行と銀行融資の財務影響度と使い分け
株式発行と銀行融資は、財務に真逆の影響が表れます。
株式発行は財務改善、銀行融資は財務悪化という影響です。
財務影響度だけを考えれば、銀行融資よりも株式発行の方が優れています。
ただし、株式発行と銀行融資の実際の影響は、会社によって異なります。
自己資本比率が低い会社にとって株式発行は財務改善に効果的ですが、すでに自己資本比率が高い会社であれば改善効果は限定的です。
このような会社は、銀行融資によって他人資本が少々増えたところで、深刻な財務悪化にはなりません。
その場合、あえて株式発行で資金調達するよりも、銀行融資で資金調達したほうが有利ということが十分にあり得るのです。
株式発行と銀行融資を使い分ける際には、同じ金額を資金調達した場合の財務への影響を比較し、総合的に判断しましょう。
企業価値への影響
資金調達することにより、企業価値に影響を与える場合があります。
株式発行と銀行融資は、企業価値に異なる影響を与えるため、それを比較してみましょう。
株式発行の企業価値への影響
株式発行のメリットでも述べた通り、株式発行は企業価値の向上につながります。
株式発行で資金調達できるのは、投資家の目に留まる会社だけです。
株式発行に応じる投資家がいなければ、いくら株式発行しても資金は集まりません。
つまり、「株式発行に成功した」という事実そのものが「投資家からの支持を得ている」ことの証拠であり、将来性に注目が集まっていることを意味します。
当然ながら、株式発行に成功すれば、投資家以外からの評価も高まるでしょう。
まず、銀行からの評価が高まります。
銀行の融資審査では返済力を重視し、基本的には本業からの利益を返済原資とみなします。
しかし、利益だけですべてを判断するわけではなく、利益以外からも収益力や返済力を判断するのが普通です。
分かりやすいのが不動産担保や信用保証協会の保証。
これらの担保・保証によって貸倒れリスクを回避できる場合、本業の収益力に多少問題があっても融資してくれます。
同様に、資金調達余力も返済力の源泉とみなすことが多いです。
例えば、融資検討先が多くの銀行から信用を得ており、銀行融資によって多額の資金を調達できる場合、銀行は資金調達余力を返済余力とみなして融資できます。
同様に、将来性がある会社は株式発行によって資金調達できるため、その資金調達余力を根拠に融資できるというわけです。
このように、株式発行は企業の価値・評価に良い影響を与えます。
もちろん、他の取引先も同じです。
株式発行で資金調達できる会社は、今後事業規模が拡大していく可能性が高く、取引先にとっての重要性も高まります。
だからこそ、「株式発行に成功→取引強化→仕入れ条件や販売条件の改善」といった影響も見込めます。
このほか、株式発行によって企業価値・評価が向上すれば、新規取引先との関係にも良い影響が期待できるでしょう。
株式発行ができない無名の会社と、株式発行ができる有名な会社であれば、新規取引先にとって取引しやすいのは間違いなく後者です。
このように、株式発行は企業価値の底上げ、経営環境の改善につながります。
銀行融資の企業価値への影響
銀行融資でも、企業価値が向上することがあります。
上記の通り、銀行は資金調達余力を返済力の一部とみなすため、「銀行融資によって資金調達できた」という実績によって、銀行評価が向上することがあるのです。
基本的に、各銀行の評価基準には大差ありません。
銀行は金融庁の監督を受けており、金融検査マニュアルの影響下にあるため、融資判断が似通っています。
当然ながら、審査基準・評価基準が類似していることを意味します。
例えば4行と取引しているとして、メインバンクが支援から手を引いた場合、その他の3行も一斉に手を引くのが普通です。
これは、サブバンク3行に「最も支援すべきメインバンクが手を引いた→補完的位置づけにあるサブバンクが積極支援すべき理由がない」という、共通の判断基準があるためです。
逆も然りで、複数行から積極支援を受けられる会社は、それ以外の銀行からの評価も高まります。
実際に、「他行が高く評価し、積極的に支援している→自行からもぜひ融資したい」といった判断につながり、新規の銀行から融資提案を受ける機会が増えるのです。
以上のように、銀行融資によって資金調達し、返済実績を積み重ね、資金調達余力を高めていくことによって、企業価値・評価は向上していきます。
もちろん、上記の通り借入金は他人資本であり、銀行融資は自己資本比率の低下につながります。
また、過度な借り入れには資金繰り負担の増加、返済力の低下、債務超過の危険など、様々なリスクがあるため、一概に「銀行融資→企業価値向上」とはいえません。
株式発行と銀行融資の使い分け
株式発行で資金調達すれば、企業価値は確実に向上します。
株式発行により社会的な知名度や信用が高まり、市場や金融機関、取引先など、多方面からの評価が高まるのです。
銀行融資も企業価値・評価の向上につながりますが、評価してくれるのは主に金融機関です。
銀行融資に成功したからといって、株式発行のように知名度が高くなったり、取引先からの評価が高まることはありません。
したがって、企業価値への影響を比較すると、銀行融資よりも株式発行の方が優れています。
資金調達を通じて企業価値の向上に取り組みたい場合には、株式発行を検討するとよいでしょう。
ただし、株式発行で資金調達できるのは、投資家の支持を得られる会社、すなわち「資金調達の時点で、企業価値をある程度評価されている会社」に限られます。
この点をクリアできない会社は株式発行が不可能となるため、銀行融資を選ぶべきです。
「融資に頼らない資金調達」にはファクタリングという選択肢も
上記で比較した通り、株式発行と銀行融資はどちらも一長一短です。
株式発行を銀行融資を比較すると、資金調達の難易度や資金調達スピードなどの問題点が浮き彫りになります。
また、株式発行で資金調達するには「出資者がいること」が前提となるため、現実的に株式発行を選べない中小企業も少なくありません。
中小企業が株式発行を検討する際、特に重視されるのは「融資ではない」ということであり、これは株式発行による資金調達の最大のメリットとなり得ます。
それは負債も増やさず貸借対照表への悪影響もないなど、融資に頼った資金調達の危険性をクリアすることが可能だからです。
しかし売掛債権を売却して資金へと変える「ファクタリング」も、株式発行同様に融資ではない資金調達方法の1つとなります。
ファクタリングは特に売掛債権によって資金繰りが圧迫されている企業にとっては、非常に頼りになる資金調達方法です。
ファクタリングを利用するメリット
売掛債権の売買契約であるファクタリングは融資ではなく、負債も増やさず担保も保証人も必要ありません。さらに最短即日での現金化も期待でき、売掛先の状況が審査で重要視され、利用者が赤字経営でも影響が小さいことから、融資の審査に通過できなかった企業も利用できる確率が充分にあります。
このような理由から、中小企業や個人事業主様にとって利用しやすい資金調達方法と言うことができるのです。
ファクタリングなら「株式会社No.1」
株式会社No.1のファクタリングの特徴は以下があります。
- 業界最低水準の手数料
- 手数料以外の費用なし
- 債権譲渡登記留保可能
- オンライン審査&オンライン契約対応
- 最短30分での即日振込可能
ファクタリング手数料の相場は2社間ファクタリングで10%から30%、3社間ファクタリングでも1%から10%と言われています。しかし株式会社No.1は2社間ファクタリングで5%〜15%、3社間ファクタリングなら1%〜5%と、低い手数料での債権の現金化を行っていただけます。さらに全国対応可能であり、日本中のどこからでも申し込みをしていただくことができます。必要な書類をスムーズにご用意していただければ、お申込みから最短30分での振込も可能など、No.1は名前の通りの業界トップのサービスで、資金調達のお手伝いをさせていただきます。
まとめ:融資に頼らない資金調達はNo.1におまかせ
資金調達には融資以外の選択肢を持つことが非常に重要です。会社経営において融資に頼り切ってしまうのは、債務超過や貸借対照表の肥大化など様々なリスクを背負うことになります。しかし株式発行やファクタリングなどの「融資に頼らない資金調達」を上手く活用することで、リスクを少なくし資金繰りの健全化の実現が可能となります。
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。
よく見られているファクタリング記事