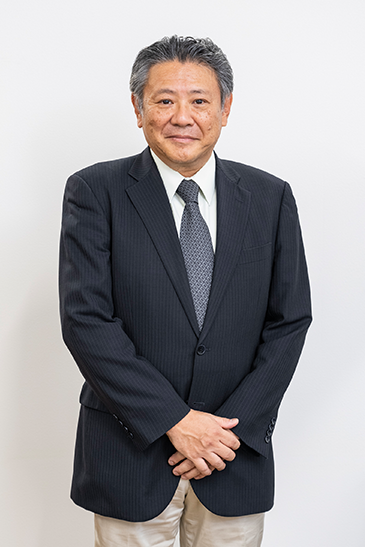カテゴリー: 助成金・社内制度
絶対にやってはいけない 助成金、補助金の不正受給!
助成金や補助金は企業が行なった活動に対して、行政が妥当と認めた場合に一定額を助成・補助するもので、大きな括りでいうと税金を原資としたものです。
従って、そのような助成金や補助金を不正に受給すると、ペナルティの対象となります。
では、どのようなペナルティがあるのでしょうか?
この記事では、助成金・補助金の不正受給について解説します。
どのような行為が不正受給になるのか?
助成金・補助金は、国が企業を支援するための制度です。
助成金は厚生労働省が、補助金は経済産業省が実施しています。
助成金・補助金はそれぞれ仕組みが異なるものの、あくまでも国から支給されるものであり、返済義務がありません。
返済義務がある銀行融資や、返済義務はなくとも経営に干渉を受ける出資などに比べると、負担が少ない資金調達方法といえます。
それだけに活用したいと考える会社も多いわけですが、助成金・補助金の受給には一定のハードルがあり、全ての会社が受給できるとは限りません。
本来受給できない会社が受給した場合、不正受給とみなされます。
具体的には、どのような行為が助成金・補助金の不正受給になるのでしょうか。
助成金・補助金の不正受給とは?
まずは、助成金・補助金の不正受給の定義を知っておくべきです。
助成金の不正受給について、厚生労働省は以下のように述べています。
「偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金を受け、または受けようとした場合、助成金は不支給または支給を取り消しします」
これによれば、本来受け取ることのできない助成金・補助金を受けることが、不正受給といえるでしょう。
実際に受給しなくても不正受給に
厚生労働省の不正受給に関する文言の中で、特に注目したいのは「または受けようとした場合」という部分です。
本来受給できない助成金・補助金を受給した場合、それが不正受給に該当することは容易に理解できます。
しかし、助成金・補助金の不正受給は、実際の受給とは無関係です。
不正受給を図ったとみなされた会社は、実際には受給していないとしても不正受給に該当します。
例えば、不正な書類を提出し、審査時に不正受給が発覚した場合、その時点で不支給となるため助成金・補助金を受け取ることはできません。
それでも、「不正受給を図った」ということが明らかであれば、不正受給として様々なペナルティが課せられるのです。
実際に受給できず、しかも不正受給として厳しく処罰されるのですから、デメリットしかありません。
「知らなかった」では済まない
助成金・補助金の手続きは煩雑です。
また、制度の内容が年々改定されることから、変更点を逐一抑え、正確に利用することは非常に難しいといえます。
会社が全て独力で手続きすることは現実的ではありません。
助成金の手続きは社労士に依頼するのが一般的です。
補助金の場合、労務の専門家である社労士の専門外となることも多く、補助金を専門とするコンサルタントに依頼することも考えられます。
専門家の支援を受けながら助成金・補助金を活用することは、不正受給を避ける上でも必要なことです。
専門家に依頼したことで安心し、実際の申請手続きにはあまり関心を持たない経営者もいるでしょう。
しかしながら、専門家を頼ったことで、却って不正受給になるケースもあります。
よくあるのが、助成金・補助金の専門家を謳う悪質業者に依頼し、不正受給が発覚してペナルティを課せられるというもの。
この場合、経営者は「依頼しただけ」「全て任せていた」「不正受給のつもりはなかった」と思うでしょうが、それでも許されるものではありません。
厚生労働省は、助成金の不正受給について以下のように述べています。
「助成金の支給申請事務を代理人に委ねていたとしても、事業主名で申請がなされる以上、その内容が不正受給に該当する場合には、事業主も不正処分の対象となります」
助成金・補助金の不正受給は、「知らなかった」では済まされないのです。
助成金・補助金の不正受給の例
具体的には、どのような行為が助成金・補助金の不正受給になるのでしょうか。
まず発注書や請求書などを偽造してやってもいない活動で助成金や補助金を申請するのはもってのほかです。
それだけではなく、よくあるケースですが発注書の日付を改ざんして、過去に支払った費用を申請することもやってはならないのです。
「ものづくり補助金」や「IT導入補助金」は補助される事業の実施期間があらかじめ決まっています。
ですからあらかじめ定められた事業実施期間以外の発注は、その補助金の対象外となります。
発注書の日付の改ざんとは期間外の発注にもかかわらず、発注書の日付を改ざんするというものです。
これは公募要領にも禁止事項として明確に書かれています。
このように公募要項に禁止行為と書かれていることは、悪気がないとはいえ決してやってはいけないことなのです。
不正受給を行うとどうなるのか?
万一、助成金や補助金の不正受給を行うと、どのようなペナルティが課せられるのでしょうか。
具体的に見ていきましょう。
助成金・補助金の返還
厚生労働省は、助成金の不正受給に関して、「支給決定後に不正受給が発覚した場合、助成金を返還していただきます」と明言しています。
もちろん、助成金の不正受給だけではなく、補助金の不正受給も返還しなければなりません。
助成金・補助金を受給するまでには、様々なコストが発生しています。
例えば、雇用関係助成金を受給するために、正社員化や賃金増額に取り組んだ会社であれば、人件費は確実に上がっているわけです。
不正受給の場合、実際には受給に必要な処置を行わないため、コスト負担は抑えられるでしょう。
とはいえ、コストゼロで不正受給が成り立つものではありません。
要件を満たしていると見せかけるために、部分的に取り組みを行った場合、それだけのコストは確実に発生しています。
また、不正受給を主導する専門家に対し、報酬も支払わなければなりません。
それらの先行コストを負担した末に助成金・補助金の受給があるのです。
一旦は受給できても、支給後に不正受給が発覚して返還するならば、それまでに負担したコストが全てマイナスとなります。
さらに、返還すれば不正受給が許されるというものではなく、不正受給のペナルティは確実に降りかかってきます。
下記の通り、社会的に信用を失ったり、違約金・加算金を請求されたり、様々な点でマイナスになるのです。
「不正受給に成功して助成金・補助金を獲得するメリット」よりも、「不正受給が発覚してペナルティを受けるリスク」の方がはるかに大きいことが分かります。
担当省庁のホームページに公表される
助成金・補助金を不正受給した会社は、信用が失墜するでしょう。
というのも、助成金・補助金の不正受給は公表されるためです。
厚生労働省は、助成金の不正受給について以下のように明言しています。
「不正受給は、企業名公表・刑事告訴の対象となる場合があります」
不正受給が刑事告訴の対象となるかどうかは、不正受給の悪質性によりけりです。
しかし、企業名の公表は避けられません。
実際、不正受給が明るみになると、「助成金・補助金交付等停止措置企業」として経済産業省や厚生労働省などの担当省庁のホームページに事件が実名で掲載されます。
近年、助成金や補助金への関心が高まっていることにより、場合によってはメディアに報道されるようなケースもあるかもしれません。
後述の通り、助成金・補助金の不正受給は犯罪です。
「助成金・補助金を不正受給した」ということは、「犯罪に手を染めた」ということにほかなりません。
したがって、不正受給のために会社名が公表された場合、信用の失墜は避けられないでしょう。
取引先の多くは、不正受給の事実を重くみます。
なんといっても、助成金・補助金の不正受給は詐欺罪です。
助成金・補助金を不正受給した会社に対し、仕入先や販売先が「詐欺をはたらく会社とは取引したくない」と考えることは、想像に難くありません。
取引先の銀行も同じです。
銀行は信用を重んじるため、信用できない会社には融資しません。
助成金・補助金の不正受給が発覚した会社を信用し、融資してくれる銀行はないのです。
不正受給をしたとなれば、取引銀行は一斉に手を引くでしょう。
社会的信用だけが理由ではありません。
助成金・補助金の不正受給により取引先企業が手を引けば業績悪化は避けられず、利益の減少、場合によっては赤字ということも十分にあり得ます。
銀行が返済原資とみなすのは、本業から得られた利益だけです。
その利益が得られないとなれば、銀行は「返済力に問題あり」「貸倒れリスクが高い」と判断し、融資謝絶という流れがごく自然なのです。
このように、助成金・補助金の不正受給は融資環境の悪化につながり、資金繰り難を引き起こします。
不正受給をきっかけに業績・財務が悪化していき、行きつく先は倒産ということにもなりかねません。
信用が失墜することを考えると、「企業名公表」は非常に重いペナルティといえます。
詐欺罪で告訴される
上記でも引用しましたが、厚生労働省は助成金の不正受給に対し、「不正受給は、企業名公表・刑事告訴の対象」と明言しています。
助成金・補助金の不正受給により、詐欺罪で刑事告訴される恐れがあるのです。
このことについて、厚生労働省は「不正受給は『刑法第246条の詐欺罪』等に問われる騎亜脳性がある」としています。
実際に、不正受給が刑事告訴に至ったケースがあります。
数年前、スーパーコンピューター開発を手掛ける企業が、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成・補助金を不正に受給したニュースを記憶されている方も多いかもしれません。
経済産業省はこの会社に助成金・補助金交付等停止措置を講じただけではなく、代表取締役社長を詐欺罪で提訴したというものです。
このように、助成金や補助金の不正受給は立派な犯罪ということなのです。
助成金・補助金の不正受給が刑事告訴に至るかどうかについて明確な基準はなく、厚生労働省は単に「悪質な場合」としています。
何をもって「悪質」と判断するかが分からない以上、助成金・補助金を活用する会社としては、不正受給につながる一切の行為を慎むほかありません。
延滞金・違約金の請求
上記の通り、助成金を受給し、後に不正受給が発覚した場合には返還を求められます。
助成金などは数万円~数十万円を受給することも多く、不正受給の発覚後、速やかに返還することも可能でしょう。
しかし、助成金の中にも、使い方次第で数百万円単位で受給できるものがあります。
最近では、支給上限額を数千万円に設定する助成金も増えてきました。
そのような多額の不正受給が発覚した場合、すぐに返還するのは難しいでしょう。
また、不正受給後しばらく経ってから発覚し、返還を求められることも。
いずれにせよ、不正受給から返還まで一定の期間を要するわけですが、その間、延滞金が発生します。
延滞金は、助成金を受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年3%です。
さらに、不正受給から返還までの期間に関係なく、不正受給額の20%が違約金として請求されます。
例えば、300万円の助成金を不正受給し、1年後に発覚したとしましょう。
この場合、不正受給の発覚により、不正受給額に20%を上乗せした360万円の返還が確定します。
さらに、不正受給が発覚するまでの1年間について、年3%(9万円)の延滞金が上乗せされます。
返還請求に素早く対応しても、369万円を支払わなければなりません。
300万円の部分は、元々不正受給したものですから、プラスマイナスゼロです。
しかし69万円の部分については、不正受給していなければ支払う必要のなかったものであり、完全にマイナスといえます。
加算金を請求される
上記の延滞金・違約金は、助成金の不正受給に対するペナルティです。
補助金の不正受給には、別のペナルティが設けられています。
補助金の不正受給が明るみになったときは、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」によって返還しなければいけません。
その際、不正受給のペナルティとして加算金を請求されます。
具体的にはこの法律の19条として、次のように加算金に関する事項が定められています。
「第19条 補助事業者等は 第17条第1項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。」
受け取った金額について、全額返金させられるだけでなく、年10.95パーセントもの加算金が追徴されるのです。
銀行融資の金利が年2~3%であることを考えると、年10.95%の加算金は非常に重いペナルティといえます。
補助金は助成金よりも受給のハードルが高く、支給額も大きく設定されています。
数千万円を受給できる補助金も多いです。
それだけに、不正受給が発覚して返還を求められても、すぐに対応することは難しいでしょう。
その場合、返還が完了するまでの期間、高額の加算金が発生し続けます。
例えば、ものづくり補助金の支給上限額は4000万円です。
4000万円の補助金を不正受給し、1年後に発覚した場合、その時点で加算金438万円の上乗せが確定します。
これだけの加算金をポンと出せる会社は少ないでしょう。
何とか438万円を返還しても、不正受給した4000万円は残っており、年10.95%の加算金が発生し続けるのです。
加算金さえ支払えないとなれば、不正受給4000万円+加算金に対して年10.95%が上乗せされ、返還額は複利で増え続けます。
雪だるま式に増え続け、経営破綻は時間の問題です。
補助金の不正受給は、助成金の不正受給のように「不正受給額の〇%(違約金)」といった上乗せがないものの、延滞金に相当する追徴が高額なため、不正受給によるダメージは計り知れません。
助成金・補助金を利用できなくなる
最後に、一定期間にわたって助成金・補助金を受給できなくなること。
これも大きなペナルティです。
不正受給を行った会社は、その後5年間にわたって助成金・補助金を受給できなくなります。
この5年間で、会社は様々な取り組みをしていくはずです。
その中には、助成金・補助金の支給対象となる取り組みもあるでしょう。
助成金・補助金は、活用の機会を的確につかみ、もれなく受給していくことが重要です。
しかし、不正受給をすれば、それもできません。
不正受給から5年が経過すれば、再び助成金・補助金を申請できるようになります。
要件を満たせば受給も可能です。
とはいえ、5年で不正受給の事実が消え去るわけではありません。
不正受給で失った信用を、5年で回復することは難しいでしょう。
もちろん、厚生労働省や経済産業省には、不正受給の記録が残り続けます。
「また不正受給をしていないか?」という目線で審査され、受給しにくくなることもあり得ます。
もちろん、再び不正受給した場合の対処は、かなり厳しいものになるはずです。
1回目の不正受給では刑事告訴に至らずとも、2回目となれば「悪質」とみなされ、刑事告訴に至る可能性が高いです。
不正受給から5年間は助成金・補助金を利用できず、5年後以降も不正受給の経歴がついて回るのですから、これだけでも不正受給のペナルティは重いといえます。
助成金・補助金の不正受給の実態
助成金・補助金の不正受給と、そのペナルティについて解説してきました。
最後に、助成金・補助金の不正受給の実態について簡単にみていきましょう。
助成金・補助金の不正受給の件数
助成金・補助金の不正受給の全体について、詳しい統計情報はありません。
厚生労働省の助成金のうち、最も広く活用されているのはキャリアアップ助成金です。
厚生労働省によれば、キャリアアップ助成金は毎年約7万件近く活用されており、そのうち約200件の不正受給が発覚しています。
7万件中200件ですから、不正受給の発生率は3%弱です。
これはキャリアアップ助成金に限ったものですが、母数が多いだけに、助成金・補助金の不正受給全体でみても大差ないでしょう。
このように、助成金・補助金の不正受給が発生していることは事実です。
不正受給の前に不支給決定に
上記の通り、不正受給の発生率は非常に低い水準です。
その理由は複数考えられますが、最大の理由は不正受給が現実的に難しいこと、そして不正受給が発生した場合のペナルティが重く、割に合わないからでしょう。
まず、助成金・補助金の不正受給は簡単ではありません。
厚生労働省や経済産業省は、不正受給防止のために様々な取り組みを実施しています。
例えば、実地調査がそのひとつです。
厚生労働省は、助成金の支給決定にあたり、事業所の実地調査を実施しています。
助成金を申請するすべての会社を調査することは不可能ですから、調査対象はランダムです。
しかし、実地調査は予告なく行われることも多く、その際、総勘定元帳や法定帳簿など、助成金に関する書類をチェックされます。
実地調査や書類のチェックを拒否した場合、助成金を受給できません。
不正受給の自覚がある会社は、実地調査に応えることができず不支給となり、不正受給にも失敗するというわけです。
もちろん、上記の通り、「不正受給を試みた」というだけで不正受給とみなされます。
実地調査を拒否した場合、不正受給の疑いありとして精査され、不正受給が発覚することも。
実地調査があることによって、不正受給のハードルがグッと上がるのです。
また、実地調査のほか、会計検査院の検査対象になることがあります。
不正受給をしている会社は、この検査を避けたいと考えるでしょうが、検査への協力に同意しなければ助成金は受給できません。
実地調査や会計検査が抑止力となり、助成金・補助金の不正受給の発生を抑えていると考えられます。
不正受給は割に合わない
助成金・補助金の申請書類は、一旦提出してしまうと差し替えは不可能です。
不正受給を図った場合、その書類が申請先の手元に残り続けます。
一旦は不正受給に成功しても、再度審査・調査すれば不正受給は発覚するでしょう。
多くの場合、不正受給は一度きりでは終わりません。
一度成功してしまうと、「案外バレないものだ」と思い、繰り返し不正受給に手を染めるのです。
そのようなことをすれば、いつか必ず不正受給が発覚し、過去の受給までさかのぼって返還を迫られ、多額の遅延金・違約金・加算金を請求されるでしょう。
以上のように、助成金・補助金の不正受給は容易ではなく、発覚・ペナルティの危険と常に隣り合わせです。
不正受給で助成金・補助金を獲得するメリットよりも、ペナルティのリスクのほうがはるかに大きいといえます。
結局、「不正受給は割に合わない」ということです。
不正受給を図るよりも、ごく普通に助成金・補助金を活用した方が、確実に良い結果につながります。
まとめ:助成金・補助金の不正受給は絶対しないこと
不正受給が明るみになると、助成金や補助金がもらえないだけではなく、社名公表や告訴により企業の社会的信用が大幅に失墜するペナルティが課せられます。
特に近年、助成金や補助金に関して社会的な関心が高まっているため、信用の失墜は経営に致命的な打撃を確実に与えかねません。
助成金や補助金は、あくまでも事業を円滑に行うために「助成・補助を受ける」ものです。
ですから社会的信用が失墜するリスクを企業が負うようなものではありません。
助成金や補助金の不正受給は絶対にするべきではありません。
コンサルタントと称する業者の中には、不正受給をそそのかす者もいるようですが、その口車に乗らないように注意すべきでしょう。
株式会社No.1の各サービスの紹介は下記からご覧ください。
ご不明点やご質問はお気軽にお問い合わせください。
よく見られているファクタリング記事